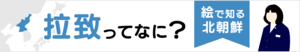蓮池夫妻編 <上>
断ち切られた夢と絆 「絶望」の中 生き続け 早期解決願い体験語る
「拉致は命以外の全てを奪う。『夢』を、『絆』を断ち切られた」。今月中旬、京都府長岡京市の平和集会。約300人の前で、柏崎市の拉致被害者で新潟産業大准教授の蓮池薫さん(60)が切々と語った。
16年前に帰国した薫さん、祐木子さん(62)夫妻ら5人以外、被害者が戻っていない悔しさも訴えた。「横田めぐみさんの家族らの訴えは、数年前までは『早く一緒に暮らしたい』だったが、最近は『意識があるうちに一目会いたい』になった。時間がない」
会場のパート女性(51)は「残された被害者を助けたいという強い思いが伝わった」としみじみ。
薫さんは近年、拉致体験などを公の場で語る機会が増えている。早期解決につなげるためだ。めぐみさんの母早紀江さん(82)は「帰国した5人は、日本に戻ってからも苦労が多々あったと聞く。そんな中、北朝鮮に残る被害者の救出へ声を上げてくださるのは、ありがたいこと」と語る。
■ ■

講演会で北朝鮮による拉致の現実や、早期解決に向けた思いを語る蓮池薫さん=京都府長岡京市
1978年7月31日夕。中央大学の学生で柏崎市に帰省中だった薫さんと、恋人の祐木子さんが中央海岸でデート中のことだった。
薫さんらによると、突然襲われて袋に入れられた後、ゴムボートから「工作船」へと運ばれていった。薬を打たれ、意識がもうろうとするうちに数日後、北朝鮮の港に着いた。だが港にも、平壌の「招待所」にも祐木子さんの姿はなかった。
「彼女はどうしたのか」「日本へ帰せ」。抗議に対し、係員は当初せせら笑う程度だったが、次第に「いつまで言っているんだ」と厳しい態度になった。命の危険を感じ、初めて「絶望」した。"軟禁生活"の中、まずは状況を理解しようと朝鮮語を覚えていった。
絶望の日々に光が差し込んだのは、祐木子さんの生存を知った時だ。80年に結婚し、後に長女と長男が誕生。日本の家族との絆を断ち切られた中、北朝鮮で新たな絆ができたのだ。
新たな夢もできた。かつては弁護士になることだったが、今度の夢は、親の責任として子供が北朝鮮で幸せに生きていける基盤を作り、教育していくことだった。ただ、その実現には「故郷に帰りたい」との思いを断つ必要があった。
「反日」の北朝鮮で差別されずに生きていくには「日本人」は不利。蓮池さん夫妻は相談し、子供には「帰還事業で北朝鮮に来た元在日朝鮮人」と言い続けることにした。また、将来子供が工作員に採用されるリスクを減らそうと、日本語を教えないことも決めた。
時に、柏崎市で息子の失踪を心配しているであろう家族の顔や、故郷の思い出が浮かぶ。その際は「故郷に帰りたいと思うことと、懐かしむことは違う」と自身に言い聞かせたという。
■ ■
北朝鮮で薫さんらが生き抜いている頃、故郷の父秀量さん(90)と母ハツイさん(86)は、海岸線を棒で突きながら歩いたり、東京など遠方を訪ねたりして探し続けていた。いつ戻ってもいいように東京の下宿先の家賃を払い、大学には休学届を出した。
80年1月に日本で初めて拉致の存在をスクープした元産経新聞記者阿部雅美さん(70)は今、79年に蓮池家を訪ねた記憶を語る。「当時は非公開だったが、苦しい胸の内を聞いてほしかったのかもしれない。親心に触れ、涙が出た」
薫さんの兄透さん(63)は「神隠しとしか考えられなかった中、阿部さんから初めて『北朝鮮』のキーワードを聞いた。当時はまさかと思ったが...」と振り返る。
後にその「まさか」が事実だったと証明される-。
「もう時間ない」蓮池夫妻
蓮池薫さん、祐木子さん夫妻は7月30日、1978年7月31日に拉致されて40年となるのを前にコメントを発表した。「(北朝鮮に残された)拉致被害者とその御家族には、本当にもう時間がありません」と早期解決を訴えた。
夫妻は2002年に帰国。「私たち家族の運命は北朝鮮に翻弄(ほんろう)され続けました」とした。
拉致問題は、北朝鮮が言うように「解決済み」ではないと強調。米朝関係の新たな展開が見える中、未来志向的な日朝関係の出発点となる被害者全員の帰国を北朝鮮に促した上で、日本政府に対し「全力を挙げて北朝鮮との交渉に取り組むことを再度強く求めます」と要望した。
(2018年7月31日 新潟日報朝刊掲載)
蓮池夫妻編 <中>
両親と偶然の"出会い" 望郷の念 帰国に淡い期待
「あっ。これ、おやじじゃないの」-。
1990年代後半のある日。北朝鮮のある場所で、日本の新聞を翻訳させられていた拉致被害者の蓮池薫さん(60)は偶然、ある記事の写真の中に、年老いた両親の姿を見つけた。
記事は、97年に結成された「『北朝鮮による拉致』被害者家族連絡会」(家族会)に関するもの。父秀量さん(90)が高校時代の薫さんの顔写真を掲げ、後ろには母ハツイさん(86)が立っていた。
薫さんは語る。「特に父は年齢以上に老けていたように見えた。それも自分のせいかと、ぎゅっと締め付けられる思いがし、酸っぱい胃液が込み上げてきた。いつしか望郷の念で胸がいっぱいになった」
ただ、「朝鮮人」と信じ込ませている長女や長男を今後も無事に育てていくには、この夢のような"遭遇"の感傷に浸らずに「早く現実世界に自分を戻さなければ」とも考えたという。
■ ■

「『北朝鮮による拉致』被害者家族連絡会」の会見で、蓮池薫さんの顔写真を手に、救出を訴える父秀量さん(中央)。後ろは母ハツイさん=1997年3月、東京・参院議員会館
長年、日本では拉致への関心は極めて低かった。88年に梶山静六国家公安委員長(当時)が、薫さんや祐木子さん(62)を含む一連のアベック行方不明事案を「拉致の疑いが十分濃厚」と明言。だがこの歴史的答弁は2紙が小さく扱っただけで、ほとんど国民に知られることはなかった。
拉致事件を長年追い続けるジャーナリストの石高健次さん(67)は「ずっと『拉致なんてうそだろう』という空気だった。政府やメディアも黙殺に近い対応を続けていた」と話す。
ところが97年2月、日本の世論が動き始める。従来のような成人ではなく、13歳だった少女の「拉致疑惑」が浮上したからだ。
この新潟市の横田めぐみさん拉致をきっかけとした関心の高まりをてこに、全国各地で孤立していた被害者家族が結束し、拉致解決を広く訴えていこうと、石高さんらも手伝い、同年3月に家族会が誕生した。
一方の北朝鮮。薫さんによると、97、98年頃から朝鮮労働党機関紙「労働新聞」で拉致関連の記事が載るようになった。論調の骨子は「拉致はねつ造」「日本反動勢力の策動」だった。
薫さんらの招待所に、労働新聞が届かない日も出てきた。理由を配達人に尋ねると「拉致関連記事の掲載日は配るなとの指示があった」とのことだった。
だが、それからしばらくたってから、薫さんは日本の新聞を翻訳中に家族会の記事を発見したという。
なぜ検閲の厳しい北朝鮮でこの記事を読めたのか。薫さんによると、当初は北朝鮮でも拉致は秘密事項で、検閲者にもほとんど知らされておらず、結果的に日本の新聞のチェックが不徹底だったなどの偶然が重なった可能性があるという。
■ ■
日本では年々「拉致疑惑」を追及する動きが加速していった。98年に柏崎市では薫さんの高校同級生の小山雄二さん(61)や野俣正一さん(60)らによる「再会をめざす会」が発足。薫さんの母校中央大では、重城拓也さん(43)を中心に「中大生を救う会」が結成された。
重城さんは「私の世代は『北朝鮮はタブー』との感覚はあまりない。理不尽にさらわれた人々を助けたい一心だった」と振り返る。
北朝鮮は、日本での世論の高まりを意識してか、薫さんらに、さらに山奥の招待所への転居を命じた。秘密保持のためとみられる。
薫さんは「長年『北朝鮮が拉致を認めるはずがない』という諦念があった。ただ、この頃から『ひょっとしたら何かが起きるのか...』というほのかな期待めいた思いが自分の中に浮かび始めたのかもしれない」と語る。
その数年後、蓮池さん夫妻ら5人は、「一時帰国」を命じられることになる。
(2018年8月1日 新潟日報朝刊掲載)
蓮池夫妻編 <下>
自由な日本で子育てを ひそかに日本名をつける
「北朝鮮で持てた自由は『考える自由』だけだ。むろん考えた本音は口外できなかったが」。柏崎市の拉致被害者、蓮池薫さん(60)は今、静かに語る。
2002年6月。山奥の招待所にいた薫さんと祐木子さん(62)夫妻は、平壌の高層アパートへの転居を命じられた。
当時北朝鮮は水面下で「ボートで漂流し、日本海で救助された後、平壌で幸せに暮らしている」との筋書きで、蓮池さん夫妻を「行方不明者」として公表し、両親を北朝鮮に面会に呼び寄せる計画を進めていた。
薫さんは当時の心境を「正直、両親と再会できる喜びより、子供の将来の不安の方が大きかった」と述懐する。ずっと信じ込ませてきた「元在日朝鮮人の子」ではなく、「在朝日本人の子」である事実が周囲に知られ、将来、不利な成分(身分)で扱われてしまうのでは-という懸念からだった。
ただ、同年9月17日の日朝首脳会談で北朝鮮は拉致を認めた。「行方不明者」の筋書きは放棄され、今度は、蓮池さん夫妻ら5人は拉致被害者としての「一時帰国」を指示された。
■ ■

中学校の特別授業で、拉致体験などについて語る蓮池薫さん=東京都立川市
「おはようございます」。同年10月15日、平壌空港の特別待合室。当時内閣官房参与の中山恭子参院議員(78)は、薫さんら5人にあいさつした。すると日本語で「おはようございます」と明るく返してくれた。また、日本への機内で政府関係者がブルーリボンバッジの着用を5人に依頼すると早速、無言ながらも淡々と胸に着けてくれた。
そんな姿に、中山さんは感じるものがあった。「5人は日本人の心を持ち続けている。子供らが北朝鮮に残る中、言えないこともあろうが『他にも被害者がいる』という無言のメッセージなのではないか」
「本音と建前」を区別して発言することが、北朝鮮での保身術とされる。当時のある政府関係者によると、5人は北朝鮮の担当者に日本行きを打診された際、当初は「日本に行く気などない」といった趣旨の回答をしたという。「北の担当者は『この5人ならば北に戻ってくる』と"信用"したのだろう」と推察する。
蓮池さん夫妻も当初は子供の残る北朝鮮へ戻るつもりだった。だが故郷の風景、家族や友人らと接するうちに「自由」な日本で子供を育てたい気持ちが高まった。悩んだ末、子供を呼び寄せるために全力を尽くすという政府を信じ、日本にとどまる「決断」をした。
子供を待ちわびた1年半余の様子について、薫さんの友人、吉田信一さん(63)は「楽しい話で笑っている時でも、ふと子供のことを考えてしまうのか、急に不安そうな顔になることがあった」と振り返る。
■ ■
04年5月22日の第2回日朝首脳会談後、子供が日本に着いた。実は薫さんは、北朝鮮で子供が生まれた時、朝鮮名と同時にひそかに日本名もつけていた。現在36歳の長女は「重代」、33歳の長男は「克也」-。そう伝えると「二人ともごく自然に受け入れてくれた」
さらに「日本には未来の目標を追う自由がある」と教えた。二人とも国内外での勉強を経て、現在は社会人として羽ばたいている。
薫さん自身も北朝鮮での24年間に固執せずに生きる決意を固めている。「拉致された過去にしがみついていたら、未来の人生まで"半分拉致"されたままの心境や状況になってしまう」
薫さんは毎日未明に起床し勉強に励む。中大に復学して卒業。翻訳家デビューを果たし、新潟産業大の准教授としても活躍中だ。
柏崎市内の保育園で働く祐木子さんは「日々やりがいがある」と笑顔。同僚も「てきぱきと仕事をこなし、園児にも明るく接してくれている」と感謝する。
薫さんは、全ての拉致被害者救出に向けて全国各地でこう訴え続けている。「拉致の解決とは、夢と絆を取り戻すことにある」と。
(2018年8月2日 新潟日報朝刊掲載)