第4弾 県北

新発田 実業家・大倉喜八郎と蔵春閣
偉人の遺産 活用探る
新潟日報 2020/11/23
新潟日報みらい大学の2020年度第3回公開講座「実業家・大倉喜八郎と蔵春閣」が11月8日、新発田市の市民文化会館で開かれた。新発田出身の喜八郎が東京・向島で1912年に建設した蔵春閣は、2012年に解体され、現在は市内で移築工事が進む。約360人の受講者を前に、東京大名誉教授で文化庁文化審議委員の藤井恵介さん(67)が、基調講演で文化的価値について解説。「ルーツを知れば、今が未来につながる」と題したトークセッションでは、有識者4人が喜八郎の功績や工事終了後の蔵春閣の活用方法などを語り合った。

大倉喜八郎の遺徳や蔵春閣の文化的価値について、登壇者が意見を交わしたトークセッション=新発田市の市民文化会館

<大倉喜八郎と蔵春閣> 喜八郎(1837~1928年)は18歳で江戸に転居すると、すぐに商才を発揮して実業家の地位を確立。現在の大成建設、サッポロビールなどの大企業を次々に設立して、近代日本の発展に貢献した。蔵春閣は1912年、喜八郎が東京・向島に迎賓館として建設。外観は木造2階建ての伝統的な日本建築だが、内装は和洋折衷の豪華なしつらえで1階に食堂と書斎、2階に33畳の大広間などがある。明治宮殿の様式を残し、政財界の要人を招いた。喜八郎死去後は所有者や用途が変遷し、2012年に解体・保存。17年、新発田市に寄贈、移築が決まった。
トークセッション
<トークセッション参加者>
藤井恵介さん
松尾浩樹さん(大成建設設計本部専門設計部部長)
坂井正さん(大倉喜八郎の会会長)
鈴木直之さん(ダイアグラム代表アートディレクター)
◇コーディネーター・間狩隆充(新潟日報社新発田総局長)
-蔵春閣を建てた大倉喜八郎とは、どんな人物か。
坂井さん 新発田城下で質屋をやっている裕福な家の三男として生まれ、18歳で江戸に出た。問屋のでっち奉公をし金をため、31歳で鉄砲の販売を始めた。明治に入り、欧米を視察、渋沢栄一と現在の東京商工会議所をつくった。大成建設や帝国ホテル、サッポロビールなどを設立し、近代日本の発展に大いに貢献した。建設した建物では、鹿鳴館、日本銀行、歌舞伎座。上野-浅草間の地下鉄も掘っている。社会教育や文化活動にも大いに貢献、東京経済大も創設した。新発田駅前にも大倉製糸工場を建設し、大勢の女性の働く場を提供した。
鈴木さん 存在は知っていたが、業績についてはほとんど知らなかった。蔵春閣の取り組みに参加し、伝記などを読み、新発田に偉大な方がいたと実感した。皆さんも自慢してほしい。
-いよいよ蔵春閣が新発田へ移築されるが。
松尾さん 候補地の中から東公園が選ばれたのは、交通の要所、多くの人が訪れる、2階からの眺望が良好などの理由だが、喜八郎が用地を寄付し整備した公園なのでゆかりがある。建物は将来、重要文化財にしたい。元のまま復旧できればいいが、東京にあったので雪に弱く、そのための改修や防災面での改修を実施する。2022年4月末に竣工(しゅんこう)の工程だ。
-蔵春閣を生かしたまちづくりをどうやるのか。
鈴木さん 駅前広場一帯の利活用と捉え、蔵春閣が移築される東公園が中心になる。移築工事期間中から、現場を囲む壁にいろんな人の写真を飾り、ここに何が建つかや、蔵春閣とはどんなものか知らせたい。朝の通学で多くの高校生が通る場所、若者にメッセージを伝え、自分と関係があることを知ってもらいたい。蔵春閣をどう使うかを含め、いろんなアイデアを皆さんからも出してほしい。
-他市で歴史的建築物を活用した事例は。
藤井さん 佐賀県出身の著名な画家・岡田三郎助の東京渋谷区にあったアトリエは、明治43年ごろの建物で蔵春閣と同じ頃のものだ。洋風なアトリエでは日本で最も古い建物だと推定している。佐賀県の博物館・美術館が明治維新150年事業で移築してほしいとの要請で、佐賀城の中の博物館前に移築した。記者会見や小さな展覧会、貸しホールなどいろいろ適用できるよう運営しているし、新進の若手画家にひと月、貸してもいる。そうすることにより多角的に魅力を発揮する。喜八郎も多角経営の天才。蔵春閣もどんどんアイデアを重ね使っていけば、魅力は3倍4倍にもなる。
-蔵春閣へ期待することは。
坂井さん 大勢の方々がそれぞれに合った方法で利用してもらいたい。見るだけではなく、使えば使うほど素晴らしい建物だと分かるはずだ。
鈴木さん 10~20年かけて育てていくことが大事。市民に根付かせるため、自分のこととして考えてほしい。
松尾さん 旧藩主溝口家の家紋を崩して作った絵柄のふすまが、大倉集古館から見つかった。由緒ある物を復活させてもいい。宝の宝庫、楽しんでほしい。
藤井さん 喜八郎が里帰りするようなもの。喜八郎の建物は、新発田の歴史に形を与える重要な一つ。大切にしてほしい。
東京大名誉教授、文化庁文化審議委員・藤井恵介さん基調講演
蔵春閣 明治宮殿と近い関係性
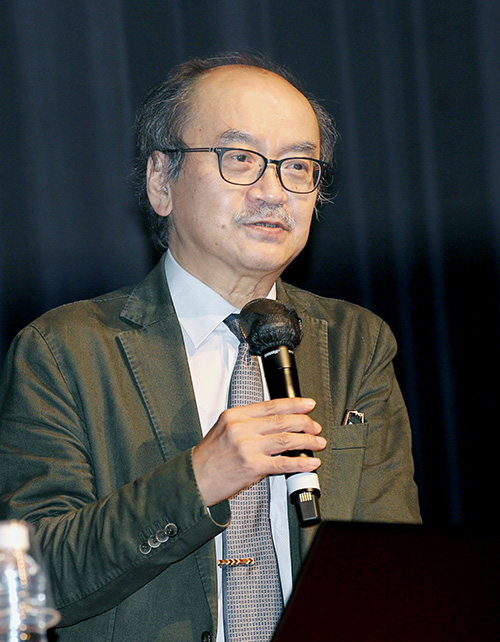
蔵春閣は明治期の日本人や外国人向けの供応や宴会を目的とした施設として、東京・向島に建てられた。1階は西洋風の食堂で椅子式になっていた。2階は廊下から景色を眺めながら、喫茶、喫煙をする遊び場。畳敷きの広い広間では芸妓(げいこ)を踊らせて、客は廊下の椅子に座って楽しむ。ぜいたくな雰囲気のお座敷。喜八郎はそんな場所を作ろうとの考えだった。
2階の和室はシンプルと思っていたが、その対局の華やかさだった。こういう座敷の作り方があるのかと、あらためて目を開かされた。(移築が完了すれば)日本では多分、新発田にしか残っていない建物。
(庭園と建築が融合した京都の)桂離宮は日本の木造建築の代表だが、建築内部は柱が細いし、装飾的な要素もほとんど入っていない。日本のお座敷の典型ともいわれ、質素を旨としている。日本の木造建築における一つの方向だが、質素であることが必ずしも価値が高いということではない。
明治宮殿は1888(明治21)年に完工して、さまざまな戦前の行事がずっと行われてきたが、1945(昭和20)年に空襲で焼失した。私たちの目の前から、宮殿建築の最も高級な建物がなくなってしまった。
日本の宮殿建築は、(外国の賓客を迎える東京の)迎賓館赤坂離宮が象徴であるかのように勘違いされている。実際は、天皇がいた明治宮殿の方が重要な建物。最高級の和風建築で造った明治宮殿は、蔵春閣と関係性が大変近い。私たちが失った華やかな木造建築をしのぶことができる建物の一つが、まさに蔵春閣だ。
こういう建物を美術品として眺めるだけでいいのか。古い建物を楽しんで使うことを考えていかないといけない。建物は上手に使えば減らないし、いくらでも使える。上手なメンテナンス、上手な修理をしながら、使っていけばいい。
これは新発田市、蔵春閣に求められている次なるステップ。建ち上がった後のことを考えていくのがいい。
<ふじい・けいすけ> 1953年、松江市生まれ。東京大学大学院博士課程単位修得退学。工学博士。専門は建築史、文化財保存学。2009年に同大教授、18年から同大名誉教授に就任し、文化庁文化審議委員を務める。建築史学会会長、東京芸術大学客員教授も歴任した。