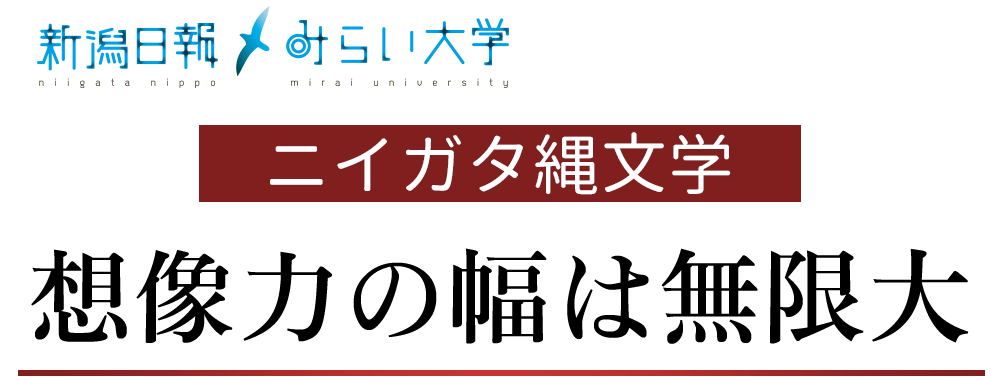第2弾 魚沼
新潟日報 2019/10/30
新潟日報みらい大学の2019年度第3回公開講座「ニイガタ縄文学」が10月9日、十日町市の越後妻有文化ホール「段十ろう」で開かれた。新潟日報社が展開する「未来のチカラ in 魚沼」の一環で、十日町市文化協会連合会設立25周年記念事業として開かれた。ドキュメンタリー映画「縄文にハマる人々」の上映会が開かれ、映画を監督した山岡信貴さんと十日町市博物館館長の佐野誠市さんのトークショーが行われた。山岡さんらは縄文ブームを追った作品「縄文にハマる人々」を題材に、縄文時代の文化が持つ魅力や可能性について熱く語り合った。
<トークショー参加者>
山岡信貴さん(映画監督)
佐野誠市さん(十日町市博物館館長)
コーディネーター 与口幸子・十日町支局長

映画の上映後、トークショーで縄文文化の魅力について語り合った山岡信貴監督(中央)と佐野誠市館長(右)=2019年10月9日、十日町市の越後妻有文化ホール「段十ろう」
山岡さん 諸説の真偽は二の次
佐野さん 正解は一人一人違う
-山岡監督が、今回の映画を撮ろうと思ったきっかけは。
山岡監督 映画に出てきたが、子どもの墓を家の入り口の下につくると聞いたとき、それが日常というのは、どんな生活なのかが気になったのが、きっかけの一つ。縄文には、想像を絶するものがあると感じた。
-映画では十日町市の笹山遺跡から出土した国宝の火焰型土器が大きく紹介されていた。その魅力は。
山岡監督 火焰型土器は一つの規格があるが、あれほど極端に細かい部分まで規格がきっちり統一されている縄文土器はない。それは、縄文人が何を思っていたかや、火焰型土器の世界観を考えるときの、手がかりにもなると思う。
佐野館長 うちの火焰型土器は国宝に指定されて今年20周年。残存率95%で、出なかったのは、ほぼ底の部分だけ。そしてこのプロポーション。去年パリで開かれた日本文化の祭典では、日本を代表して展示され、高く評価された。十日町の宝として、日本、世界に発信できることは市民として誇らしい。
-映画では、いろんな人が縄文を自由に捉えていた。縄文時代の精神文化をお二人はどう考えるか。
山岡監督 正しい説かどうかということは、あまり興味がない。縄文の土器を煮炊きに使っていたという話を聞いたときに驚いたが、僕らは、あれを日用品として使うには、何かが失われている。なぜ使うのか動機の一番大きなものは分からなくなっている。でもそれを自分が分かる範囲で答えを出すのは間違い。もしからしたらすごく遠い球を投げてくれているのに、僕らが分かる話に置き換えてポンと受けてしまうのは良くない。だから、できるだけ「変な球」をどんどん聞きたい。人間にこんな可能性があるんだ、と想像の幅が広がるような。
例えば、火焰型土器というけれど、あれは火焰じゃない、とまず思う。
佐野館長 6年ほど前、津川雅彦さんが博物館に来て、これは信濃川の水面だと。周りのギザギザが水面で、渦があって、サケが飛んでいる。それを聞いて愕然としたし、逆に腑(ふ)に落ちると思った。
山岡監督 それはすごく分かる。上部のギザギザが川面で、飛んでるのは私もサケだと思う。あれでサケを煮たことがすごくすてきだ。自分たちで捕ったサケを、サケが元気に泳ぐ姿を模した土器で煮ていただく。すごくやさしい。さみしくないよ、周りには仲間が泳いでるよと、サケへの思いがあると思う。そんなことを思いながら、元気に泳ぐサケの元気をみんなでいただく。それが正解かどうかは分からないが。
佐野館長 分からないなりに考え、自分の中での正解が一人一人違うのはいいし、楽しいことだと思う。
-縄文に学ぶべき点は。
佐野館長 縄文時代、移動民族から定住を始め竪穴式に住んだ。そこでお年寄りと一緒に暮らしていたというのが私は一番好き。北海道の遺跡では50歳くらいの女性の骨、絶対歩けないような大腿骨が出ている。移動民族のときは、足の悪い人やお年寄りは切り捨てて次の場所へ移らなければいけなかった。縄文は自然と共生し、一緒に仲良く暮らした。八百万(やおよろず)の神を受け入れてきたように、われわれの民族は多様なものを享受して認めてきた。今、自国愛で世界中が混乱しているときに、縄文人の在り方は大事だと思う。
山岡監督 縄文時代とそれ以降と何が一番違うのか。弥生以降は、うちの土地で作った米を勝手に食うなの世界で、「私」と「あなた」が明確に分かれだした。縄文時代はその差がもう少しフワーンとして、境目がないような世界だった。弥生以降どんどん「私」が強化され膨らんできたが、昨今の国同士の様子など見ると、私、私、私って言い過ぎている。縄文時代の「私」というものが、今の在り方と違っていたことに思いをはせるのは、意味があると思う。
映画「縄文にハマる人々」
縄文時代の遺物や生活様式に魅せられた人々に話を聞き、全国の遺跡や博物館を訪れてその謎を追うドキュメンタリー。土器と土偶に共通する文様や、縄文人とアイヌ民族、アボリジニとの類似点を調べ、1万年以上続いた時代の本質に迫ろうとする。見えてくるのは生と死を分けない思想。縄文生活の実践者の話は興味深い。
詳しい内容や上映予定は公式サイト、http://www.jomon-hamaru.com/
映画に登場 県内の施設
火焰型土器、火おこし体験…
映画「縄文にハマる人々」のパンフレットに掲載されている「映画に登場する遺跡・博物館」のうち、新潟県内施設の概要=各施設とも月曜(祝日の場合は翌日)休館=

県立歴史博物館(長岡市関原町1)
常設展示「縄文人の世界」「縄文文化を探る」で多数の土器や資料を公開。
<常設展示観覧料> 一般520円、高校・大学生200円、中学生以下無料
<問い合わせ> 0258-47-6130
馬高縄文館(長岡市関原町1)
国重要文化財の火焰土器が発見された馬高遺跡の出土品を収蔵・展示する。
<入館料> 200円、高校生以下無料
<問い合わせ> 0258-46-0601
十日町市博物館(十日町市西本町1)
国宝火焰型土器=写真・磯谷史朗撮影=を常設展示。
<入館料> 一般500円、中学生以下無料
<問い合わせ> 025-757-5531
津南町農と縄文の体験実習館なじょもん(津南町下船渡乙)
津南町で出土した火焰型土器などを展示し、火おこし、土器作り、勾玉づくり、アンギン編みなど縄文体験ができる実習館。敷地内には竪穴住居が6軒復元された縄文ムラがある。
<入館料> 無料
<問い合わせ> 025-765-5511
津南町歴史民俗資料館(津南町中深見乙)
秋山郷を中心に、地域全体から集められた生活用具、土器などを展示。
<入館料> 一般成人210円、未成年・学生100円
<問い合わせ> 025-765-2882
会場の声
土器作ってみたい/多様性ある世界

南魚沼市六日町の会社員(27) 「土偶にかわいらしさを感じ、縄文に興味を持っていた。縄文人の生と死や自然との向き合い方が現代とは違うのが印象的だった」
群馬県みなかみ町の会社員(33) 「もっと土偶や土器などを生で見てみたいと思った。監督のトークも面白かったので、もっと聞きたかった」
新潟市西蒲区の会社員(34) 『火焰土器は火がモチーフではない』という話が良かった。自分でも土で何か作ってみたいという気持ちになった」
十日町市中条甲の団体職員(33) 「土器や土偶に関する研究者の考えはたくさんあり、その量に圧倒された。映画を見ているうちに、私も縄文にハマっていった」
三条市吉野屋のイラストレーター(51) 「現代とは異なる多様性のある世界を見せてもらった。土器や土偶は自由な発想で作られていたと感じた」
命問う契機に
燃え上がる炎に見立てる人がいれば、春に萌(も)える草木の生命力や、波打つ川の水面を思う人もいる。本県から出土する「火焰型土器」を前にしただけでも、私たちの想像力は刺激される。
縄文の土器や土偶は不思議だ。何のための装飾なのか、誰が作ったのか、人や動植物の姿をそのままに描かないのはなぜか。そして人々は何を願って暮らしていたのか。
文字もない、はるかな時代を映し出すささやかな手がかりは、あまりに難解だが、「正解は分かりっこないんだから、ここはいっそ、想像力全開で楽しく向き合っちゃおうよ」。山岡信貴監督と佐野誠市館長は、そんなワクワク感で会場を満たしてくれた。
縄文の何がこんなに人を引きつけるのか、結局分かったとは言えないが、命や豊かさについて、ゆっくり考える機会をくれたことは確かだ。
(十日町支局長・与口幸子)