第2弾 魚沼
希望満ちる明日に
「10年後さらに輝く地域へ」
-提言フォーラム詳報-
新潟日報 2019/11/17
新潟日報社が魚沼地域で展開した「未来のチカラ in 魚沼」の中核となる提言フォーラム「10年後 さらに輝く地域へ」が10月22日、南魚沼市の市民会館で開かれた。地元住民が、雪国文化を生かした広域観光の振興や、移住・定住の促進へ自治体が連携して取り組むよう提言した。また、住民と3市2町の首長を交えたパネルディスカッションでは、交通インフラの整備や雇用の創出、福祉・教育の充実など幅広いテーマを巡って、真剣な議論が繰り広げられた。

魚沼地域5市町の広域連携や観光振興、移住定住促進などをテーマに、首長と住民代表が意見を交わしたパネルディスカッション=10月22日、南魚沼市民会館
住民3人が提言

雪国観光圏代表理事
井口 智裕さん
ブランド化 広域連携が鍵
今回は「10年後の地域に必要なコト・モノ・人」をテーマに、5市町のメンバー9人が8月から3回集まって議論した。10年後の理想の地域像を「雪国ブランド」の視点から考えてみた。
雪国観光圏は魚沼地域の5市町と群馬県みなかみ町、長野県栄村で活動している。湯沢町のスキー、十日町市と津南町の大地の芸術祭など、全国的に有名な観光資源はあるが、それぞれがPRするだけでは、マーケットの面で厳しい。
地域に共通する概念が雪国文化であり、世界的に素晴らしい価値がある。地域をひとくくりにした中で見えてくる可能性が、広域連携という考え方だ。そのために重要なのは、誰がどういう意思決定をするのかという組織。もう一つは、財源をどうするかだ。
行政や観光協会がいろいろな取り組みをしているが、単発的なイベントやキャンペーンだけでは、地域は持続的に発展していかない。そこで観光庁は「観光による地域づくり組織」の設立を提唱している。当然コストがかかり、人を雇うにも財源の問題がある。
5市町の厳しい財政状況が続く中、「観光の財源は観光客から取る」ことを提言する。今いわれているのが、宿泊税や観光税の導入だ。世界では当たり前で、ナパ・バレー(米加州)やワイキキ(米ハワイ州)でも取っている。観光による収入で、地域に必要なインフラに投資するなど、住民の生活が豊かになることがなければ、本当の意味での観光立国とはいえない。

松之山・酒の宿「玉城屋」社長
山岸 裕一さん(十日町)
豊富な資源に付加価値を
10年後、どんな未来を想像するか。魚沼地域には豊富な雪資源、10の酒蔵、おいしいコメがある。雪、酒、食を生かした、より付加価値の高い観光分野へのシフトを提言したい。
経営する旅館玉城屋では、フレンチと日本酒のペアリングで単価を2~3倍に上げ、高価格の付加価値路線で運営している。宿泊客のほか、スタッフとして働きたいと、県外から移住する人も増えている。
現状の課題は、ご当地ナンバー問題のように、雪国にマイナスイメージを持った住民が結構多いことだ。雪国での生活は大変だが、魅力もある。未来のためにどうすればいいか?
一つめは、住民が雪国の生活やストーリーの価値を認識し、発信することだ。例えば、春の山菜は雪解け水のおかげでおいしい。雪国だから、こういうおいしい食が生まれる。みんながポジティブに発信することで、未来があると思う。
二つめは、2次交通の整備が必要不可欠で重要になる。JR越後湯沢駅に到着後、観光地を回る周遊バスがない。タクシーではなかなか回れない人もいる。条例などの改正が必要になるが、車を共有できるライドシェアで観光地を巡ることができれば、地域の付加価値が上がるのではないか。
2次交通の整備には金が掛かるので、5市町で観光税を導入し、持続的な財源を確保する。その財源で広域的なDMO(観光地域づくりのための法人)を運営し、観光を盛り上げていければいいなと思う。

移住定住促進会社「きら星」社長
伊藤 綾さん(湯沢)
「誇り持って生きる」肝要
移住促進は、どの市町村も力を入れて取り組んでいるが、住民が地域の暮らしに誇りを持っているか、楽しんでいるかが重要だ。
私は柏崎市出身。3月、湯沢町に引っ越してきた際に「なんで湯沢町なんだ。何もない」「なぜ来たか」と言われた。住民が自分の地域の価値を下げる発言をするのを聞いてきた。
観光分野と同様、住民が雪国の暮らしを楽しみ、発信することが、移住定住においても大切だ。10年後の未来ビジョンとして「このまちで誇りを持って生きる」ということが肝要で、定住者に選ばれる地域になるため、提言したい。
5市町が地域の特色を大事にしながら稼ぐ力をつける。付加価値の高い産業を興し、住民が潤うことが大事だ。住民が「自分の商売で稼ぐんだ」と前向きに変わっていく必要がある。
移住者にとっての課題は住まいだ。東京の高所得者が来たとき、適した住宅が見つからない。空き家はあるがぼろぼろ、などの問題がある。満足できる住まいがあることが、移住先に選ばれるために必要となる。
福祉と教育の充実だ。魚沼基幹病院(南魚沼市)は医師や看護師不足。常勤医がいなくて苦労している地域もある。また高校以上の教育が受けられないことも、人口流出の原因となる。
5市町の首長に「オール魚沼で魅力的な地域づくり」を提言する。1自治体で闘い、人を集める時代は終わった。市町の垣根を越えて地域の魅力を発信できる仕組みがあってほしい。
パネルディスカッション
<パネリスト>
林 茂男氏(南魚沼市長)
関口 芳史氏(十日町市長)
佐藤 雅一氏(魚沼市長)
桑原 悠氏(津南町長)
田村 正幸氏(湯沢町長)
井比 晃さん(旅行会社「HOME HOMENiigata」社長)
岡崎 理香さん(南魚沼市女子力観光プロモーションチームメンバー)
山本 あいさん(地域PR団体「このめ」代表)
<コーディネーター>
八木浩幸・新潟日報長岡支社長
(文中は敬称略)



提言を受けて
林市長 雪の悪印象突破したい
佐藤市長 広域行政は幅広い枠で
八木 「雪国文化」という共通の価値観をもつ5市町が観光振興で連携し、移住定住につなげて魅力ある地域にしていく具体的な提言が示された。
林 地域共通の課題に言及された。昨年、ご当地ナンバー導入の議論の際、住民の間に雪国が「ダサい」というマイナスイメージが根強いことが浮き彫りになった。そこをなんとか突破したい。東京五輪の暑さ対策として雪冷房の普及を進めているのもその一つ。
関口 行財政の広域連携の提言があったが、「平成の大合併」を検証しないと。移住定住の視点や、公共交通が観光推進に必要だという提言には大いに賛同する。住民に対する交通インフラと、観光の交通インフラを掛け合わせる形で整備できないか。
佐藤 連携を目指す上で、自治体それぞれにある地域性や特殊性を考える必要がある。商圏や農業のかかわりもあり、広域行政の枠組みは幅広く考えてもいい。観光客を増やすことは地域が潤うことになるが、どれだけ雇用が生まれるか、産業や定住の場としてどう整備するか分析が必要だ。
桑原 まずは教育だ。5年前からジオパークを通して、地域の良さを、価値に変えていくことができる人材を育てている。子どもたちには魚沼全体が学びの場になる。持続可能性を目指すにはある程度の財源の集中投入が必要。1自治体がすべての施設を持たなくても、互いの財産を生かし合うことが大事。
田村 湯沢町は多くの事業所が観光に関連している。提言の指摘のように、好循環を生むには、訪れる人が求めるものを磨き上げ、新たな魅力を作ることが大切だ。2次交通の話では、今ある鉄道や路線バスのアクセスをいかに良くするか、訪れる人にどう知らせていくかが大事だ。
井比 十日町で人を呼びむ込む旅行会社を経営している。観光資源を生かすには交通インフラが必要。雪が降り、道も悪く、こんな不利な状況はない。大手自動車メーカーと組み、人工知能(AI)技術を活用して自動運転の特区になってほしい。
岡崎 私は神奈川県出身で、夫の出身地の南魚沼市に移住した。移住した後、定住につなげるには、ケアが重要。就職先の情報など、近隣自治体についても知ることができれば選択肢が増える。広域連携で、いろいろな場所でケアが受けられるようになればいい。
山本 首都圏の大学を休学し、南魚沼市に戻って活動している。地元には何となく帰りづらかった。高校を卒業するまでに、地域のことを勉強し、地域の人と話す機会が少なかったからだ。雪国文化を意識しながら、地元を知る機会を増やせればいいと思う。



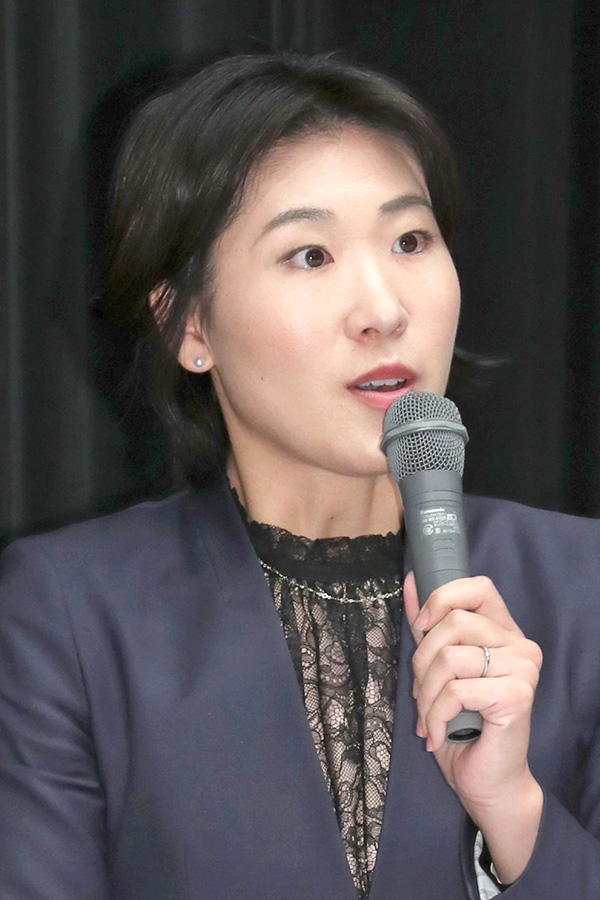

広域連携と観光税
桑原町長 意思決定の仕組み必要
田村町長 雪国観光圏 うまく機能
井比さん 観光資源維持に財源を
八木 観光での財政的な広域連携や観光税(宿泊税)導入をどう考えるか。
佐藤 自治体として財政的な交流をする仕組みがまだできていない。同じ地域で生活する者として、今後それぞれの良さを出し合って連携に取り組まなければ。全国魅力度ランキングで魚沼市は88位に入った。単に「魚沼」の名前のブランド力なのか分析が必要だ。
桑原 広域連携を進めるには組織体制が課題という話があったが、どのように意思決定のシステムができるか。ある程度広いエリアで人口も多い。どれだけスピーディーに適切に取り組めるか。意思決定のシステムのイノベーションが必要ではないか。
田村 地域経済を発展させるには観光の力は大きい。各市町が同じことでなく、それぞれの特性を磨き上げることが大事。財源では、宿泊税をすぐに導入するのは難しい。雪国観光圏は各自治体が応分の負担をし、うまく活用していて、協力態勢もできている。
関口 宿泊者数は湯沢町が圧倒的に多い。宿泊税は金沢や京都も始めたし、東京都もやっているが、観光は宿泊だけでなく食事、お土産などいろいろなところでお金は落ちる。宿泊税で入る分を地域全体で使う提案だと思うが、湯沢町民にご理解いただけるか。そんなに簡単ではないだろう。
林 昨年、20年ぶりにオーストリアへ視察に行って町の変貌ぶりに驚いた。公共の施設は観光税で造られている。目指すものとして広域連携は分かるが、市町によって住民の要望は異なり、簡単ではない。まずは緩やかに進めながら、最終的な目標に向かうことが大事かと思う。
井比 十日町市の「星峠の棚田」には年間50万人が訪れるが、地元集落に落ちるお金はごくわずか。観光税はインフラだけでなく、お金の落ちにくい場所や、観光資源の維持などに使われるべきだ。プロとしてサポートできる組織が必要。縦割り行政ではない形で魚沼地域での観光を推進できる。
移住定住促進
関口市長 協力隊 10年大きな意義
岡崎さん 自然の価値 学ぶ機会を
山本さん 帰って来る理由は「人」
八木 提言には移住定住の視点が盛り込まれていましたが。
関口 魅力があるよと、外の方から言ってもらって地域に元気が出たという実例もある。一騎当千の人たちに選んで、住んでもらう方策をやっていくことは大事。そういう意味で十日町市では「地域おこし協力隊」の制度を導入して10年になるが、私どもにとっても非常に意義があった。
林 地域連携という視点でみると、南魚沼市は、魚沼市と湯沢町と連携して地域活性化に取り組む「定住自立圏構想」に取り組んでおり、運動施設や図書館の相互利用を進めている。行政は幅広い。例えば保育だとか、一つ一つやっていくことが大切。
佐藤 これからは人口を増やすのは難しい。減らさない仕組みが必要。働く場の選択肢を広げることが、若者の定住につながる。子育て、教育など、子どもへの投資をして地域のよさを発信したい。第2のふるさととなれるよう、関係人口も増やしたい。
桑原 私たちの地域は、雪、食材、酒など売り物はたくさんある。本質的にみれば、食料もエネルギーも自給できる。人が生きていくには適した地域ではないか。この私たちの上質な生き方、思想自体が価値になる。それを売り込んでいけたらと思う。
田村 観光が主要産業の湯沢町にとって、交流人口の拡大が命題だと思う。移住定住をはじめさまざまな取り組みを進めている。人口減少で労働力、地方を支える力も少なくなっている。福祉や教育の充実などを図り、労働環境や雇用環境を整えることが非常に大事だ。
岡崎 住民がここに住む価値を見いだし、意識して、それを発信してくことが大事。息子たちは「(南魚沼市は)空気がおいしい」と良さを語る。この自然を、雪国の価値を理解して守っていくための教育が大切。大人になっても学ぶ機会があれば。
山本 祖父と2人暮らしの時期があり、地元の人に育てられた。地元を離れてみて、「帰ってきたい理由」は「人」だったと気づいた。効果が出るのは先になるが、中高生には人や自然の豊かさ、雪国文化に代表される地域の良さを知る機会を増やせればいい。
益田 浩・新潟県副知事
地域の視点 発信の参考に
新潟日報社の「未来のチカラ」に期待している。地域の課題に、地域の視点で取り組み、いろいろな提言がいただける。魅力も発信してもらえる。新潟県は花角英世知事の肝いりで4月から「新潟ブランドをどうやって発信していくのか」という取り組みを始めた。「未来のチカラ」を参考にさせてもらっている。
魚沼地域では、10年後の輝く未来、雪国の観光の可能性、移住・定住の促進というテーマで提言をいただく。パネリストは地域で頑張っている人たちなので、楽しみだ。
県は大型観光企画「デスティネーションキャンペーン」や国民文化祭、全国障害者文化祭でも魚沼・雪国をテーマにしていろいろな取り組みを行っていく。
客席の声
「福祉や教育大切」共感/柔軟な発想に感心
<南魚沼市、大学生の女性(21)>
移住・定住拡大の提言にあった「質の高い住まいを」という視点が新鮮だった。首長の話を聞けたのはいい機会だった。魚沼市長の「観光だけで移住・定住にはつながらないから、長く住み続けてもらうためには福祉や教育も大切」という意見にも共感した。
<十日町市、市議会議員の男性(54)>
民間の人たちは柔軟な発想を持っているなあと感心した。観光振興や観光税の問題などは、この場だけの議論に終わらせず、市全体や議会の場でも引き続き議論を続けていきたい。
<魚沼市、無職の男性(78)>
まず五つの市と町が交流することによって、その他の自治体との交流も生まれるのではないか。5市町は同じ雪国だが、文化が異なる。一体感をつくるために、子どもの頃から行き来してはどうか。
<魚沼市、会社社長の女性(73)>
新潟県には空路も海路もあり、交通の便がいい。外国と仲良くして、観光客にスキーや温泉を楽しんでもらえば、ビジネスチャンスになる。フォーラムを聞き、もうひと頑張りしようと思った。
<魚沼市、市民団体「只見線なんとか会」のメンバー男性(35)>
広域連携で、わが会はJR只見線振興のため、福島県只見町と連携してさまざまな取り組みを行ってきた。将来は只見線の列車が浦佐駅に乗り入れし、首都圏から魚沼地域経由で福島県まで結ぶ広域観光圏をつくってはどうか。
新潟日報社 小田 敏三社長
子どもたち勇気づけよう
「未来のチカラ」は、新潟日報が地域に出向いて生の声を聞き、地域をどうしたら元気にしていけるのか一緒に考えて、発信していくプロジェクト。新潟県は広いので、それぞれの地域で抱えている課題が異なる。足かけ4年で県内全域を回る。
9月22日に南魚沼市のJR浦佐駅で新米のおにぎりや地酒、郷土料理を販売する「米と酒 魚沼の陣」という催しを開いたら、予想を大きく上回る8千人が来場した。魚沼地域は想像以上のブランド力を持っていると実感した。それを力に変えていきたい。「10年後の魚沼を元気にしてみせる」と、未来を生きる子どもたちを勇気づけるようなメッセージを送っていただけるよう期待している。