第6弾 柏崎・出雲崎・刈羽
[未来のチカラ in 柏崎・出雲崎・刈羽]
10年後 さらに輝く地域へ
-提言フォーラム詳報-
新潟日報 2021/08/24
提言フォーラム詳報
2. 提言の補足
支え合って連携深め
フォーラムでは、発表された提言を踏まえ、各メンバーが注目するポイントや今後必要なことについて、それぞれが意見を述べた。
─今後の交流の在り方について考えていることは。

春日俊雄さん(新潟産業大学特任講師)
集落維持 移住者と共に
荻ノ島集落のかやぶきの宿ではかつて、「より多くの交流人口を」ということがスローガンだった。2013年に20周年を迎え「大人数との交流」から「集落への共感をベースにした互いに支え合う交流」へと転換した。交流の効果を集落の維持につなげることがキーワードになった。
荻ノ島集落には、若い人が移り住み、地元の人も移住者と向き合っている。交流の質については、継続度、親密度、心からの愉(たの)しみ度、支え合い度、知的活性度、モチベーション度が目指すべきところになる。

布施和則さん(不二美術印刷社長)
創業目指す人を後押し
観光面では後継者問題が特に大きく、宿泊業や飲食業の余裕がなくなっている。従業員らの縮小に伴い、社長自らが全てをやらざるを得なくなり、イベントの参加などで営業活動を思うようにできなくなった結果、仕事が来ないという負のスパイラルになっている。
一方で、ピンチをチャンスに変える人も多く、昨年からことしにかけ、柏崎では女性経営者が何人も創業した。こうした「トップランナー」に走ってもらい、その人たちを応援できる取り組みができればいい。

塚田真理子さん(星くじらのしっぽ代表)
孤独な子育て防止策を
山梨県から柏崎市に移り住んで困ったことは、人とつながりにくく、地域のイベントやお店の情報を得にくいということ。ささいなことも話せる場や、人と出会ってつながる場など、外の居場所をつくることは、母親や移住者のみならず、今後一人暮らしの高齢者が増える社会にとっても必要だ。
山梨県では、カウンセラーを囲む育児座談会があった。同じ経験をした母親からの共感や実践アイデアもあり、自分だけではないという安心感が得られた。孤独な子育てを防止するために、他の自治体の良い事例を取り入れてほしい。

和田典士さん(木工作家)
SNSでつながり生む
「交流人口の質」という切り口では、横のつながりが大事だと考えている。インターネットの普及で情報が得やすくなり、個人事業主も発信しやすくなった。特にSNSが発達し、利用する側も店の情報を得ることができ、店側も発信できる。
私自身は、家具や小物のオーダー製作を中心にしているため、お客さんの幅は比較的狭いが、興味がある人に情報を届ける手段としてSNSを使っている。個人と個人が結ばれると、全体の交流の質が上がっていくと思う。
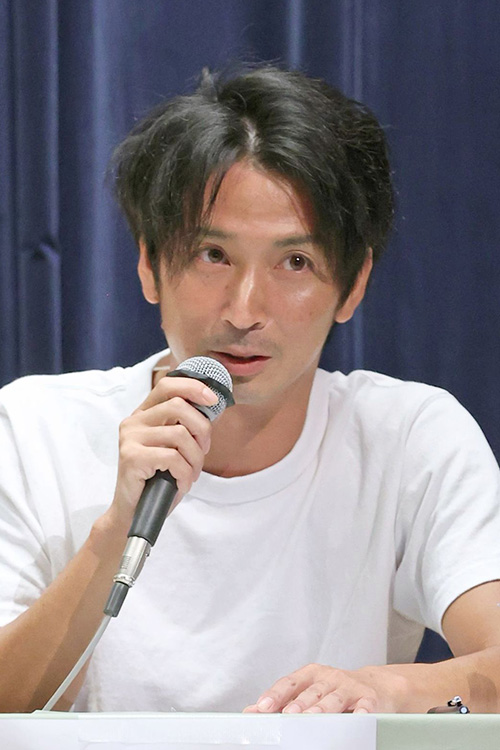
飯田裕樹さん(ピーチビレッジ刈羽農業事業部)
将来の選択へ就農体験
刈羽村の特産品である砂丘桃は、生産量や販売量が少なく、「幻の桃」と呼ばれている。売り上げの倍の経費がかかっていたため、価格帯の見直しや、販売、予約方法を改善したが、生産者は年々減少し、5年後には現在の半分程度になるかもしれない。
今後は「100年後も刈羽村の特産品であるために」をキャッチフレーズに活動したい。小学生などに就農体験の場を増やして、将来の職業の選択肢の一つにすることが必要。砂丘桃を存続させて、もうかる土台を築き上げていきたい。
10年後の地域理想の姿へ 魅力を理解感動を発信
-10年後の理想像に近づくために、市町村連携や地域活性化で必要なことは。
春日さん 地域を持続させるために、地域内の交流やつながりが必要になってくる。地域のつながりは、暮らしのさまざまな問題を住民同士が共有するという関係性を新たに生み出す。
主体的に課題を乗り越えていくことで、地域内外に開かれた温かな地域社会ができる。まずは住んでいる人が身近な自然、歴史、食を楽しんで、知識ではなく、感動を発信していけば、外から魅力的な地域として認識されるだろう。
布施さん 子育て支援について3市町村で互いのいいところを取り入れ合えたら、子育て問題の解決につながるのではないか。自治体間の境界を一度なくして連携できたらいい。
Uターンで柏崎市に戻ってきた。戻るとき、柏崎市の情報を知る方法がなくて困った。地元を離れた人が地元の良さを感じ取って戻りたいと思ったときに、地元の情報を知っていれば安心して戻れる。ウェブページや冊子を作ったことで、自己満足してしまうことが一番駄目。常に情報が伝わるようにプッシュ型の情報提供をしてみてはどうか。
塚田さん 市内の子育て世代の間では、冬でも子どもを遊ばせられる施設が市内にほしいという話題になる。3市町村が連携して、子育て拠点となる施設ができれば、周辺自治体からも遊びに来る親子が増え、地域の新たな魅力になる。
親戚がいない移住者でも、子どもを預けられる環境や、子連れで過ごせる場所、人と人を積極的につなげる仕組みがあれば、子育て移住者に選ばれる地になるだろう。移住者の孤立防止の取り組みとして、郷土料理や歴史をたどるまち歩きなどで土地と移住者をつなげる企画があると助かる。
和田さん サラリーマンから個人事業主になった。起業するときに何から始めたらいいか分からなかった。いいアイデアを思いついても、始め方が分からず、踏み出せない人はすごく多いと思う。思いついたアイデアを形にできる環境を整えてほしい。
アイデアを実現できる環境があれば、SNSなどで発信し、面白い活動はだんだん広がっていくだろう。テレワークも進み、都会にいなくても仕事ができる。地域に面白いコミュニティーがあれば、人が集まるようになるだろう。
飯田さん 刈羽村ではスポーツ合宿を誘致して観光につなげる動きがある。村内のサッカー場の利用者から食事を楽しめる場所などをよく聞かれるが、すぐに答えられないときもある。
合宿に来て終わりでは、もったいない。住んでいる人が地域の魅力を把握し切れていないと感じる。発信する前に、自分たちの地域の魅力を理解することが大事だ。いろいろな角度からこの地域に人を集め、交流の場が生まれることで地域は活性化していくだろう。
花角英世知事ビデオメッセージ
自然や歴史 広く伝えて
新潟日報社の「未来のチカラ」で今回の舞台となる地域には、豊かな自然や充実したスポーツ施設、北国街道の宿場町として栄えた歴史など魅力的な資源が豊富にある。その魅力を核にした交流の広がりもある。
提言フォーラムをきっかけに地域住民に地域の魅力に気付いてもらい、人と人、人と地域のつながりをつくり出す取り組みに関心を寄せてほしい。
魅力を磨き上げ、広く発信することで子どもたちが地域に誇りを持ち、若者が住み続ける活力あふれる地域になることを期待する。
県も誇りを持って外に魅力や価値を発信するため、「新潟※(コメジルシ)プロジェクト」を始めた。未来のチカラとの連携を進めていきたい。
主催者あいさつ 小田敏三・新潟日報社社長
若者たちが輝ける場へ
「未来のチカラ」は、新聞社はニュースを伝えるだけではなく、人と人、地域と地域、地域と人をつなげる役割も重要だという認識のもと、社を挙げて地域に出向き、課題を膝詰めで聞かせてほしいという趣旨で始めた。
2019年に上越地域でスタートし、柏崎・出雲崎・刈羽は6カ所目だ。
今回、提言作成チームは10年後を見据えてこの地域を輝かせたいと、特に未来を担う若い人たちが地域にプライドを持てるようにするにはどうしたらいいのかを真剣に話し合ってきた。
地域の課題をきっちり届け、提言は紙面やいろいろな構想で実現していく。魅力ある地域づくりのためにわれわれの力も発揮させていただきたい。