第5弾 県央

新潟日報 2021/04/28
<三条> 雲蝶の若さと熟練 一望したい
「越後のミケランジェロ」といわれ、江戸後期から明治にかけて県内各地に作品を残した彫刻師石川雲蝶(1814~83年)。三条は、初めて雲蝶がやって来た越後の地であり、所帯を持ち最期を迎えた場所でもある。ボランティアガイド団体「三条雲蝶会」副会長の江畑徹さん(65)は「あまり知られていないが、三条は雲蝶が越後に来て最初の作品と最後の作品が残る要の地」と話す。それらを一望できるという同市の本成寺とその山内寺院を、江畑さんと巡った。(三条総局長・渡部麻里子)
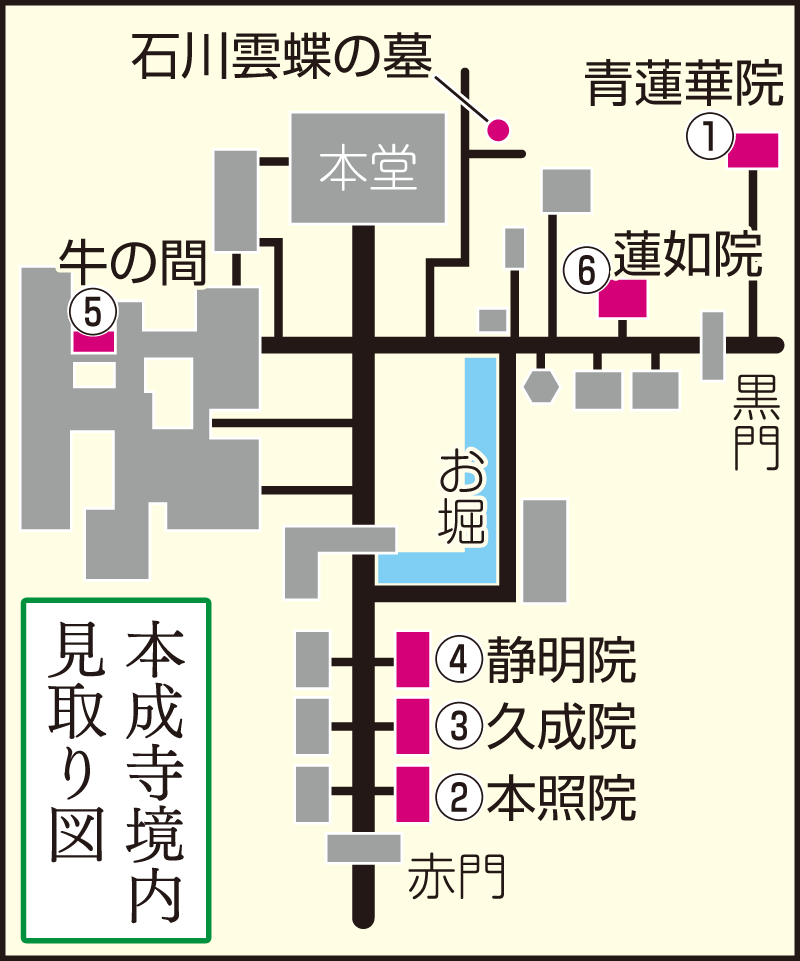
巨匠の造形 間近に体感
本成寺は鎌倉時代に創建された法華宗総本山。雲蝶は、同寺の世話役でもある三条の金物商内山又蔵の招きで、寺の彫刻を手掛けるため20代後半に江戸からやって来たという。
最初期の作品とされるのが、

「江戸高田住」と刻銘がある青蓮華院の手挟み
本照院の門の竜や獅子の彫刻は、1974年に改修した際に出てきた棟札に刻銘と制作年の記述があり、33歳の作と分かった。竜には羽があり、4体配置されている。江畑さんは「竜は門の桁の断面を隠すための装飾だが、羽を生やすことでうまく覆っており独創的。寺院を竜たちが飛び回って守っているイメージが湧く」と感心する。隣の

飛竜=本照院
魚沼地域の華やかな天井彫刻などで知られる雲蝶だが、本成寺には動物の置物が多く残る。鋭い観察眼や緻密な技、味わい深い造形など、"アーティスト雲蝶"を間近に体感できる。

仙人が読む本に署名が見つかった静明院の向拝彫刻
静明院にある小ぶりの亀は、制作年代は不明だが、岩に爪を立て首をもたげる姿が力強い。よく見ると、後ろ足の爪は4本、前は5本。本物も同様で、「非常によく観察している。うろこ状の皮膚もリアル」と江畑さん。さらなる注目点は木目を生かした甲羅という。「彫刻作家が『どうしたらこんな風に彫れるのか』とうなっていた」と話す。

亀=静明院
本成寺本山にある赤牛は、最晩年の63歳の作品。1893年の火災で雲蝶による大牛の彫像と本堂の欄間彫刻が焼失してしまったことから、雲蝶の長男が手元にあった赤牛の置物を寄贈した。あばら骨や尾骨が浮き出た様など写実的だが、頭部やひづめはよく見ると大きすぎる。「デフォルメして本物らしく見せている。牛の本質を彫りだした、成熟の創作」と江畑さんは絶賛する。

赤牛=本成寺本山
蓮如院の猿の置物も見逃せない。木の股に腰掛け、上を見上げる姿は詩情あふれる。制作年は不明だが、江畑さんは「若い頃の作かも」と話す。記されたサインの字体に、若い頃の癖が見られるという。「目線一つでさまざまな想像を喚起させ、円熟味がある。若くして多彩な才を持っていたことに驚く」と目を輝かせた。

猿=蓮如院
本成寺境内に墓も
「本成寺の雲蝶の墓にも足を運んでみて」と江畑さんは勧める=写真=。元の墓は隣の小さな石柱で、1979年に雲蝶の孫が新しい墓を建てた。本成寺には雲蝶を招いた内山又蔵の墓も。こちらは見上げるほど大きく、権勢を物語る。
