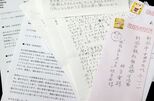【2021/05/22】
生活面重点企画「依存症を考える」の第3部「電子の迷宮(ラビリンス)」では、スマートフォンやインターネット、ゲームに依存し、課金トラブルのほか、睡眠不足で不登校となる子どもや苦悩する親らの声を伝えた。連載後、同じような悩みを抱える家族から、手紙やメールで感想が寄せられた。記事で触れられなかった事前アンケートの一部とともに紹介する。
「私もずっと悩んでいる」と手紙につづったのは県内在住の匿名の母。次男が中学生になる時期に夫が亡くなり、「おとなしい性格が暴君のように一変した」。不登校気味となり、毎夜暴言を吐きながら、朝方までゲームをするようになった。
何とか入った高校も行きたがらず、連日必死で起こし、車で高校に送った。息子が後部座席から髪を引っ張ったり、たたいたりしてきても「心の中で泣きながら、とにかく卒業だけはさせたかった」。担任の先生とカウンセラーの助けもあり、何とか卒業できた。
今も大学に送迎しているが、対人関係が苦手なのは変わらない。ゲーム漬けの日々は続くが、暴力は振るわなくなった。
子育ての反省点に「幼少時に無理難題を押しつけ、多くの習い事、厳しい運動チームに入れた」ことを挙げ、「大学卒業後、社会に出ても見守る」との決意を記した。
長岡市の会社員女性(47)は、スマホを長時間使用する高校2年の子どもが気掛かりだという。
昨年、新型コロナウイルスの影響で、高校入学後1週間もたたないうちに休校に。毎日友達とスマホでゲームをすることに大半の時間を費やすようになり、学校再開後も一定時間ゲームをしないと収まらなくなった。
現在もゲームをする「日課」は続き、「部活をして疲れていてもゲームだけは欠かさない。その執着心に怖さを覚える」。成績によってスマホの時間制限を設けるなど、本人と話し合う最中に新聞連載が始まった。「まさに家での悩みとリンクする記事だった。スクラップし、夫と子どもと話していきたい」と記した。
新潟市の40代主婦は、中学生の息子がゲームや会員制交流サイト(SNS)、音楽試聴と、スマホを際限なく使う。「親が介入しないとやめることができない。社会で『心身が一定程度成熟した高校生から』といったルールを作ってもいいのでは」と提案した。
子どもの健全育成に取り組む「子どもとメディアを考える会」のメンバーで、柏崎市の酒類小売業の浅利親男さん(58)は、連載を読み、「問題は感じているのに、一緒にやってみようという人が少ない」と指摘。地域で大人と子どもが共に考える場の大切さを強調し、「気付きから対策を早く打つことができる。共に取り組んでいきましょう」と呼び掛けた。