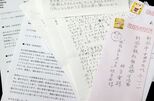【2021/10/15】
1月から掲載してきた生活面重点企画「依存症を考える」では、さまざまな依存症の当事者や家族、支援者らに向き合った。表層の症状だけでなく、誰でも抱えうるストレスや生きづらさ、社会の偏見にも迫った。本社に届いた読者の声を紹介し、企画を振り返る。
根本の生きづらさを探った第6部「心の奥底」では、拒食や過食などを繰り返す摂食障害を取り上げた。
「私も摂食障害」という中越地方の30代女性は、食べ物を口に入れては吐き出すことを続けてきたと打ち明けた。記事を読み「みんな頑張って闘っているんだ。私も食べることが楽しいと思えるように頑張る」と決意をつづった。
新潟市の10代女子学生も、高校時代のダイエットから拒食症になり、体重が減って階段すら上れなくなった経験を明かした。入院を経て体重は戻り、「食べることは生きるために必要だと改めて感じた」。
■ ■
第6部では親が依存症だった人の苦しさ、第3部「電子の迷宮」ではゲーム・ネット依存に目を向けるなど、子どもや若者の視点からも依存症を見つめた。
スマートフォンを見るのがやめられない新潟市の30代女性は「承認欲求をSNSに求めている気がする」と吐露。子どもの頃は「父がパチンコばかりで帰って来ず、祖父母と母は不仲で、毎日の言い合いに耳をふさいで耐える日々だった」とし、「一緒に笑って食卓を囲める家族」がほしかったと振り返った。
第2部「幸運は続かない」では、ギャンブル業界の依存症対策の実効性を問い掛けた。同様に、行政などのアルコール依存症対策を批判するのは長岡市の50代男性。「乾杯条例が施行され、『酒の陣』が大々的に催されてきた。アクセルとブレーキを同時に踏んでいるようなものだ」と訴えた。
依存症は本人が病気だと認めづらく、「否認の病」とも呼ばれる。生活困窮者を支援する中越地方の40代男性は、ギャンブル依存症の疑いがある人に受診を提案したが、受け入れてもらえなかった。「本人に病気の認識がない。まずは病気かもと思ってもらえるよう話していきたい」
病気と認めても、県内は治療の場が十分とは言えない。第5部「日だまりの守り人」では、あらゆる依存症に対応する上越市の「さいがた医療センター」に密着した。
第5部に感想を送ってきたのは、子どもがギャンブル依存症に苦しんだ末に「旅立った」という県内の女性。その意味は明確には書かれていなかったが、「旅立った子に、治療ができる病院が新潟にできたよと教えてあげようと思う」とし、「もっともっと情報発信され、苦しむ本人、家族が少しでも減りますように」と願った。
■ ■
第4部「闇からの脱却」で触れたように、特に薬物は厳しい教育啓発や規制もあり、偏見が根強い。
これに対し、新潟大出身で北海道大大学院の渡部虎太朗さん(23)は「患者を廃人かのようにあげつらう風潮は否めない」と指摘する。「依存症は『孤独』を生んだ社会の問題でもある。自己責任の一言で片付けることが、健全な解決だとは思えない」と投げ掛けた。
第1部「乾かぬグラス」に始まり、回復の歩みを続ける当事者や家族を多く紹介した今回の企画。記事に呼応し、エールの手紙を寄せた人もいる。
新潟市東区の浅野薫さん(70)は若い頃にアルコール依存症になり、酒をやめ続けて35年。「どうか酒で苦しんでいる人よ、家族よ、断酒会につながってほしい」と呼び掛け、「穏やかな日常を取り戻してほしい。二度とない人生なのだから」と結んだ。