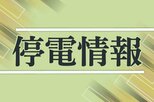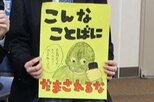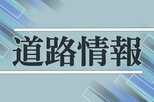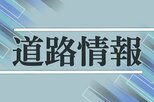人を乗せて空を飛行する次世代の移動手段「空飛ぶクルマ」。国内の自治体では交通、防災、医療、観光など地域のニーズに合わせて導入を目指す動きがある。先行自治体の一つで、救命救急医療と災害救助に活用する方針を掲げる宮崎県延岡市は3月2日、初めて試験飛行を実施した。試験飛行の現場を訪ね、脱炭素の観点でも注目されている新技術を間近で見た。(論説編集委員・仲屋淳)
3月2日午後2時前、宮崎県延岡市の九州保健福祉大学のグラウンドには、延岡市民をはじめ県内外から訪れた約300人が、白い機体が飛び立つのを見つめていた。
機体は中国製の「EH216」(高さ約1・8メートル、幅約5・6メートル)だ。2人乗りで、垂直に離着陸する。

空飛ぶクルマの特徴は、狭い場所での垂直離着陸、自動操縦ができることだ。電動で脱炭素の観点でも優れている。騒音はヘリコプターよりも確かに小さい。
一般的に航空機の部品数は、大型機になれば約300万点といわれる。空飛ぶクルマは1万〜2万点だ。部品が少なければ機体価格や、整備費用も安くなる。

操縦は地上からの遠隔操縦だ。運航前、会場で「携帯電話を電波が発しない機内モードにして」と注意が呼びかけられた。
操縦は各地で...
残り1969文字(全文:2484文字)