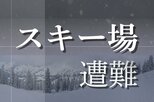夏山シーズンが佳境を迎え、季節は秋に向かいつつあります。猛暑の今年は、涼を求めて高い山に登る人も多かったのではないでしょうか。しかし、山は標高の高低にかかわらず、危険と隣り合わせ。登山道からの滑落や道迷い、熱中症などによる山岳遭難への備えは欠かせません。
登山者によって知識、経験、体力はさまざまです。遭難の原因としては、体力的に無理な計画を立てたり、経験に見合わない技術的に難易度の高い山に挑戦したりしたことが挙げられます。
「自分の体力、技術的にどんな山なら登っても大丈夫なのか?」。そんな疑問のヒントになるのが「山のグレーディング」です。公表元の新潟県などにグレーディングの見方や活用方法について聞きました。新潟県内の山の難易度と山岳遭難件数などをまとめた「新潟100名山難易度マップ」も作成しましたので、併せてご確認ください。
◆そもそもグレーディングとは?
山のグレーディングとは、新潟県を含めた10県1山域が発表している、いわば「山の難易度表」です。全国有数の山岳県である長野県が山岳遭難の増加を受けて、2014年に公開したのが始まりで、新潟県は翌15年から公開しています。
登山者が自分の体力と技術に合った山を選べるように、各県が統一された基準で難易度を定めています。登山ルート別に雪のない時期の好天時を想定し、「体力度」を10段階、「技術難易度」を5段階で評価しています。それぞれの要素について解説します。
◆「体力度」とは?
体力度は1~10の数字で示されます。数値が大きいほど、よりルートが長くなったり、標高差が大きくなったりします。新潟県では、各山の登山ルートのコースタイムと、地図ソフトなどで把握した登山ルートの登山口から山頂までの標高差を基に体力度を算出しています。具体的には以下のような目安となっています。
- 1~3:日帰りが可能な山
- 4~5:1泊以上が適当な山
- 6~7:1~2泊以上が適当な山
- 8〜10:2~3泊以上が適当な山
◆「技術難易度」とは?
一方、技術難易度は登山道の整備状況や危険箇所の有無などによって、A~Eのアルファベットで示され、AからEの順に登山者には以下のような技術が求められます。
| 難易度 | 登山道 | 求められる技術・能力 |
|---|---|---|
| A | ●概ね整備済 ●転んだ場合でも転落・滑落の可能性は低い ●道迷いの心配は少ない |
●登山の装備が必要 |
| B | ●沢、崖、場所により雪渓などを通過 ●急な登下降がある ●道が分かりにくい所がある ●転んだ場合の転落・滑落事故につながる 場所がある |
●登山経験が必要 ●地図読み能力があることが望ましい |
| C | ●ハシゴ・くさり場、また、場所により雪渓や渡渉箇所がある ●ミスをすると転落・滑落などの事故となる場所がある ●案内標識が不十分な箇所も含まれる |
●地図読み能力、ハシゴ・くさり場などを通過できる身体能力が必要 |
| D | ●厳しい岩稜や不安定なガレ場、ハシゴ・くさり場、藪漕ぎを必要とする箇所、場所により雪渓や渡渉箇所がある ●手を使う急な登下降がある ●ハシゴ・くさり場や案内標識などの人工的な補助は限定的で、転落・滑落の危険箇所が多い |
●地図読み能力、岩場、雪渓を安定して通過できるバランス能力や技術が必要 ●ルートファインディングの技術が必要 |
| E | ●緊張を強いられる厳しい岩稜の登下降が続き、転落・滑落の危険箇所が連続する ●深い藪漕ぎを必要とする箇所が連続する場合がある |
●地図読み能力、岩場、雪渓を安定して通過できるバランス能力や技術が必要 ●ルートファインディングの技術、高度な判断力が必要 ●登山者によってはロープを使わないと危険な場所もある |
県によると、難易度は各地の山岳会や市町村の担当課に各山の登山ルートを点検してもらい、鎖場や雪渓、痩せ尾根などルート上の危険箇所を調べて、ランク付けを行っているとのことです。


◆新潟県内の山の難易度は?
それでは、新潟県内の山の難易度はどのくらいなのでしょうか?...