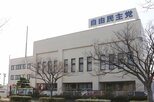今年最大の政治決戦となる参院選の公示まであと2日に迫ったが、近年の選挙では交流サイト(SNS)が情報収集の場となる一方で、偽・誤情報や誹謗(ひぼう)中傷が拡散されるなど課題も指摘されている。南魚沼市にある国際大付属の研究所、グローバル・コミュニケーション・センター(東京)の山口真一准教授(社会情報学)に選挙時のSNSとの向き合い方などを聞いた。
-2024年の東京都知事選や兵庫県知事選では、SNSが選挙結果に影響を与えたとされます。SNSと選挙の関係に変化があったのでしょうか。
「SNSや動画サイトを従来のエンターテインメントとしてだけではなく、選挙という重要なイベントの情報源として活用する人が非常に増えた。若い世代だけでなく、中高年も情報源として活用しているのはこれまでになかった現象だ」
-SNSが大きな力を持つことの利点と課題は何でしょう。
「利点は政治の裾野が広がり、関心を持つ人が増えること。実際に兵庫県知事選では前回より投票率が15ポイント近く上がっている」
「課題は過激な言説や真偽不明な情報が拡散されやすいことだ。政策に目が向かず、本当かどうか分からない情報を基にした対立構造や自分なりの“正義”で投票先を決めてしまう。選挙で分断が進みすぎることも深刻な課題だ。一般市民の間で対立が深まり、誹謗中傷が吹き荒れては健全な民主主義の運営が難しくなる」
-なぜSNSでは真偽不明な情報が広まりやすいのでしょう。
「SNSで最も拡散されやすいのは怒りの感情だ。よりセンセーショナルな情報が目を引きやすく、極端な意見ほど発信されやすい」
-インターネットは閲覧履歴から自分の考え方に近い情報ばかりが表示される「フィルターバブル」に陥りやすいと言われます。
「誰もがフィルターバブルに陥っていると知っておくことが大事だ。ネットで見ているのは、切り取られたすごく狭い世界の意見だと理解すること。意識的に新聞やテレビなど別の情報源に当たり、疑う癖を付けてほしい」...