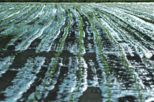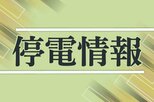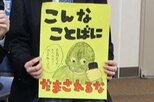家族以外とほとんど関係を持たない「ひきこもり」状態の人が全国で115万人以上いるとされ、社会問題化している。政府は今国会で孤独・孤立対策を推進する法案を提出する方針だ。ひきこもりは実態がつかみにくい。当事者の多くは、社会とつながりたいという意思を持っているものの、適切な支援が十分届いていないのが現状だ。新潟県内の当事者に話を聞き、支援を模索する県内外の動きを追った。(4回連載の4回目)
部屋の窓を閉め切り、天井からつるされた電灯をずっと見つめていた。ひきこもっていた20代の中頃だ。「体は健康だけど寝返りも打てなかった。今思い出しても怖い」。十日町市の桑原晴民(はるたみ)さん(36)が振り返る。
小学1年の夏休み明けから不登校になった。中学卒業後に「何もやらなければこもってしまう」と危機感を抱き、アルバイトを経て定時制高校に通った。

桑原晴民さんが自宅から撮影した月
声が小さく、会話がうまくできないことがコンプレックスだった。「周りが自分を気にしているわけじゃないと思うけど、動くと誰かに見られている気がした」と明かす。座席から一歩も動けずトイレも我慢した。高校1年の時は誰とも口をきけなかった。
大学に進み、卒業後は就職した。だが、仕事についていけなかった。誰かに嫌がらせをされたわけではない。人前でうまく話せず要領よく働けないことが申し訳なく、自分を責めた。体が動かなくなり、仕事を辞めた。
ひきこもり状態だった10年ほど前、高校の同級生から十日町市の不登校、ひきこもり支援グループ「フォルトネット」に誘われた。寸劇の裏方やイベントのチラシづくりから社会参加が始まった。
最初は途中で帰宅することもあったが、カメラに興味を持つと活動の範囲が広がった。「ファインダーをのぞくと自分の顔が隠れる。周りから見えなくなるから」という。今ではフォルトネットの記録係を任され、写真はひきこもり家族会の情報誌に掲載されるようになった。

カエル(桑原晴民さん撮影)
昨年から、ひきこもり状態の人らと対話する支援活動を始めた。フォルトネット代表の関口美智江さん(67)は「何もしゃべらなくても、温かく包み込む。自分もひきこもりを経験しているから気持ちが分かるのだろう」と推測する。自然体で活動する桑原さんは「自分が支援されながら、支援している感じ」とほほ笑む。
つらい時期、桑原さんがうれしかったのは誰かに声をかけてもらうことだった。しかし優しい声にうまく対応できず、ふさぎ込むこともあった。
高校2年の時、転入生の声がすっと心に入ってきたことが印象に残っている。「不登校だったからと気を遣って声をかけてくれる人と、そんなのは関係なく普通に声をかけてくれる人は何かが違う」と考えた。心身ともに厳しい時は支援を無理に受け入れなくてもいいと思う。声かけに何も答えないのも、意思表示の一つだ。
桑原さんは昨年12月から職業訓練校に通い始めた。何か動いていないと、再びこもってしまう不安に陥る。それでも、フォルトネットの活動に携わりたいと意欲を見せる。「すごいことはできないけど、支援に関わらせてもらえたら」と控えめに語った。
=おわり=
(この連載は報道部・中村茂雄が担当しました)
「ウェブ写真展×ともしび求めて」を掲載中
× ×
この連載への感想や、ひきこもりで悩んでいる当事者の方、家族、支援者の方の声をお寄せください。こちらの専用フォーム(クリックやタッチをするとページが変わります)から送ることができます。
◇ひきこもりに関する公的な電話相談窓口(相談料は無料。通常の電話代がかかります)
新潟県ひきこもり相談ダイヤル 025(284)1001(月〜金曜、午前8時30分〜午後5時。祝日、年末年始除く)。
新潟市に在住の方 新潟市ひきこもり相談支援センター 025(278)8585(火〜土曜、午前9時〜午後6時、祝日・年末年始除く)。