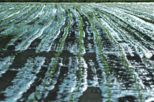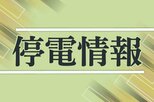連載の記事はこちらから(会員以外の方も読むことができます)
<1>出せないSOS
<2>推計値115万人
<3>「まず生きる環境をつくる」
<4>カメラが広げた世界
取材を終えて 編集局報道部・中村茂雄
まず、今回取材で厳しい体験をお話していただいたひきこもり当事者の皆さんに感謝します。
取材を通し、ひきこもり支援には、二つの考え方を深めることが必要と感じました。
一つ目は時間をかけて当事者と向き合いながら解決の糸口を探っていくこと。ひきこもること自体を否定してはいけません。窒息しそうな現代社会で、生きる術として「こもる」ことは必要だからです。気持ちが外に向いた時に備え、支援者側が複数の選択肢を用意することが求められます。
二つ目は今、目の前にある命の危機を救う手だてです。いわゆる「8050問題」を抱える家庭への介入になりますが、高齢者の介護中にひきこもり状態の人を見つけた時の対応に悩む担当者の悲痛な声を耳にしました。健康が悪化しても周囲に助けを求められない「セルフネグレクト」(自己放任)状態だった場合、どう支援していけばいいのでしょうか。
こうした時、福祉関係者の「横のつながり」に期待が集まります。ただ、言うほど簡単な作業ではないようです。それぞれが単務を抱えており、組織として方向性を共有していくことが難しいという声もありました。
ならばと、トップダウンで動いたのが、連載の2回目で取り上げた東京都江戸川区です。ひきこもり施策を担当する部署をつくり、大規模アンケートを行いました。2度、3度と手間を惜しまず再調査を行い訪問支援が必要な家庭を絞り込んでいる最中です。江戸川区では、ひきこもりの問題については「行政が最後の砦(とりで)」という考えが大前提にありました。アンケートにはかなりの予算が必要でしたし、方法を巡り反発の声もありました。ですが、必要性を住民らに丁寧に説明する「本気度」が際立っているように感じました。
江戸川区の現場のトップは40代の女性です。バブル崩壊後の就職氷河期を生き「人ごととは思えない」と話していたのが印象的です。就労のつまずきがひきこもりのきっかけになることは非常に多いと言われています。今回、連載で紹介した支援者の多くが「氷河期世代」に該当し、また強い目的意識がありました。今後のひきこもり支援を進める上で、こうした人材をどう生かすが問われています。

連載4回目に取り上げさせてもらった桑原晴民さんが、自宅から撮影した月の写真
× ×
連載「ひきこもり支援の模索 新潟県内の当事者に聞く」への感想や、ひきこもりで悩んでいる当事者の方、家族、支援者の方の声をお寄せください。こちらの専用フォーム(クリックやタッチをするとページが変わります)から送ることができます。
◇ひきこもりに関する公的な電話相談窓口(相談料は無料。通常の電話代がかかります)
新潟県ひきこもり相談ダイヤル 025(284)1001(月〜金曜、午前8時30分〜午後5時。祝日、年末年始除く)。
新潟市に在住の方 新潟市ひきこもり相談支援センター 025(278)8585(火〜土曜、午前9時〜午後6時、祝日・年末年始除く)。