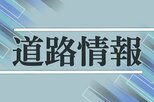新潟水俣病第5次訴訟カ水俣病被害を訴える新潟市などの男女が2013年12月、国と昭和電工(現レゾナック・ホールディングス)に損害賠償などを求め新潟地裁に提訴した訴訟。原告が水俣病かどうかや、九州に続き新潟県でも水俣病が発生したことに対する国の責任の有無が主な争点となっている。で新潟地裁は4月、国の救済策から漏れた原告47人のうち26人を水俣病と認めた。同種訴訟で大阪、熊本両地裁も原告の多数を水俣病認定しており、原告側は早期決着を国に訴えている。熊本県での懇談会で環境省側が被害者の発言を遮断した問題が起きるなど国の姿勢が問われる中、新潟地裁判決の意義や被害者救済の在り方について、公害訴訟に詳しい東北大大学院法学研究科の樺島博志教授(56)=法理学=に聞いた。(報道部・坂井有洋)
-新潟地裁は、原告26人を水俣病熊本県で1956年に公式確認された病気で、その後、新潟県の阿賀野川流域でも集団発生した。毒性の強いメチル水銀を含む工場排水で汚染された魚介類を食べた人やその胎児が水銀中毒を発症し、亡くなった人も多い。症状は感覚障害や運動失調、視野狭窄(きょうさく)など。外見的な異常は現れずとも、手足のしびれや頭痛などに悩まされ続ける人もいる。とした一方で、19人の罹患(りかん)を認めませんでした。判決をどうみますか。
「第5次訴訟と同じ損害賠償訴訟で、最高裁などがすでに国の患者認定の基準を否定する判断を示しているが、新潟地裁判決はそれらに依拠していない」
「判決では一人一人が水俣病かどうかという医学的な個別判断をしている。しかしそれは法律家の傲慢(ごうまん)だ。法律家に医学的判断はできないが、裁判官は病気の原因を特定できると過信している。判断が間違っていた時には、水俣病の人を切り捨てることになるという覚悟があったのか、疑問だ」
-水俣病かどうかはどう判断すべきでしょうか。...