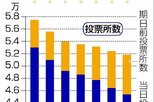衆議院選挙(衆院選)公示日の10月15日まで1週間に迫った。今回から新潟県の小選挙区は新たな区割りに変わる。衆院に小選挙区比例代表並立制小選挙区は最多得票者1人が当選。全国を11ブロックに分ける比例代表は政党・政治団体(政党等)の得票に応じて議席を配分し、各政党等の候補者名簿の上位から順に当選となる。定数は465人(小選挙区289、比例代表176)。政党等に所属して立候補する小選挙区の候補者は比例代表に重複して立候補できる。小選挙区で敗北しても、所属政党等が比例代表で獲得した議席数や名簿順位などによって「復活当選」も可能。複数の重複立候補者が同一順位の場合、小選挙区の当選者の得票数にどれだけ迫ったかを示す惜敗率が高い順に復活当選する。が導入され四半世紀余り。県内選挙エリアの抜本的な見直しは初めてとなる。これまで同じ自治体の中でも複数の選挙区が入り交じる地域もあったが、市区町村の境界線で分けられることになる。候補者にとっては未知の戦いとなり、手探り状態のまま本番に突入する。
今回の区割り変更は、「1票の格差選挙区ごとの国会議員1人当たりの有権者数が異なることにより、投票の価値に不均衡が生じる問題。人口の多い都市部ほど1票の価値は軽くなりやすい。例えば当選者1人の二つの選挙区があり、それぞれの有権者数が40万人と20万人だと格差は2倍となる。」の是正によるものだ。2022年6月に衆院選挙区画定審議会(区割り審)が全国の小選挙区定数を「10増10減」する新区割り案を岸田文雄首相(当時)に勧告した。それに基づき、新潟県は六つの選挙区(各定数1)が五つの選挙区に減り、選挙エリアも再編された。
◆「市区町村の区域は分割せず」…つまりどうなった?
旧区割りは「平成の大合併」前の市町村区画がベースになっていたため、例えば、長岡市は旧5区のほか旧2区、旧4区がモザイク状に広がっていた。
新潟市北区も旧1区、旧3区、旧4区に、新潟市南区は旧1区、旧2区、旧4区にそれぞれ3分割されており、同じ地域に住む有権者の間で選択できる候補者が異なる状況が続いていた。
今回導入される新区割りは、区割り審が「市区町村の区域は分割しない」などを原則に線引きし直したものだ。...