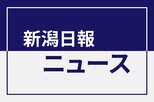地震や水害といった災害に備える必要性は、自治体、企業、家庭のそれぞれで高まっている。20年前の中越地震2004年10月23日、新潟県中越地方を震源として発生した地震。旧川口町(現在の長岡市)で震度7、旧山古志村、旧小国町(いずれも現長岡市)、小千谷市で震度6強を観測した。新潟県や内閣府の資料によると、地震の影響で68人が亡くなり、4795人が重軽傷を負った。住宅の被害は計12万1604棟で、このうち全壊は3175棟、大規模半壊は2167棟、半壊は1万1643棟だった。などの経験を基に、避難時を想定した非常食や生活用品は多様化が進む。新潟県長岡市稲保4の防災用品の大手商社「船山」に、万一の際に役立ち、注目される商品について聞いた。
かつて乾パンやアルファ化米が主だった防災食は、国内の度重なる災害を経て大きく進化した。味や栄養価の向上はもちろん、災害時の使いやすさに配慮した工夫が目立つ。

例えば「レトルト玄米保存食ちゅらめしシリーズ」(愛知県・幸源)は、開封後そのまま食べられ、スプーンも付いている。トマトリゾットやエスニックピラフなど、メニューも多彩だ。
船山の消防防災部の小山敦史さんは「メーカー側がひと手間かけることで、被災地の負担を減らそうとしている」と説明する。普段使いも兼ねて、電子レンジの加熱か水を注ぐだけで食べられる商品も多い。
防災食に力を入れている亀田製菓グループの尾西食品(東京)をはじめ、食物アレルギー特定原材料28品目を使わない商品を扱うメーカーも多くなった。船山もそうした商品の取り扱いを進め、カタログにアレルギー対応の一覧を掲載している。

避難生活では疲れが取れにくくなるため、...
残り936文字(全文:1460文字)