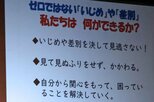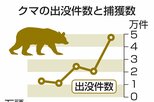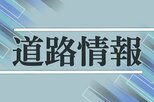「“生存それ自体がはらんでいる絶対の孤独”を私たちは抱えている」。新潟・市民映画館シネ・ウインド代表の齋藤正行さん(75)は、坂口安吾の随筆「文学のふるさと」を引き合いに、生きることの根底には孤独があると切々と語り、続けた。「生きるなんて、本当は誰もがつらいに決まっているんだ」。3月は自殺対策強化月間。長年自殺対策と向き合ってきた齋藤さんに思いを聞いた。(報道部・森田雅之)
2009年、新潟市の自殺率(人口10万人当たりの自殺者数)が28・7人に上り、全国の政令指定都市の中で最も高くなった。自分の娘に「新潟を世界で一番いいところにする」と約束していただけに、じっとしてはいられなかった。
できることから始めようと11年、新潟NPO協会として、自殺対策に取り組む県内の活動団体を紹介する冊子「死ぬな!」の発行を始めた。新潟市自殺対策実務者ネットワーク会議のメンバーとしても、勉強会や街頭活動を通じて自殺を巡る課題に向き合い続ける。
厚生労働省の人口動態統計によると、新潟市の自殺者数は政令指定都市となった07年以降、09年の233人をピークにやや減少傾向にあるが、23年は135人(男性100人、女性35人)に上り、踊り場の状況にある。
経済不安や健康問題など自殺に追い込まれる事情はさまざまだが、「生きることがつらいのは、もはや個人の問題ではない。人間そのものが何かを考えろ」と訴え、生きづらさを抱える人には、いつもこう語りかける。「気が狂うまで考えよう」

「いくら考えても解決できず、気が狂いそうになることもあるだろう。それでも考える努力を続ければ思考の幅が広がり、新たに見えるものがあるはずだ」との思いからだ。
生きづらさを抱える中では、映画や文学、音楽といった芸術が心の支えになると信じている。たとえ悲惨なものが根底にあろうとも、作家が作品で提示している物語を解釈し、自分で新しく豊かな物語を描いてほしいと願う。
自殺対策に長年取り組むが、人を救えたかどうかは分からない。積み上がるのは「救えなかった」という結果だけだからだ。
人は、今日も明日も経験のない日を送る。自分自身も、それは恐ろしいことだと思う。生きることはつらい。「それでも考えよう。つらくてつらくてしょうがないことを」。そして、「死ぬな!」と言い続ける。
自殺対策強化月間の3月、新潟市中央区のシネ・ウインドでは14日まで、東日本大震災と東京電力福島第1原発事故の被災者らを追ったドキュメンタリー映画「生きて、生きて、生きろ。」を上映している。火曜休館。