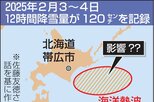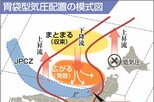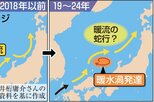水中グライダーを組み立てる和川拓さん(左)。日本海の観測に貢献している=3月、新潟市中央区
長期企画「碧(あお)のシグナル」の第5シリーズ「気候変動に挑む」は、海や大気の変化を探る研究者らに迫ります。(5回続きの5)
地球の表面積の7割を占める海の中をどう効率的に調べるのか。切り札の一つがロボット技術だ。国の水産資源研究所新潟庁舎(新潟市中央区)は海の中を自動で観測する「水中グライダー」を活用する。
全長約2メートルの丸みを帯びた細長い機体に翼が付くのが特徴で1台数千万円ほど。内部の浮きやおもりの位置を調整し、移動する。
主任研究員の和川拓さん(43)は「船舶では難しい海が荒れる時でも調査できるのが強みだ」と語る。水深1000メートルまで潜ったり浮いたりしながら水温や塩分、酸素を測定する。時速1ノット(1・85キロ)以下の低速で進み、3、4カ月は連続して観測できる。
▽佐渡沖で「低塩水」発見
水中グライダーの歩みは平たんではなかった。2007年、...
残り1267文字(全文:1650文字)