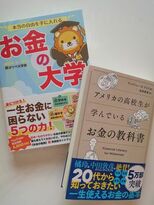【2021/04/28】
「子どもがゲームにのめり込んだ要因は」「親が歩み寄る姿勢を見せていこう」-。新潟県上越市のコミュニティセンターで月1回、子どものゲーム依存や不登校に悩む親が集まり、語り合う家族会がある。
この会を立ち上げたのは、ゲーム依存の高校生の息子を持つ上越市の会社員、大原政志さん(59)=仮名=。「周囲の理解が進んでいない。せめて同じ悩みを抱える家族が分かち合える場が必要だと思った」
息子がゲームに没頭し始めたのは中学2年の頃。朝起きられず学校に行けなくなった。ゲーム機を取り上げると逆上した。学校や児童相談所に相談しても「ゲーム時間を制限して」など既に試したことを提案されるばかり。「思いつく事は全てやって駄目だったから来ているのに…。切迫感が伝わらずズレを感じた」
会をつくることを決意し、ゲーム依存の専門外来がある病院にチラシを置き参加者を募った。
現在のメンバーは5人。家族同士で話すことで親の意識が変わってきたと感じている。大原さん自身も「親も変わる必要がある。ゲームに興味を持って子どもと共通の話題をつくるなど、対応を変えるのも大事だ」と気付いた。
高校生の息子がゲームにはまり不登校という参加者の50代女性は「今でも制服姿で通学する子を見かけると、いいなと思う」と打ち明けるが、「以前は登校させようと必死だったが息子が自ら行動に出るまでじっくり待とうと思えるようになった」と話す。
■ ■
ただ、ゲーム・ネット依存に悩む家族が集う場は県内でわずか4カ所と、アルコールなど他の依存症に比べてかなり少ない。世界保健機関(WHO)が「ゲーム障害」を国際疾病として正式に認定したのが2019年5月。ゲーム・ネット依存が病気だとはまだ世間に知られているとは言い難く、家族からは「周囲から理解されない」「家族会が少なく、同じ悩みを持つ人と知り合えない」といった切実な声が上がる。
新潟市と上越市で「ネット・ゲーム依存症家族の会」を開く堅田和子さん(53)は「会にもなかなか人が集まらない」と嘆く。「親が子どもの異変に気付いても、ゲームのやり過ぎで相談するという発想自体が持てないのだと思う。親が対応を学ぶことが第一歩になる」と訴える。
■ ■
第三者に相談することで解決の道筋が立つケースは少なくない。県内の主婦、小林美緒さん(35)=仮名=は昨年4月に突然、40代の夫から「カードの請求額が増えて、自分だけでは払えなくなった」と告白された。利用明細書を確認すると、2年間でスマートフォンのゲーム課金に100万円以上を費やしていた。
問いただすと課金によって優位に立てるオンラインゲームにはまっており「仲間に認められてやりがいがあった」とつぶやいた。夫への不信感でいっぱいになり、スマホの履歴を全てチェックしなければと考えるようになった。請求額は貯金を崩して払ったが「気軽に話せる内容ではなく、誰にも相談できずつらかった」。
そんな時に、県精神保健福祉センターで依存症の相談があることを知った。取り乱した様子の小林さんを見て、スタッフは「冷静になって。極端に制限するとかえって悪化する」と話した。アドバイスを受けて完全に禁止するのではなく課金額を5千円に制限するなどして、依存は落ち着いた。
「あの時、アドバイスを得られて良かった」と小林さん。誰かに相談することの大切さを身に染みて感じている。