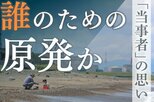新潟県に立地する柏崎刈羽原発1985年に1号機が営業運転を開始した。全7基の出力合計は821・2万キロワットで世界最大級だが、2023年10月現在は全基停止中。東京電力は2013年に原子力規制委員会に6、7号機の審査を申請し、17年に合格した。その後、テロ対策上の重大な不備が相次いで発覚した。終了したはずだった安全対策工事が未完了だった問題も分かった。で大きな事故が起きれば、広範囲に影響が及ぶ。いわば県民の誰もが当事者だ。柏崎刈羽原発は6月、技術的には再稼働東京電力福島第1原発事故を踏まえ、国は原発の新規制基準をつくり、原子力規制委員会が原発の重大事故対策などを審査する。基準に適合していれば合格証に当たる審査書を決定し、再稼働の条件が整う。法律上の根拠はないが、地元の自治体の同意も再稼働に必要とされる。新潟県、柏崎市、刈羽村は県と立地2市村が「同意」する地元の範囲だとしている。できる準備を整えた。国や東京電力が地元同意新規制基準に合格した原発の再稼働は、政府の判断だけでなく、電力会社との間に事故時の通報義務や施設変更の事前了解などを定めた安全協定を結ぶ立地自治体の同意を得ることが事実上の条件となっている。「同意」の意志を表明できる自治体は、原発が所在する道県と市町村に限るのが通例。日本原子力発電東海第2原発(茨城県東海村)を巡っては、同意の権限は県と村だけでなく、住民避難計画を策定する30キロ圏の緊急防護措置区域(UPZ)内の水戸など5市も対象に加わった。を求めてくる中、住民は何を思うのか。長期企画「誰のための原発か 新潟から問う」の今シリーズでは、原発事故時の避難行動を区分するラインや県境など、境界線の内外を歩いて聞いた。(6回続きの6)
柏崎市の中央部に位置する北鯖石地区。初夏の風が水をたたえた田んぼを吹き渡り、土の香りを運んでくる。地区を貫くように通る北陸道の向こうに東京電力柏崎刈羽原発が見える。

北鯖石は原発から直線距離で約6キロに位置する。北陸道は原発事故時の避難路でもある。ただ原発から半径5〜30キロ圏は避難計画都道府県と市町村は、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づく地域防災計画を作成することが求められる。また、原子力災害対策指針に基づき、原子力災害対策重点区域を設定する都道府県と市町村は、地域防災計画の中で対象となる原発などの施設を明確にした原子力災害対策編を定めることになっている。新潟県の広域避難計画は、地域防災計画に基づき策定されている。上、事故があってもすぐには遠くへ逃げないことになっているエリアだ。住民は自宅などに屋内退避原発の事故などにより、放射性物質が放出されている中で避難行動を取ることで被ばくすることを避けるため、自宅など屋内施設にとどまること。国は原発からおおむね半径5~30キロ圏に住む人は、放射性物質が放出された場合は「屋内退避」するとしている。屋内退避中は戸締まりや換気設備を止めることなどが必要となり、数日間継続することも想定されている。する。より近い5キロ圏内の...