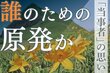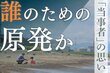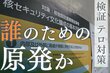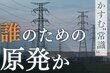1969年に新潟県の柏崎市と刈羽村などの議会が原発誘致を決議して、54年が過ぎた。東京に拠点を置く東京電力が営業運転を始めた柏崎刈羽原発は2023年12月現在、全7基が停止中だ。発電した電気の大部分を首都圏に送り続けた世界最大級の原発は、県民に何をもたらしたのだろう。自治体は原発設置に伴う税収、地域には交付金で公共施設も整備された光の部分がある一方、2002年のトラブル隠し以降、東電自らが県民の信頼を裏切る負の事態も相次いだ。福島第1原発事故、その後の柏崎刈羽原発でのテロ対策上の重大な不備…。問題が起きる度、県民は原発の議論を強いられてきた。一体誰のための原発なのか。新潟から原発を巡る疑問を考えていく。

誰のための原発か-新潟から問う 東京電力柏崎刈羽原発
ここから記事が始まります

[誰のための原発か]「当事者」の思い・番外編<下>―東京の声 電気代上昇で再稼働待望、「危険押しつける都民はずるい」と自省も 東京電力柏崎刈羽原発の新潟から問う
国や東京電力が柏崎刈羽原発7号機の再稼働を求めて「生産地」の新潟県に働きかけを強める現状は、「大消費地」に暮らす東京都民の目にどう映るのか。長期企画「誰のための原発か 新潟から問う」の今シリーズ番外編では、都内各所でさまざまな人に考えを聞いた。(2回続きの2)
記事はここまでです