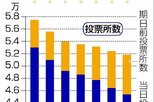新しい選挙区割りで初めて実施された2024年の衆議院選挙(衆院選)で、新潟県内5小選挙区は立憲民主党が全勝した。小選挙区で野党系が全勝したのは、民主党政権が誕生した2009年以来、15年ぶり。過去の衆院選では、どんな攻防が繰り広げられてきたのか。現行の選挙制度になった1996年から前回2021年の衆院選までの結果を、当時の出来事や世相とともに振り返る。(肩書、数字は当時)
- 新潟県内5小選挙区は立憲民主全勝、裏金問題の自民高鳥修一氏・細田健一氏は落選
- 決戦「10・27」総選挙!結果のまとめページ
- 各候補者はどう戦った?新潟県内各選挙区、戦いの跡
- 「衆院選2024」特設ページはこちら
1996年10月 「新党ブーム」が先細り

定数が複数の中選挙区制から小選挙区比例代表並立制に移行して最初の衆院選は、自民党、社会党(社民党の前身)、新党さきがけの連立政権下の1996年10月に行われた。全500議席のうち、自民党が解散前から28増の239議席を獲得する。93年の「新党ブーム」が一転。社民、さきがけは議席を減らして閣外協力に転じ、第2次橋本龍太郎内閣は自民単独内閣となった。
新潟県内は、全6小選挙区を自民公認候補が独占。石川や長野など5県で構成する比例代表北陸信越ブロック(定数13)で新潟県関係は自民党と新進党の比例単独候補各2人、小選挙区との重複で民主党候補1人が復活当選した。
小選挙区の投票率は、全国が59・65%で初めて6割を下回った。知事選とダブル選だった県内も前回から約7ポイント下がり、68・85%で戦後ワースト2位だった。
選挙前年の95年は阪神大震災や地下鉄サリン事件など大きな災害や事件が発生し、危機対応を巡って政治不信が高まった。選挙翌年の97年は消費税が3%から5%に引き上げられたほか、山一証券など金融機関の破綻も相次いだ。

新潟県内でも証券会社や信用組合の破綻・廃業が続き、99年7月には新潟証券取引所閉鎖が決定、99年10月には地銀4行の一角の新潟中央銀行が経営破綻した。バブル経済崩壊後の国内経済はさらに視界不良となった。
2000年6月 ベテラン落選、自民に衝撃
2000年4月、自民、公明など3党による連立政権で首相を務めた小渕恵三氏が脳梗塞で入院し、自民党幹部5人の協議で、党幹事長の森喜朗氏が党総裁と首相の後継に決まる。小渕氏は5月に死去。「密室談合」とされた誕生の経緯に首相自身の数々の失言も相まって、森内閣の支持率は一貫して低迷する。
2000年6月の衆院選は、森内閣への信任が最大の争点だった。森氏は新潟市での遊説で「(無党派層は)寝てしまってくれればいい」などと発言。自民党は全480議席のうち233議席と、解散時から38議席減らした。一方、都市部を中心に躍進した野党第一党の民主党は32増の127議席へと伸ばした。
小選挙区制となって2回目の当時は候補者調整の過渡期でもあり、地盤や支持層が重なる自民系候補同士の熾烈(しれつ)な戦いが各地で繰り広げられた。新潟県内も同様で、全6小選挙区のうち自民は前職4人が再選したものの、閣僚経験もあるベテラン2人が落選。無所属新人1人、民主元職が当選し「自民王国」に衝撃が走った。
公明、保守両党を加えた3党では絶対安定多数を確保した森政権。しかし、自民党内では元幹事長らが野党の内閣不信任案に同調しようとした「加藤の乱」が起こる。不発に終わったものの党内は分裂。翌01年には米ハワイ沖で愛媛県立水産高の実習船「えひめ丸」が米原子力潜水艦に衝突し9人が死亡した事故の対応で批判を招き、同年4月、森内閣は退陣した。
2003年11月 マニフェストで民主躍進

2001年4月、自民、公明、保守3党連立政権の森喜朗首相の後を受け、小泉純一郎氏が首相に就任する。派閥の順送り人事廃止や「聖域なき構造改革」を打ち出し、発足当初から国民の人気を集めた。
02年9月、小泉首相が北朝鮮を電撃訪問し、国交正常化実現への努力を表明した日朝平壌宣言に署名。金正日総書記が日本人拉致を認めて謝罪し、本県の蓮池薫さん、曽我ひとみさんら拉致被害者5人が10月に帰国した。
03年11月の衆院選は「マニフェスト選挙」と呼ばれた。直前に自由党を吸収した民主党が、政権を担った際の目標に期限や数値、財源などを明記したマニフェスト(政権公約)を示し、他党もこれに追随した。
全480議席を争い、自民党は解散時から10減らしたものの237議席を獲得して第1党を維持。民主党は比例で一挙に72議席を獲得し、小選挙区と合わせ40増の177議席と躍進する。社民、保守新など少数政党が埋没し、二大政党時代の到来を印象づけた。
新潟県内では、全6小選挙区のうち民主党が新人2人を含め3人当選。元外相で与党に批判的な無所属元職の田中真紀子氏を含め、野党系が過半数を制した。
01年の米同時多発テロや米英によるイラク攻撃を経て、03年に有事法制関連法やイラク特措法が成立。自衛隊のイラク派遣を巡っては、新潟市や三条市など県内市町村議会で延期や中止を求める意見書が相次ぎ可決されたが、04年1月、小泉政権はイラク派遣を開始する。
2005年9月 「郵政解散」で自民が圧勝
2005年7月、小泉純一郎首相の悲願でもあった郵政民営化法案が通常国会に提出され、5票差で衆議院を通過する。自民党から多数の造反者が出て参議院で否決されると、首相は「『郵政解散』だ。賛成か反対か国民に問いたい」として衆議院を即日解散する。
郵政民営化の是非に争点が絞られた異例の選挙。小泉首相は反対派候補に党公認を与えず、その選挙区には女性官僚や著名人ら「刺客」を擁立した。9月の投開票の結果、自民は84議席増の296議席と歴史的勝利を収める。一方、民主党は64減の113議席と大敗し、岡田克也代表が辞意を表明した。

だが、新潟県内では自民候補に郵政解散の追い風は吹かなかった。全6小選挙区で当選した自民前職は稲葉大和、近藤基彦の両氏。他は民主前職の筒井信隆、西村智奈美、菊田真紀子の3氏と民主の支援を受けた無所属前職の田中真紀子氏だった。自民は元職吉田六左エ門と新人高鳥修一の両氏、民主は新人鷲尾英一郎氏が比例復活当選した。
比例単独では、04年の中越地震被災地の「顔」として知られた旧山古志村長・長島忠美氏が自民名簿1位で初当選し、公明党の漆原良夫氏が4選した。本県関係の衆院議員は、小選挙区と比例で改選前の7人から11人へと一挙に増えた。
特定郵便局長OB組織トップのお膝元で、民営化反対・慎重派の自民候補が多かったことも背景にあった。選挙結果を受け、郵政民営化法案は衆参両院で10月に可決、成立した。
06年9月まで5年余り続いた小泉政権下では、経済や地方行財政など幅広い分野で改革が進められたが、景気回復が鈍い中で格差の拡大も課題になった。「平成の大合併」と呼ばれる市町村合併で、新潟県内は112市町村が30市町村に減り、減少幅は全国最多だった。
2009年8月 民主が大勝、政権交代実現

2007年9月、体調不良を理由に安倍晋三首相が突然、首相の座を退いた。後継の福田康夫首相も08年9月に辞任し、2代続いた「投げだし」に批判が高まった。自民党は09年7月の東京都議選など地方選でも敗北。後任の麻生太郎首相は党内対立を招くなど、求心力を失っていく。
09年8月の衆院選は、自民長期政権に対する国民の不満を背景に、「政権交代」を掲げた野党第1党の民主党が大勝した。全480議席のうち308議席を獲得。衆参両院で多数派が異なる「ねじれ」も解消し、政権交代が実現した。民主の鳩山由紀夫代表が首相に就き、社民党、国民新党との連立内閣が発足した。

新潟県内でも全6小選挙区で...