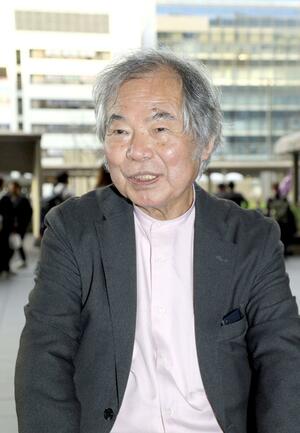
能登半島地震2024年1月1日午後4時10分ごろに発生した石川県能登地方を震源とする地震。逆断層型で、マグニチュード(M)7.6と推定される。石川県輪島市と志賀町で震度7を記録し、北海道から九州にかけて揺れを観測した。気象庁は大津波警報を発表し、沿岸部に津波が襲来した。火災が相次ぎ、輪島市では市街地が広範囲で延焼した。から1年。過疎高齢化が進む被災地はいまだ復旧の途上にある。石川県の災害危機管理アドバイザーを務めた室崎益輝(よしてる)・神戸大名誉教授(80)=防災計画=は「能登の被災集落を維持するために、中山間地が大きな被害を受けた2004年の新潟県中越地震2004年10月23日、新潟県中越地方を震源として発生した地震。旧川口町(現在の長岡市)で震度7、旧山古志村、旧小国町(いずれも現長岡市)、小千谷市で震度6強を観測した。新潟県や内閣府の資料によると、地震の影響で68人が亡くなり、4795人が重軽傷を負った。住宅の被害は計12万1604棟で、このうち全壊は3175棟、大規模半壊は2167棟、半壊は1万1643棟だった。に学ぶべきだ」と指摘する。その思いを聞いた。(報道部・平賀貴子)
-能登半島地震の被災地の現状をどう見ますか。
「支援の手が足りず、苦しんでいる被災地の現状を知るたびに胸を痛めている。ばらばらに広域避難し、行政や支援者から『見えない状態』に置かれている被災者は少なくない。このままではコミュニティーの再建は、ままならない」
-地域復興の鍵は。
「集落と支援者が被災者と心を通わせながら、まずは対面でニーズを把握する必要がある。その上で、復興支援員など外部を交えて集落単位で集まる場をつくり、復興に向けた前向きな気持ちを養わなければいけない」
-ボランティア不足も話題になりました。
「石川県が当初、不要不急の移動の自粛を呼びかけたことで、行かないことを正当化するような雰囲気になってしまった。今も、ボランティアの絶対数は足りていない。能登の人たちは孤立し、見捨てられたと感じている。今からでも遅くないので、被災地に足を運んでほしい」
-「中越の教訓は、能登半島で生かせる」と主張しています。中越地震はどのような特徴がありますか。...












