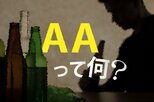毎年11月10~16日は「アルコール関連問題啓発週間」です。2014年に施行された「アルコール健康障害対策基本法」に基づくもので、お酒に関する問題への関心を深めるため、期間中は国や地方公共団体などによる広報活動が行われます。年末年始が近づくにつれ、お酒を飲む機会も増えていきます。お酒は日々の生活や人間関係の潤滑油にもなる一方で、過度な飲酒はアルコール依存症などのトラブルを招きます。アルコール依存症の取材を続けるうちに浮かび上がってきたのは、お酒の消費量は減少傾向なのに、依存症患者は増加しているという実態でした。(デジタル報道センター記者・田中渓太)
| ○アルコール健康障害専門医療機関 | 電話番号 |
| さいがた医療センター(上越市) | 025(534)3131 |
| 河渡病院(新潟市東区) | 025(274)8211 |
| かとう心療内科クリニック(新潟市江南区) | 025(382)0810 |
| 県立精神医療センター(長岡市) | 0258(24)3930 |
| 関病院(柏崎市) | 0257(23)4314 |
| 三交病院(上越市) | 025(543)2624 |
| ささえ愛よろずクリニック(新潟市秋葉区) | 0250(47)7285 |
◆お酒断ち“立派な窓際社員”になれた
「会社をサボって酒を飲んでいたら子どもに見つかって、逆ギレしてしまった」「ストレスがあると食事は食べず酒に逃げ、気づいたときには体重が37キロになっていた」…。9月末、アルコール依存症患者の自助グループAA(アルコホーリクス・アノニマス)の県内活動40周年を記念するイベントが新潟市江南区で開かれました。県内外からメンバーや医療関係者ら約70人で埋まった会場では、メンバーが依存症に苦しんだ過去や依存症の怖さについて話しました。

ある男性は、全国の営業成績が毎日貼り出される社内で「自分を大きく見せよう、周りにできる人に見られるよう」に酒浸りになっていったと振り返りました。
「会社に行くのがつらいので、酒を飲んで出社したら仕事がはかどった気がした。結局、上司に飲酒がバレて個室で詰められるまで飲み続けてしまった」と振り返りました。
AAに通い始めて、同じ依存症の患者と体験を分かち合う中で、初めて自分を大きく見せることをやめて「つらいです」と周囲に打ち明けることができたといいます。
「立派な“窓際社員”になれた」と自嘲しますが、お酒を断ったことで自分を偽らずに生きられるようになったと胸を張ります。「AAに出会い、お酒をやめて正直に人と接することができた。依存症に悩む仲間にAAの存在を広めたい」と力強く語りました。
◆依存症は孤独と深く関連
会合では、県からアルコール依存症の治療拠点機関に指定されている河渡病院(新潟市東区)の若穂囲(わかほい)徹院長が、アルコール依存症の症状や治療方法について語りました。
若穂囲院長は「依存症の治療は、患者自身が病気であると認め、病院に足を運ぶことから治療が始まる」と話します。しかし、「依存症は本人がだらしないから」といった周囲の偏見や誤解が病気を自覚する上でハードルになっていると指摘します。

依存症になる背景として「アルコールを飲み過ぎると脳の耐性がつき、アルコールがないと不安定になり、手の震えなどの症状が出たり、飲酒をコントロールできなくなったりする」とも説明します。
依存症を防ぐために1番大事なのは人間関係とも強調しました。「苦しいときに1人で悩まない。誰かの助けを借りることに引け目を感じない。『お互い様』の精神が浸透していってほしい」と語りました。
◆全国的に酒類の消費量は減少傾向も…
アルコールを取り巻く社会全体の状況はどうなっているのでしょうか。まずは国の統計などを基に、成人1人当たりの「酒類販売(消費)数量」を調べてみました。
新潟県のほか東北や南九州、沖縄などの都道府県でお酒が多く飲まれていることが分かります。それぞれ日本酒や焼酎、泡盛に象徴される酒どころです。
ただ、全国的にお酒の消費量は減少傾向にあります。国税庁の資料によると、国内の成人1人当たりの酒類消費量は1992年度の101.8リットルをピークに2023年度は75.6リットルまで大きく減っています。
背景にはノンアルコール飲料の普及や、若年層のアルコール離れなどが指摘されています。
これに対し、アルコール依存症患者は全国的に入院患者が減っている一方で、外来患者は増えています。全国の患者数は2013年度が入院患者2万8490人、外来患者が8万1722人だったのに対し、2022年度は入院患者2万5435人、外来患者が10万9323人と総数は増加しています。
新潟県でも患者数は増加傾向にあります。
お酒の消費が減っているのに、なぜアルコール依存症の患者数は減っていないのでしょうか。...