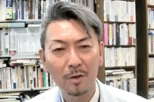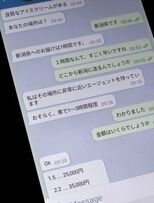【2021/06/30】
「おーい、頼むよ」
窓から心地よい風が吹き込む新潟市南区の2階建ての古民家。民間の依存症リハビリ施設「新潟ダルク」で、薬物やアルコール依存などの30~70代の男性12人が、声を掛け合いながら、クッキー作りを楽しんでいた。生地をこねるなど、役割分担しながら作業に取り組んだ。
薬物依存で、1年半前に入寮した県内出身の50代男性は「クスリを使っていたときは、食事も睡眠もとらなかった。ここには仲間がいる。一人じゃない」とはにかむ。いじめを受けた苦しさから中学生でシンナーを始め、結婚後も妻の目を盗んで使った。8回ほど入退院を繰り返した後に入寮した。今の願いは妻とまた暮らすこと。入寮して料理係として磨いた腕を「妻に披露したい」。
共同生活を送る施設では3食は原則入寮者が自炊し、当番制だ。起床は午前7時ごろで就寝は午後10時。多くが2、3人の相部屋で寝起きし、規則正しい生活を送る。過去の経歴が分かると対等に付き合えないことなどを配慮し、お互いをニックネームで呼び合う。
自身も覚醒剤の依存に苦しんだ施設長の田中五八生(いわお)さん(52)=名古屋市出身=は「薬物依存の人は周囲と孤立しがちで、人間関係のストレスを抱えている。共同生活で自分の役割が与えられる意義は大きい」と強調。それが薬物を断ち切ることにつながる。
規則正しい生活の中には、クッキー作りや海の家に行くなどのプログラムも含まれる。「薬物のない生活は楽しくなければ続かない」と田中さん。無理に頑張るストレスは再使用の引き金になるという。
■ ■
ダルクは、1985年に薬物依存の当事者が東京都内に設立。NPO法人日本ダルクによると、新潟ダルクも含め全国に62団体88施設ある。
新潟ダルクでは、スタッフは県外のダルクの元入寮者が務め、運営資金は、主に入寮費で賄う。生活費が苦しい人は生活保護費から捻出する。本人が薬物関係者から離れるために、地元から遠い施設を選ぶことも多い。約6年前に県外から新潟ダルクに入寮した60代男性は「クスリがなくても自然体で笑える自分に気づいた」と穏やかに語る。
回復に大きな役割を果たすのが、朝食と夕食後の1日2回のミーティング。これまでの人生や依存に至った経緯などを語り合う。薬物を使った弱さを認め、前向きな人生を目指す。夜は毎日、県内各地に出向き、自助グループの集会を運営しながら思いを共有する。
ただ、スタッフとして残る者を除き、ダルクを出て薬物を使わない生活を続けられるのは約3割だという。断ち切る難しさを理解する田中さんは「自分一人で薬物をやめられないと自覚したときが本当の回復への第一歩。失敗したときこそ、ダルクを思い出してほしい」と呼び掛ける。
■ ■
回復のプロセスは新潟ダルクの中だけでなく、外部との関わりも重要だ。
入寮者は学校で生徒に薬物依存の苦しみを語ったり、依存症者がいる病院や刑務所で「断薬を続ける姿」を見せたりする。それが自らの回復の現状を客観的に見ることにつながる。
田中さんは依存症者を「人間関係をうまく築けず、困ったときに薬物しか頼れなかった人」と表現し、地域貢献の重要性を指摘する。「家族や仲間から見放された人にとって、人に感謝されることは自尊心を高めてくれる」
近所の草刈りなどボランティアを行うことで、地域でも理解の輪は広がる。畑仕事を手伝ってもらった新潟市南区の市民グループ「しなのがわ工房ままや」の西山久子さん(72)は「一生懸命な働きぶりに、手作りのおこわなどをお返しした。応援したい」と感謝した。