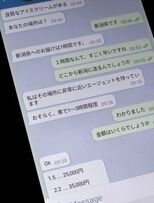【2021/07/07】
「人生が終わる」などと、さまざまな誤解や偏見を持たれがちな薬物依存症。しかし他の依存症と同じく病気であり、回復できることにも変わりはない。当事者や家族、社会はどう向き合うべきか。治療の第一人者で、国立精神・神経医療研究センター(東京)の松本俊彦医師(53)にリモート取材で聞いた。
-どんなメカニズムで薬物依存になるのですか。
「1回使うと依存症になる、快感が脳に刷り込まれるといわれるが、そうではないと示す事実は多い。違法薬物経験者で依存症の診断がつくのは11%程度との国連の報告もある。依存症は薬理学的な作用だけでは説明できない。その本質は苦痛の緩和だ。以前からの悩みや苦しみが薬物で一時的に和らぎ、それが『報酬』となって薬物摂取という行動を学習し、気付くと薬物に振り回されている」
「例えば市販薬や処方薬が分かりやすい。DV被害や借金などに悩み、抗不安薬などで楽になるという対処を続け、依存症になることがある。違法薬物も、しんどい人生を送ってきた人ほど得られる快感が大きいと理解してもいいかもしれない。そもそもの苦痛の緩和度合いが大きいからだ」
-依存症になりやすい人の傾向はありますか。
「性格に独特の偏りがある、意志が弱いという言説は、とっくの昔に否定されている。さまざまな性格の人がいて、健常人とさして変わらない」
「違法薬物に手を出す人は、居場所を見いだせずコミュニティーへの信頼を失う体験をしてきたのではないか。私たちと法務省の共同研究でも、虐待被害などの経験が驚くほど多い。家庭にも学校にも居場所がない中、存在価値を認めてくれる人が薬物を勧めてきたら断れないと思う」
-回復に必要なことは。
「社会における居場所、人とのつながりが必要だ。ただ、実際は地域から排除される傾向がある。要因の一つは薬物が犯罪化されていること。メリットはあるが、依存症の人を孤立させ、回復しにくくするデメリットは大きい。私たちの患者を見ても、逮捕されていない人の方が薬物をやめている率が高い」
-大麻の「使用罪」導入が議論されています。
「大麻が安全とは思わないが、悩む人がますます孤立し回復が阻害される。日本の規制はアルコールやギャンブルには甘いが、薬物には異様な厳しさがある」
-啓発のあり方は。
「『人間やめますか』『ダメ。ゼッタイ。』の啓発や、逮捕された著名人をこきおろすメディアの悪影響は大きい。薬物を使った人はいじめても構わないと言わんばかりの社会だ」
「かつて学校での講演でアンケートをすると、生徒の約1割は『薬物を使いたい人は使えばいい』と答えた。自尊心が低く、飲酒や喫煙、自傷行為などの経験もあった。こうした子に『ダメ、ゼッタイ』と言っても反発を招く。孤立感をどう軽減するか考えなければいけない。さらに今、10代が最も乱用する薬物は市販薬だ。乱用防止教育を抜本的に変える必要がある」
-当事者や家族にアドバイスはありますか。
「不安を含め、正直に言える場所を確保してほしい。自助グループでは決して糾弾されない。精神保健福祉センターで愚痴を聞いてもらうだけで薬物が止まる人もいる。家族が相談し、本人の治療につながることもある。また、家族だけでも幸せになろうという観点も大事だ」
「新潟県内では家族会が行政とも協力するなど、さまざまな活動が行われている。新型コロナウイルス禍で、当事者や家族によるオンラインのミーティングが広まり、地方の人や子育て中のシングルマザーも参加している。一人で悩まないでほしい」
◎松本俊彦(まつもと・としひこ)1967年、神奈川県生まれ。精神科医。佐賀医科大卒。神奈川県立精神医療センターなどを経て、2015年から国立精神・神経医療研究センター薬物依存研究部長。