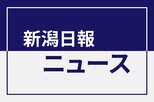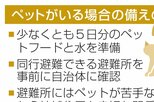◆[解説・液状化マップ]新潟県の地域別概要
地域別の概要は次の通りです。内容は国土交通省北陸地方整備局発行の「新潟県内液状化しやすさマップ」を基にしています。
▶地図はこちらからも確認できます(PDF)
※パソコンの場合はこちらを推奨
【村上地域】村上市街地は一部の造成地をのぞき液状化の可能性が低い。胎内川と荒川に挟まれた地域で、砂丘沿いには危険度3のエリアが広がり、一部に液状化の可能性が高い地域がある。新潟地震の際の履歴も集中している。
JR岩船駅付近から七湊集落にかけては、液状化の可能性がある地域が広がる。
【新発田地域】旧紫雲寺潟に液状化の可能性が高い地域が広がっている。新潟地震の際の履歴だけでなく、古い時代の痕跡も見つかっている。加治川でかつて川が流れていた地帯(旧河道=きゅうかどう)にも多数の履歴がある。
福島潟の周辺や阿賀野市の旧水原町周辺は、広い範囲にわたって液状化する可能性がある。
【新潟地域・全域】信濃川河口付近と通船川(人工河川)沿いに液状化の可能性が高い範囲が広く分布している。この領域は新潟地震の際に液状化した範囲とほぼ重なる。また信濃川、阿賀野川のかつての川の範囲とも一致する。
じゅんさい池の周辺は砂丘地で、標高も高いが地下の水位が高い可能性があり、液状化の可能性がある地域に含まれる。信濃川より西の砂丘地は標高が高く、地下水位が低いため可能性は低い。古町地区は新潟地震では被害がほぼなかったが、新潟地震よりも大きな揺れとなれば液状化する可能性がある。
阿賀野川右岸で可能性が高いのは、かつての河川の蛇行部。西川下流の左岸は地下水位が高く、液状化の可能性が高い。旧黒埼町や小新、小針方面や鳥屋野潟、旧亀田町の周辺は宅地の造成地が広がり、液状化の可能性が高いエリアも広くなっている。大潟・田潟・鎧潟といった旧湖沼(干拓地)は液状化の可能性がある地域となっている。
【燕・三条地域、五泉・加茂・田上方面】信濃川本流や西川、中ノ口川のかつて川だった地帯(旧河道)沿いに液状化の可能性が高い部分が分布している。大河津分水の上流側と下流側はかつての川幅が広く、注意が必要。
大河津分水の分岐点より北側は、燕市から旧巻町にかけて広い範囲で液状化の可能性があるエリアが広がっている。三条・燕・五泉の市街地では宅地造成地の拡大により、液状化する可能性のある範囲が広がっている。
【長岡地域】盛り土造成した宅地が広がる市街地の多くは液状化の可能性がある地域とみなされている。市街地より上流側で、信濃川両岸の段丘上は本来、液状化の可能性がほとんどない地域だが、人工的な要因により液状化の可能性がある地域となっている。
小千谷市街地では著しい液状化の履歴があるものの、その後の復旧作業により要因がなくなったため、可能性が低い地域と判定されている。
【柏崎地域】砂丘の標高が高いなどの要因から、地区全体として液状化の可能性は非常に低い。ただ、砂丘の縁に当たる部分では地下の水位が高く、人工的に手が加えられている可能性があるため、液状化の可能性が高い。市街地は盛り土造成の影響から、液状化の可能性のある範囲が広がる。
【上越地域】高田平野は液状化の要因の少ない地盤の構造となっている。直江津地区を中心に宅地や工場の盛り土造成地が広範囲に広がり、液状化の可能性のある範囲となっている。砂丘の縁に当たる部分でも地下水位が高く、液状化の可能性がある。
【糸魚川地域】姫川の流域は液状化の可能性がほとんどない。
※地図は北陸地方整備局、地盤工学会北陸支部が作成し2012年に公表した「新潟県内液状化しやすさマップ」のものです
▼合わせて読みたい
× ×
※各種相談窓口などの情報をまとめて公開しています。