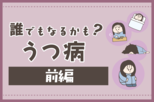津波対策を理由に運転差し止めを命じた判決は初めてだ。電力会社が安全性を立証できないのに再稼働などできるはずがない。
事故が起きれば生命や身体の安全が脅かされるとして、北海道電力泊原発1~3号機の周辺住民が運転差し止めと廃炉を求めた訴訟で札幌地裁は、運転差し止めを命じる判決を下した。
判決は、「津波に対する安全性の基準を満たしていない」とし、事故が起きた場合、周辺30キロ以内の住民に人権侵害の恐れがあるなどと指摘した。
既存の防潮堤の地盤に液状化が生じる可能性がないことを資料によって裏付けていない点や、新たに建設される防潮堤の構造も決まっていないことを理由に挙げた。
東日本大震災で巨大津波に襲われた東京電力福島第1原発は全電源を喪失、炉心溶融が起きた。北海道電は提訴から10年以上経過したのに、その教訓を真摯(しんし)に受け止めず対策に生かしていなかった。
原発を巡る訴訟では、科学的知見や資料を持つ電力会社が立証責任を尽くさない場合は「安全性を欠く」と判断する枠組みがある。
このため「泊原発に想定される津波を防ぐ施設は存在しない」と結論付けた。
判決では安全性を積極的に立証しようとしない北海道電の姿勢も批判された。
北海道電は原子力規制委員会が適合性の審査中であることを理由にした。しかし、地裁は審査終了時期が見通せないと指摘し、審査に時間を要していること自体を「泊原発が抱える問題の多さをうかがわせる」事情と捉えた。
泊原発は2013年に再稼働を申請した。同時期に申請した九州電力川内1、2号機などが再稼働しているのと比べても、泊原発の審査の長さは際立っている。
北海道電の説明していた地層が規制委の調査で見つからず審査が振り出しに戻ったこともある。
これで安全な稼働ができると言えるのか。原発事業者としての資質を疑わざるを得ない。
昨年10月に閣議決定されたエネルギー基本計画は、原発の電源構成比を30年度に「20~22%」としているが、20年度は3・9%にとどまる。ウクライナ危機に伴う燃料高騰を踏まえ、岸田文雄首相は原発再稼働に積極的だが、前のめりすぎるのではないか。
本県に立地する東電柏崎刈羽原発では、核物質防護体制の不備などが相次いでいる。安全性に対する姿勢に首をかしげざるを得ないい事案が頻発している。
柏崎刈羽原発の運転差し止め訴訟でも、原告側は防潮堤の液状化や地震動の評価手法などに問題があると主張している。
安全性を追求し、科学的根拠に基づき迅速に説明責任を果たさねばならない立場であると、原発事業者は肝に銘じてもらいたい。