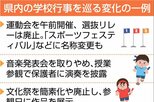折り曲げた足を両手で支えて座る。誰が名付けたか「体育座り」。学校の授業や集会でおなじみの座り方が体に悪影響なのではないかとの指摘が各地で上がっている。新潟日報の「もっとあなたに特別報道班」(もあ特)に寄せられた意見でも否定的な声が目立つ。日本独特とされる体育座り、あなたはどう考えますか?(報道部・黒島亮)
「体育座りを長時間続けるのは体によくありません」
こう話すのは、新潟リハビリテーション大(村上市)副学長の押木利英子教授(73)=小児理学療法=だ。
体育座りは、背中を丸めて手で足を囲む形になる。この姿勢を続けると呼吸が浅くなる上、腰痛や肩こりなどにつながるという。
押木さんは「どの座り方が楽かは個人差がある。座り方を柔軟に、自由に変えられるようにするといい」と話す。
いすに座る形式についても「同じ姿勢を強制しては体育座りと一緒」。体への負担を減らすため、クッションや座布団などを使うことも提案する。
もあ特会員からは「高校3年生の娘が座骨神経痛で、体育座りをするのがつらい」という切実な声のほか、床やグラウンドに直接座ることによる衛生面への不安も寄せられた。
自らの子どものころを振り返り「体育座りでお尻の当たる部分が痛いので、手をついたり姿勢を崩したりすると先生に叱られた」との声もあった。
▽座らせ方は「各校の判断」
海外に家族のいるもあ特会員によると、体育座りは日本以外ではあまりないユニークな座り方のようだ。旧文部省が1965年に参考資料として公表した手引きに体育座りが紹介されており、そのころから全国に広がったようだ。
ただ、国は体育座りを推奨しているわけではなく「あくまで座り方の一つ」(スポーツ庁政策課)との位置付けだ。
県と新潟市の教育委員会に取材すると、体育や集会での子どもの座らせ方は「各学校での判断」という。
県内のある小学校の校長は「新型コロナウイルス対策などの課題がある中、座り方の見直しはできていない」と現状を説明。「体育座りにどのような問題が指摘されているかをキャッチし、対応したい」と話す。
▽同じ姿勢は負担、正座でも
押木さんは「同じ姿勢を長時間続ければ、体育座りに限らず体に悪影響を及ぼす」とも指摘。「座り方や姿勢を適宜変えることで、股関節や体のバランス、筋肉などへの負担が減る」と説明する。
同じ姿勢が体に負担がかかるというのなら、日本の文化に根付いている正座はどうなのか? 押木さんに聞くと「同じ姿勢を続けることによるデメリットは正座も同じ」との答えが返ってきた。エコノミークラス症候群などと同様の問題といえるという。
米国在住の弟がいるというもあ特会員は、弟の話として「『あぐらが多い』とのことだった。寝そべらない限り好きなように座らせておけばいい」との意見を寄せた。
ことしの運動会でも体育座りをしている子どもの姿が見られた。子どもの負担を減らす座り方について、議論を深めてみませんか。