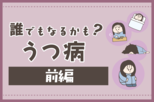未曽有の原発事故を防げなかった旧経営陣の責任を司法が初めて認めた。会社に損害を与えたとして役員個人に巨額賠償の支払いを命じた重みを、関係者は真摯(しんし)に受け止めなくてはいけない。
東京電力福島第1原発事故を巡り、総額22兆円を東電に賠償するよう求めた株主代表訴訟で、東京地裁は旧経営陣4人に計13兆3210億円の支払いを命じた。
賠償額は国内の民事訴訟で最高額とみられる。廃炉や被災者への賠償金、除染など東電側が負担する費用から算定した。
判決は原子力事業者トップの責任を明確に認めたものだ。極めて甚大な被害が伴う原発事故を起こせば、個人でも賠償を科せられるほどの責任の重さを示した。
原発の過酷事故について、判決は「わが国そのものの崩壊にもつながりかねない」と指摘した。事業者は絶対に事故を起こさないと肝に銘じなくてはいけない。
裁判の争点は、政府機関が公表した地震予測「長期評価」に基づき、東電は巨大津波を予見できたか、経営陣が対策を命じていれば事故を回避できたか、だった。
判決は、長期評価について、地震や津波の専門家による適切な議論を経て承認され、相応の科学的信頼性が認められると指摘、津波は予見できたとした。
その上で、原子力部門幹部の元副社長が長期評価の信頼性を不明とし、対応を放置したことを「先送りと評価すべきで、許されない」と批判した。元会長と元社長はこうした判断に不合理な点がないか確認する義務を怠ったとした。
事故との因果関係について、原発の主要建屋や重要機器室に浸水対策工事を実施していれば、避けられた可能性があったとした。
原子力損害賠償法は過失の有無にかかわらず、事業者が事故の賠償責任を負うと規定している。このため被災者が東電を訴えた民事訴訟では、東電内部での責任の所在は主な争点にならなかった。
今回の判決は、担当部署が本格的な対策を進言しても聞き入れないなど経営陣の姿勢も指弾し、「安全意識や責任感が根本的に欠如していた」と非難した。内部の責任に言及した点は注目できる。
裁判長は一連の原発関連裁判で初めて原発敷地内を視察、質問も投げかけた。提訴から10年余り、丹念な審理だったと言えよう。
6月の避難者訴訟最高裁判決では、長期評価の信頼性や津波予見性は判断されなかった。同じ旧経営陣のうち3人が被告となった強制起訴裁判の一審判決は、長期評価の信頼性を認めなかった。
ほぼ同じ争点で判断が割れるのは、それだけ津波対策の評価が難しいからだろう。
8月には原発避難者らによる新潟訴訟の控訴審が始まる。過酷事故を起こした東電は原告の声にしっかり向き合わねばならない。