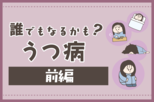手続きは一歩進んでも、風評被害を懸念する漁業者らの反対は依然強い。地元自治体の了解も得られていない。
政府や東京電力は地元や関係者の声に耳を傾け、真摯(しんし)に対応しなければならない。
東電福島第1原発の処理水海洋放出計画を審査していた原子力規制委員会は、「安全性に問題はない」として計画を認可した。
計画では処理水に含まれる放射性物質トリチウムの濃度を国の基準の40分の1未満になるまで大量の海水で薄め、海底トンネルを通して沖合約1キロで放出する。2023年春ごろの開始を目指す。
11年の事故で溶け落ちた核燃料への注水や、建屋に流れ込む地下水、雨水で発生した大量の汚染水を東電は浄化し、処理水として敷地内のタンクに保管している。
タンクは当初、23年春ごろには満杯になる見通しだった。増設は廃炉作業に支障を来すとして政府は21年4月、処理水の海洋放出を決めた。その後、タンク満杯の時期は23年秋ごろに延びたが、東電は放出時期を変えていない。
認可を受け全国漁業協同組合連合会(全漁連)は、「全国の国民・漁業者の理解を得られておらず、断固反対であることはいささかも変わらない」と声明を出した。
政府は4月に全漁連の申し入れに対し、漁業を継続するための「超大型の基金創設」や、風評被害に国が責任を持つなどと回答したが、溝は埋まっていない。
政府と東電は「関係者の理解なしにはいかなる処理水の処分もしない」と約束していたはずだ。地元への丁寧な説明は不可欠だ。
一方で東電は、認可の対象外の所で、工事を既に進めている。放出前の処理水を一時的にためる立て坑などだ。
これでは不信を招くのではないだろうか。地元漁業者からは、「放出ありきで設備の準備が進んでいる」と不満の声が出ている。東電の前のめりの姿勢に首をかしげざるを得ない。
トリチウムが環境に蓄積することによる生態系への影響や、内部被ばくを懸念する見方もある。
11年の事故以降、日本産食品の輸入規制を続けてきた国・地域の間では解除の動きもあるが、海洋放出により再び規制に転じる国が増えはしないか気に掛かる。
認可に伴い、韓国は憂慮を日本側に伝えた。中国は環境への影響などを巡り多くの疑問が残っているとし、「断固として反対だ」と反発している。
福島県と第1原発が立地する双葉、大熊両町は近く、計画の是非を判断するとみられるが、来年春までに漁業者らの理解を得られるかは不透明だ。
政府や東電は、スケジュールありきで計画を進めるのではなく、関係者としっかりと向き合ってもらいたい。