テロ対策上の重大な不備が相次いだ東京電力柏崎刈羽原発(新潟県)について原子力規制委員会は、対策に改善がみられるとして、東電に核燃料の移動を禁じた是正措置命令を12月27日に解除した。形態が多様で常に警戒が必要なテロに加え、ロシアのウクライナ侵攻で原発への武力攻撃も現実となった。原発の危機管理の在り方を専門家はどうみるか。初回はテロ対策について防衛大国際関係学科の宮坂直史教授(60)に聞いた。(2回続きの1)
-原発への武力攻撃、テロに対する政府の備えの現状をどうみていますか。
「原発に限らず、武力攻撃やテロから住民の安全をどう確保するのかは、2004年に成立した国民保護法に基づく国民保護行政の分野となる。だが、原発が攻撃対象となり、占拠されることを想定した訓練は全国的に少ない。手が回っていないのが現状だ」
-東京電力柏崎刈羽原発では、テロ対策上の重大な不備が問題になりました。
「他人のIDを使った不正侵入は論外だ。原子力規制庁から原発事業者向けの教育用ビデオ『核セキュリティー文化』の制作を受託した際は、侵入検知などの機材が壊れたまま放置し、大事に至った海外の事例を示した」
-まさに柏崎刈羽のことを指摘した内容ですね。
「原発で何か起きれば、住民に大きなリスクをもたらす。原発や核施設の安全を高めるためには、経営層を含め、全従業員のセキュリティー意識向上が国際的に求められている」
-柏崎刈羽原発での一連の事案では、内部の人間が安全を脅かす事態への認識不足も課題に挙がりました。
「原発では出入り業者らを含め多様な立場の人が、それぞれの職務、思惑で動いている。海外の原発では、労働環境への不満から従業員が問題を起こした例がある。外部からの攻撃よりも内部脅威が懸念されている」
-原発で働く人の身元や思想の調査は必要ですか。
「プライベートまでチェックせざるを得ない。身近なところに脅威があるかもしれないと考えるならば、機械頼みのセキュリティーではいけない」
-武力攻撃やテロで原発が攻撃された場合、住民は避難できますか。
「状況次第だ。情報がなく、どこに武装集団がいるか分からないような状況で外に出てはいけない」
-2007年の国民保護訓練から、横須賀市(神奈川県)の訓練を監修しています。
「横須賀市は年1回、市独自に国民保護の訓練をしている。17年度は某国から弾道ミサイルが飛来し、市上空で核爆発が起きたという想定で、どう住民を避難させるか訓練した。核爆発があっても生存者は多いと考えられる。厳しい想定で行うと、計画通りにできないことが多い」
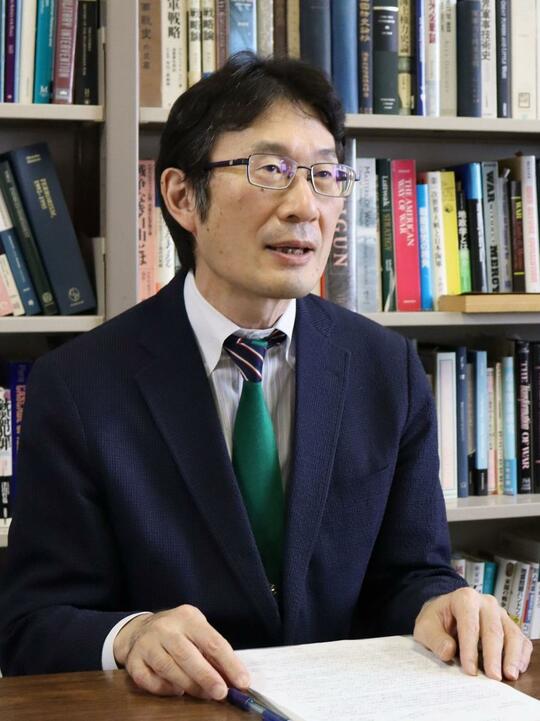
宮坂直史教授
「例えば10項目の論点を設定し、そのうち1、2項目でも何ができたのか、逆に何ができなかったのかを検証する。関係機関がそれらを認識しておくことが大事だ」
-訓練で核テロを想定した理由は。
「横須賀基地を拠点とする米海軍第7艦隊の存在だ。北朝鮮は横須賀を攻撃対象だと公言したことがある。米軍基地を攻撃しなければ自らが危ないという考えだ。当然、最悪の有事に備えなくてはならない」
-横須賀市には核燃料の加工会社もあります。
「万が一の事故時に爆発すると、放射性物質が外に出る。住宅街も近いので意識して訓練している。第7艦隊の空母、潜水艦などは原子力艦船だ。基地での放射能漏れを想定し、横須賀港から半径3キロ以内の住民を対象に、毎年町内会が持ち回りで訓練に参加する」
「住民の中で、放射線監視装置(モニタリングポスト)の数値が何を意味するか、正確に理解している人は少ない。きっかけが武力攻撃でも事故でも、住民が核災害や放射線関連の知識を持っておくことが最も重要だ」
◎宮坂直史(みやさか・なおふみ)1963年。東京都生まれ。専門は国際政治、安全保障、テロリズム研究。慶大卒。日本郵船に3年勤務、早大院博士課程中退。1999年に防衛大助教授、2008年10月に防衛大教授。近著に「テロリズム研究の最前線」(法律文化社)、訳書に「テロリズム」(岩波書店)など著書、論文多数。内閣官房の訓練評価委員長を務める。
× ×














