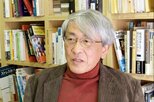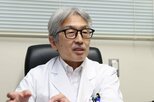赤や白、黒、金などさまざまな色彩の模様が入った錦鯉は、優雅な姿から「泳ぐ宝石」とも呼ばれる。2017年には新潟県の鑑賞魚に指定された。現在では国内にとどまらず海外でも広く人気を集め、発祥の地である長岡市や小千谷市で開かれる品評会には、国内外から多くの愛好家が訪れる。人々を引き付ける錦鯉。種類や鑑賞方法、歴史、生産の手法について専門家に聞き、魅力に迫った。
(長岡支社・佐藤薫)
品種は140種超!品評会で重視されるポイントは?
専門家に聞く“掛け合わせの妙”
泳ぐ宝石と一口に言っても、全日本錦鯉振興会によると錦鯉の品種は140種を超えるといわれる。種類はどう分けられ、評価や鑑賞の際には何がポイントになるのだろうか。淡水魚の養殖技術や生態を研究している県の内水面水産試験場(長岡市)の場長、佐藤将(しょう)さん(57)に教えてもらった。
錦鯉は江戸時代、突然変異で色鮮やかになった食用のマゴイが起源とされ、それらが掛け合わされることで種類が増えてきた。近年は海外との取引が増え、品質保証が重要になってきたことから2022年、主な21種について初めて日本農林規格(JAS)に定義が明文化された。
代表的なものが「紅白」「大正三色(たいしょうさんしょく)」「昭和三色(しょうわさんしょく)」の3種で「御三家」とされる。大正三色は作出した大正期に「三毛(さんけ)」とも呼ばれたため、今でも三色と書いて「さんけ」と読むことがある。同試験場によると、現在の呼称はJASなどで「さんしょく」で統一されている。
「紅白」は読んで字のごとく白地に赤い模様が付いている。江戸時代には既に前身となる鯉が生まれていたという古い品種だ。「大正三色」は白地に赤の模様に加え、背中に黒の模様が入る。「昭和三色」は黒地に白や赤の模様が入っており、黒く染まった「墨」と呼ばれる部分が腹から背中にかけて巻いている。
このほか黒ともう1色で構成する「写りもの」、青みがかった網目模様が付いた「浅黄(あさぎ)」、全身が光沢を持った金色の「山吹(やまぶき)黄金(おうごん)」などが主な種類だ。

新潟県は錦鯉生産量が全国で最も多く、全体の約4割を占める。生産者が多い上に業者ごとに得意とする品種が違うといい、佐藤さんは「産地の山を一回りすればさまざまな品種を手に入れられるのが、新潟県の錦鯉養殖の特長だ」と話す。
県が開発し、14年に発表した品種「黄白(きじろ)」は、白地に黄色の模様が入る。開発に携わった佐藤さんによると、1997年ごろに試験場で偶然、レモン色をした個体が生まれた。改良を進め、安定して生み出せるようになった。「御三家のようなトップの品種にはならないとは思うが、彩りの一つになればと作った」と胸を張る。
錦鯉の美しさを競う品評会では、上から見た美しさが評価される。まず着目されるのが体形だ。ふっくらした姿が好まれ、評点の50%を占めるともいわれる。体形に次いで色の質、模様と続く。
錦鯉は大きいもので体長1メートルにもなるが、小型も養殖されており、自宅の水槽などで手軽に飼うことができる。比較的病気に強く丈夫なため、飼いやすい生き物だとされる。佐藤さんは「庭に池があるようなお金持ちの趣味というイメージを持つ人もいるが、数百円から買えるものもある。さまざまに楽しんでもらいたい」と話している。
◆おや?食用のマゴイが…誕生と進化の歴史に迫る
錦鯉はいつ、どのようにして誕生したのか。
県水産試験場が1931年にまとめた資料などによると、約200年前の江戸時代後期、現在の長岡市山古志地域や小千谷市にまたがる地域「二十村郷(にじゅうむらごう)」で、住民が食用に育てていたマゴイが突然変異で緋(ひ)色や白色になった。それらを掛け合わせるなど試行錯誤を重ねて、赤白の模様が入った鯉を生み出したのが起源だという。
当初は錦鯉という名前はなく「色鯉」「模様鯉」などと呼ばれていた。明治に入ると高値で売買されるようになり、1875(明治8)年ごろには、あまりに投機的な事業だとして県が養殖を禁じた。それでも生産者らは地場産業としての重要性を訴え、間もなく禁止は解かれた。
全国に広まったきっかけが、1914(大正3)年に東京で開かれた「東京大正博覧会」だった。生産者が「変わり鯉」として出品し、注目を集めた。39(昭和14)年には、米国サンフランシスコで開催された万博に出品され、海外にも知られ始めた。
錦鯉の名称は、その美しさに感嘆した大正期の県水産主任官・阿部圭さんが呼び始めたとされる。戦後にかけて呼び名が定着していくとともに、さまざまな新品種が登場。世界中にファンを持つようになっていった。
県内水面水産試験場の場長、佐藤将さんは「山奥の農村のことで書物も残っていないため、詳しい起源は分からないが、文化として育て上げたのは二十村郷の人々で間違いない」と断定する。
海外でも人気沸騰!輸出額は20年間で5倍近くに
「登竜門」の故事にあやかり…アジアでは縁起物に
10月下旬、長岡市山古志地域で開かれた品評会には国内外のファンやバイヤーらが集まり、錦鯉が悠々と泳ぐ水槽を熱心に見て回った。米国やインドネシア、タイなど14カ国のオーナーが自慢の鯉を出品。実に約4割が海外からで、全体総合優勝に輝いたのは米国の愛好家が所有する86センチの「大正三色」だった。
海外での錦鯉人気は年々高まっている。貿易統計によると、2023年の錦鯉の輸出額は66億9500万円に達した。03年の13億8300万円に比べ、20年で5倍近くまで伸びた。
輸出先の国・地域別で割合をみると、23年は米国が15・99%を占めてトップ。中国が15・50%とほぼ並んだ。以下はインドネシア(10・05%)、香港(9・82%)などが続いた。

小千谷市の大日養鯉場社長で、全日本錦鯉振興会理事長の間野太さん(51)は「芸術的な姿や縄張り争いをしない平和な性格、人懐っこさが受けていると思う」と分析する。
また、例えば中国には鯉が急流を上って竜になるという「登竜門」の故事があり、鯉は立身出世の象徴ともされているため、アジアでは縁起物としての人気も高い。
振興会は、あの手この手で普及に努める。海外ではバイヤー向けに品種説明のセミナーなどを実施。22年には県などとの実行委員会として新潟市で「世界錦鯉サミット」を開き、集まった21カ国の駐日大使や業者を楽しませた。
国内向けには、錦鯉を関東地方で無料配布したり、...