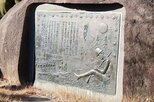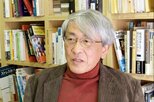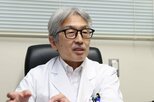ロボットで災害救助や機器の点検作業といった課題をこなす技術を競ったり、ゲーム競技の得点を争ったりする「ロボコン」は、設計から製作、操縦まで、チームで一糸乱れぬ連携が必須だ。長岡市では、長岡技術科学大学や長岡工業高専の学生らが複数のロボコンチームをつくり、活発に活動している。10月には、技科大大学院生のチームが世界大会の1部門で初優勝した。ひたむきに取り組む学生や、それを支える地元企業、イノベーション(技術革新)を担う人材を育てる試みに迫った。
(長岡支社・渡辺賢吉)
災害救助ロボット開発に心血注ぎ…高難度の“任務”こなし栄冠
長岡技科大大学院生7人でつくる「NuTech-R」
四つのローラーが付いた足回りの上にロボットアームを装着した災害救助ロボットが、遠隔操作でスムーズに動き回る。ロボットアームががれきの撤去やバルブの閉栓をし、アームに装着したカメラが周辺の様子に目を光らせる。
新技術やユニークなアイデアを披露する「ワールドロボットサミット(WRS)」の一環として、世界大会「過酷環境F-REIチャレンジ」(福島国際研究教育機構主催)が10月10〜12日、福島県で開かれた。長岡技科大大学院の学生7人でつくるロボット開発チーム「NuTech-R(ニューテックアール)」は、「プラント災害チャレンジ」の部門で念願の頂点に立った。
大会ではインドやスイス、オーストリアの海外勢を含む9大学のチームを退けた。チームリーダーの長谷川晴基さん(24)は「ロボットが高いパフォーマンスを発揮できて、本当に良かった」と、ほっとした表情を見せた。
ニューテックアールは、中越地震を契機として技科大と長岡市内の製造業者を中心に結成したロボット研究会「Nexis-R(ネクシスアール)」のノウハウと技術を継承し、学生自身で開発を進めるチームだ。ロボットは英語で探索を意味する「Seek」と名付け、2024年11月から開発してきた。
予選と決勝で与えられたミッションは六つだった。がれき撤去やトンネル内の多重事故の探索など、災害や事故を想定した課題に加え、圧力計の読み取りやタンク壁面の老朽化の診断といった日常点検に関する課題もあった。ロボットの汎用(はんよう)性が求められ、難易度も高い。

多重事故の現場では、車の下の燃料漏れをアームの先端に付けたカメラで確認し、周辺のがれきを除去した。車内の負傷者を確認するため、ドアを開けるミッションにも挑戦。完全には開けられなかったものの、配信動画で解説を務めた専門家は「ドアの開閉は難しいが、かなり良いトライをしている。今まで、ここまでやったチームはなかったのではないか」と評価した。
ロボット「Seek」は優れた機動性と操作性を十分に発揮し、他のミッションも着実にこなした。設計と製作を主に担った鳥羽広葉さん(23)は「大会の直前にアームの強度を増して、間に合わせた。社会実装を意識し、研究結果を課題解決につなげる取り組みはやりがいがある」と強調する。

次の目標は、26年7月に韓国で開かれる世界大会だ。長谷川さんは「開発を通して、社会に役立つロボットを作り、長岡の技術力を発信したい」と意欲を見せた。
◆悪天候でも機動性損なわず…快挙支えた地元企業の技術
ニューテックアールのロボット「Seek」には、...