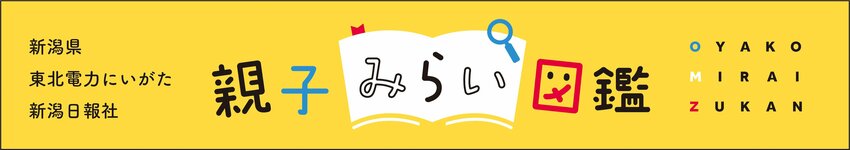子育てに王道はない。手探りを繰り返す毎日が、やがてわが家の子育てになっていく。パパたちが歩んできた「パパの細道」をのぞかせてもらう対談企画。3rdシーズンのテーマは長いようで短い「子どもと過ごす時間」。今回はどんな細道が待っているだろうか。
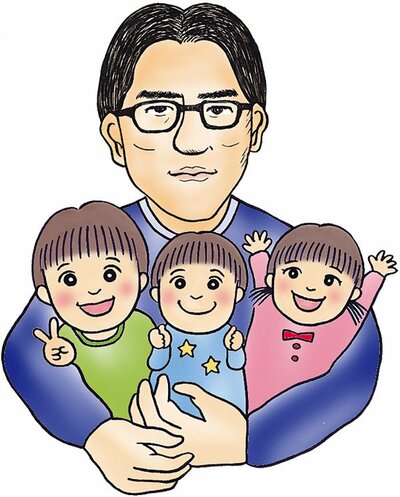
横田 孝優
コピーライター。11歳・9歳の双子の3児のパパ。企業理念の開発やホームページの文章制作などを手がけるほか、新潟日報asshにて2024年1月まで子育てコラムを連載。 https://ztdn.net/

坂田 匠さん
建築金物の製造・販売などを展開する長岡市のサカタ製作所代表取締役。2018年に男性育休100%を達成し、現在まで継続中。その他にも残業時間ゼロや製造業でのテレワーク推進など、革新的な働き方を実現している。
まず、残業をゼロにした
横田 パパの細道3rdシーズンは、「子どもと過ごす時間」をテーマに、これまで4人のパパと対談を重ねてきました。子どもとの時間を充実させるためには、多くのパパにとって仕事との関係は切り離せないと思います。サカタ製作所では「残業ゼロ」「男性の育休100%」を実現されていますが、取り組みについて具体的に教えていただけますでしょうか。
坂田 まず、残業をゼロにした理由ですが、一番の根底には「社員の所得を向上させること」がありました。今回のテーマである「子育て」には、後からつながった形です。
当社は東京や大阪にも拠点がありますが、新潟の社員と東京・大阪の社員の間には所得格差がありました。新潟から東京・大阪に転勤する場合は、地域手当が上乗せになるため問題はありませんが、逆に東京・大阪の社員を新潟に赴任させた場合、給与を下げるわけにはいかないため、社内で所得格差が生じていたのです。
また、東京・大阪の社員の給与が十分かといえば、まだ足りないと感じていました。そうなると、新潟の社員の給与もさらに上げる必要があります。この「所得格差」を解消することが、残業ゼロを導入する大きなきっかけでした。
所得を向上させるために給与を上げることになりますが、残業には1.25倍以上の割増賃金が発生し、経営的には時間あたりのコストが上がります。また、社員にとっては残業をしたほうが経済的なメリットがあるため、結果的に非効率な働き方が生まれてしまうのです。
本来、給与は仕事の価値に対して支払われるべきですが、実際には時間に対して支払われているのが現状です。つまり、付加価値が生み出されていなくても、長時間働くことで収入が増えるという仕組みになってしまっています。これは企業全体の生産性を低下させる要因となるため、何とかして残業をなくしたいと考えていました。
しかし、実際にはなかなか実現できず、何年もその状態が続いていました。そんな時に株式会社ワーク・ライフバランス代表の小室淑恵(よしえ)さんに全社員の集会で講演をしていただきました。「残業がいかに生活や仕事にとって悪影響を及ぼすか」という内容で、その講演を聞いて「これはチャンスだ」と思い立ち、急遽「残業ゼロ」を宣言したんです。

残業時間ゼロや製造業でありながらテレワークを推進するなど、革新的な働き方に取り組んできた同社
育休復帰と人間的成長
横田 なるほど。まず残業ゼロのきっかけがあったんですね。
坂田 この決断によって、社内で抱えていたさまざまな問題が解決しました。その一つが「男性の育休」です。実は私自身、当初は「男性も育休を取れるの?」と驚いたのですが、「取れるなら取ればいいじゃん」と育休の取得を推奨するようになりました。
残業がなくなり、業務の属人化も解消されました。以前は「その人にしかできない仕事」が多く存在していましたが、今では誰でもフォローできる体制が整いました。その結果、誰かが長期間育休を取っても、ほとんど問題が生じなくなったのです。
横田 大きな改革だったわけですが、社内からの反発はありませんでしたか?
坂田 はい、ありました。しかし、小室さんの講演を社員全員が聞いたことで、「なぜ残業が良くないのか」という認識は共有できた。それが大きかったですね。
もし私一人が講演を聞いて「残業をなくそう!」と言っても、社長が突然おかしいことを言い出したと思われてしまう。でも、全社員が講演を聞いて「これは良い話だ」と思えたことが、スムーズな導入につながったのだと思います。
横田 社員の皆さんが前向きに取り組めたのは、その共通認識があったからなのですね。
坂田 育休を取得した社員たちは、育休前とは見違えるほど変わって帰ってきます。まるで精神修行をしてきたかのように穏やかになって、良い父・良い夫の顔になって戻ってくるんです。
家事や育児の大変さを身にしみて実感するようになる。同僚に対しては育休を取らせてもらったことへの感謝も生まれる。その結果、職場に戻ってきた時には、より協力的で、感謝の気持ちを持った人間になっています。表情も父親らしい責任感あふれるキリっとした感じに変わっている気がします(笑)。

産休・育休を終えて復帰した社員たちは、一人として例外なくみんなきらきらした良い表情になって戻ってくるのだそう
横田 会社として、子育て中の社員へのサポートは何かされていますか?
坂田 男性社員が妻の妊娠を報告すると、上司や役員を交えて育休取得に向けた面談をします。総務からは、育休・短時間勤務などの制度を説明する機会を作りました。引き継ぎも、業務の見直しや無駄な仕事を削減するチャンスと捉えるなど、育休を推進する仕組みを作りました。
収入面についても、給付金や補助金などを含めた給与シミュレーションを作り、不安を取り除きます。復職後も、元の職場で同じ業務に戻ることを徹底しています。部下の育休取得に貢献した管理職も表彰するようにし、「休めない雰囲気」を一つずつ打ち破っていきました。そのため、育休を取得する社員には「育休から戻ったら自分の居場所がなくなるのでは?」という心配もないようです。
横田 復帰後の社員さんの活躍を、周りの皆さんが見ているのも理由の一つでしょうね。
坂田 育休から戻った社員たちは、みんなリフレッシュしたような顔をして帰ってきます。家庭での大変さを経験したはずなのに、むしろ前向きな雰囲気になっていますね。
仕事を逃げ道にしない
横田 やっぱり最初が肝心で、最初から子育てに積極的に関わっていれば、パパもママと一緒に歩んでいける。オムツ替えやお風呂に入れるといったことも自然に習得できますよね。
坂田 仕事を逃げ道にしないことが大切だと思います。正直、私自身がそうでした。子育てにおいては落第ですね。当時は、私も世間も、子育ては女性がするものと考えていましたし、男性はちょっと手伝うだけで「役目を果たした」と天下を取ったような気持ちになれました。お皿を片付けたり、オムツを替えたりするだけで、まるで「育児と家事の中心は俺だ」と錯覚していました。「しかも仕事も頑張っているぞ」と胸を張っていた。でも、それは大きな勘違いだったと、後々になって気付いたんです。
横田 男性育休については、少なからずご自身の反省も込められているということでしょうか。
坂田 結果的にそうなったという感じです。

育休中の社員の子育ての様子。同社では数カ月~1年単位で育休を取得する人が多いという
(後編に続きます)