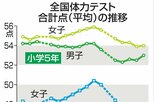新潟市東区の阿賀野川河口近くの左岸堤防で、県と市の準絶滅危惧種に指定されているカニ2種類と巣穴が見つかった。巣穴は直径数センチ、深さは1メートルに達し、堤防の安全性が懸念されるとして、管理する北陸地方整備局阿賀野川河川事務所が対策工事に着手。作業に先立ち、新潟明訓高校(江南区)生物部による、カニの「引っ越し作戦」が展開された。
見つかったのはクロベンケイガニとアカテガニ。いずれも体長4センチほどで、前者は体が黒っぽく足に硬い毛が生えており、後者は赤いハサミが特徴。近年、環境の変化により個体数が減少している。県内では阿賀野川や信濃川付近に生息し、河口近くの地面に掘った穴にすむ。

阿賀野川河川事務所によると、下山ポンプ場排水樋門前の堤防では、大雨時にカニの巣穴から堤防内の土砂が流出する被害が確認されていた。堤防の安全性とカニの生育環境を確保するため、堤防にある巣穴をいったん埋めてプラスチック製ネットで覆い、盛り土をしてカニの新たなすみかにすることにした。
工事中のカニの一時預かりを依頼された新潟明訓高校の生物部が現地を観察したところ、周辺には170個以上の巣穴があった。部員13人が9月、餌を入れたプラスチック製カップを堤防に埋め、約170匹を捕獲した。


ポンプ場付近のカニはここ2年ほどで急増したという。市水族館マリンピア日本海(中央区)の野村卓之館長は「太陽光で温められた排水路の熱が堤防ののり面に伝わり、カニの生育に適した環境となったのではないか」と推測した。

生物部部長で2年の生徒(16)は「人間の安全も大事だが、カニも無事に保護できて良かった。部員で協力して大切に育てたい」と話した。カニは部室で管理し、工事が終わる10月中旬以降、元の場所に戻す予定だ。...
残り125文字(全文:864文字)