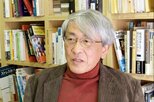「ウナギは夏よりも冬の方がおいしいんです」。取材の始まりは、新潟県阿賀野市のウナギ養殖業者から聞いたこの一言だった。ウナギは夏の「土用の丑(うし)の日」に食べる人が多く、報道や宣伝で夏に見かけることが多いので、旬は夏だと思い込んでいた。
新潟県内の料理人に真相を尋ねたところ、ウナギもブリなどと同じように、寒い冬を越すため、体内に脂肪を蓄える。故に、夏より脂ののりがよく、おいしく感じる人が多いのだという。ただし、これが定説となっているのは、自然界で育つ天然物の話だ。
今はウナギ専門の料理店であっても、取り扱うのはほとんどが養殖物。年間を通じてほぼ一定の水温で育つため、「夏と冬でそんなに変わらない」との声もある。しかし、取材した熟練の料理人たちは「養殖物も冬の方が脂がのっている」と断言した。
そもそも、なぜ多くの日本人は夏の土用の丑の日にウナギを食べるのか。諸説あってはっきりしないが、江戸時代の学者、平賀源内に由来する説が一般に知られている。
それによると、夏にウナギが売れなくて悩む店があった。平賀が「丑の日に『う』が付く物を食べると夏負けしない」との伝承をヒントに、「本日、土用の丑」と店の看板に書いたところ、繁盛したため広まったという。
夏の暑さがウナギの食欲を誘う面はあるだろうが、夏の食べ物と決めつけるのはもったいない気がする。冬ならではのウナギの魅力を探った。...
残り3218文字(全文:3809文字)