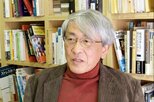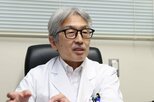花を飾りたい、あの人に花を贈りたい。そんな時は、花屋だろう。色とりどりの花々、中には遠い国から空輸された珍しい品種もあり、さながら万国博覧会の様相だ。一方で「店舗を持たない花屋」がある。自宅やアトリエで、オーダーに応じた花束を作ったり、花材とともに飲食店などへ出かけて生け込んだり。今回、紹介する2人は、そんな働き方だけでなく、使う花材に特徴がある。野に咲く草花や木々、畑で育てた草花。彼女たちの緑と花のあしらいは、普段暮らしているところの風景や足元に、改めて目を向けさせてくれる。
(撮影はフリーカメラマン・内藤雅子)
自然の素材を自然体で生ける…野に咲く草花で映す「里山」
森田春薫さん
新潟県出雲崎の古い町屋を改装した料理店「たわい」。「今回は、この棚を緑多めにしたいという依頼があったので、いろいろ集めてきました」と、森田春薫(はるか)さん(52)は花を生け込んだ。天井まで届く古い棚、その棚板一枚一枚に、器に挿した緑や花を置いていく。ヤマアジサイ、ギボウシ(ウルイ)、ガマズミ、ツルニチニチソウ、バイカオウレン、ヒメコバンソウ…。すべて、弥彦にある森田さんの自宅や竹林のそばで取ってきたものたちだ。
花屋で計25年間、働いた。小さな頃から作ることが好きで「植物も好きだった」。住宅会社勤務を経て生花店に就職。ただ、フラワーアレンジの依頼が少なく、活路を求めてコンテストに応募。入賞者を多く出している花屋に、縁あって転職した。プレゼント、お祝い、結婚式、葬式。日々、要望に応じて切り花をアレンジし、3年後、新潟市内の新店舗の立ち上げに店長として携わった。
区切りを付けたくて5年前に退職。辞めた時は「家のことをやりつつ畑でも」と思っていたが、程なくしてまた、植物に関わることになった。
家の近くにできた飲食店でアルバイトを始めると、前職を知っていたスタッフから店内装飾を頼まれた。「食前茶や料理に野草を使う店だったので、それなら、花材も近くにあるものがいいかなと思って」。森田さんは家の周りで草花を集め始めた。ヨモギ、クロモジ、ドクダミ、クズ。花屋では売っていない、野にある草たちを使うことにした。

少し前、森田さんはおいの病気をきっかけに新潟市北区で自然栽培を学び、畑で野菜を育てていた。その時に感じたある種の「心地よさ」にも後押しされた。
自然栽培とは、植物が持っている育つ力を生かすこと。「(農薬や化学肥料を使う)慣行栽培と自然栽培を並行している農家の方から『自然栽培の田んぼに行くと風が違う』と聞いて、それを感じてみたいと思ったんです」。風は分からなかったが、農家では目の敵にされる雑草がぐんぐん生えてくるのが嫌じゃなかった。「むしろ、草っていいなと思った」。さらに、収穫できずに放っておかれたキャベツも「きれい」と思えた。腐るのではなく、水分が抜けつつ色と形が残るドライフラワーに、初めて興味が生まれた。
花屋では、枯れた花は捨てていた。振り返ると「だれかの都合で調整されている花」に、違和感も芽生えていた。曲がった形に魅力を感じ、捨てられた枝で自分なりに工作してみると、自身の底に積み重なっていた思いや土を触った経験が、一つにつながった。「自然にあるもの、手の届くものを使いたい」。それは、目新しさを競い合う現場からも離れられて「しっくりくる」と思った。

「たわい」の一角では、最後に「線が足りない」とシャガの葉が添えられ、緑と花のあしらいが完成した。壁一面、初夏に萌える緑が息づく。映し出されているのは、弥彦の里山の風景だ。「いつも、見慣れた野草をすてきにしてくれる」と、たわいオーナーの岩田知里(ちさと)さん(40)は言う。野草も使う店の料理を、目でも印象付ける。
森田さんは「その辺にあるもので気楽に生けているから、見る人も扱う人も楽にしてもらえると思う」と話した。確かに、料理店にはほどよい緊張感と、見慣れた景色の安堵(あんど)感が溶け合っていた。
“畑からの手紙”届けたい…「花の命は短い」に込める美学
佐藤さゆりさん
果樹園のある農家に生まれ育った佐藤さゆりさん(40)のそばには、いつも草花があった。畑に行く道すがらや果樹園の木々の下には草花。幼い頃の遊び相手はもっぱら花だった。いろんな花をぎゅうぎゅうに詰めた花弁当や蕾(つぼみ)を凍らせた花氷を作った。中学時代、習いごとを勧められ、華道を選んだ。結婚して出産。「“お花”なんて言っていられる時じゃなかったけれど、こっそり」通い続けた。「花が心に効くと...