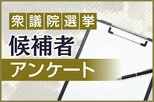原発事故時に住民の被ばくを抑えるために行う「屋内退避原発の事故などにより、放射性物質が放出されている中で避難行動を取ることで被ばくすることを避けるため、自宅など屋内施設にとどまること。国は原発からおおむね半径5~30キロ圏に住む人は、放射性物質が放出された場合は「屋内退避」するとしている。屋内退避中は戸締まりや換気設備を止めることなどが必要となり、数日間継続することも想定されている。」。新潟県内でその対象となる原発から半径5〜30キロ圏の避難準備区域(UPZ)原発などで事故が発生した場合に防護措置を行う区域の一つ。原発からおおむね5~30キロ圏は緊急防護措置を準備する区域=Urgent Protective action planning Zone=とされる。放射性物質が放出される前に屋内退避を始め、線量が一定程度まで高くなったら避難などをする区域。5キロ圏はPAZ=予防的防護措置を準備する区域=という。柏崎刈羽原発の場合、柏崎市の一部(即時避難区域を除く全ての地区)、長岡市の大半、小千谷市の全域、十日町市の一部、見附市の全域、燕市の一部、上越市の一部、出雲崎町の全域が当たる。の市町では、事故と地震や大雪が重なった場合の不安が根強く、詳細な対応基準を求める声が多い。しかし、屋内退避の運用を議論する原子力規制委員会原発推進を担う経済産業省から安全規制の役割を分離させ、原子力規制に関する業務を一元化した組織。東京電力福島第1原発事故を受けて発足した。国家行政組織法3条に基づき、人事や予算を独自に執行できて独立性が高い「三条委員会」として環境省の外局に位置付けられる。衆参両院の同意を得て首相が任命する委員長と委員4人で構成する。のチームや、内閣府の原子力防災担当は「範疇(はんちゅう)外」「解決済み」とするなど、すれ違いが続いている。
- 原発事故時の屋内退避「許容される行動示して」原子力規制委員会の運用見直し、全国38自治体から意見
- 豪雪時の原発事故、除雪どこまで可能? 屋内退避運用見直しに意見続出
- 原発事故時「屋内退避困難は検討対象外」、自治体に趣旨伝わらず
- 原発事故時の屋内退避「3日間目安」 原子力規制委員会検討チームが中間まとめ
11月12日にあった規制委の屋内退避検討チームの会合に先立つ11日、新潟市中央区では、県内30市町村でつくる「原子力安全対策に関する研究会」の実務者会議が開かれた。まさに屋内退避が議題で、国担当者も出席。発言した上越市の担当者は、規制委検討チームのこれまでの議論が、多くの家屋が倒壊するなど...