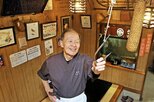北海道や太平洋側を含めて記録的な不漁といわれた2024年秋の鮭(シロザケ)。大型企画「碧(あお)のシグナル」の第2シリーズ「旅する魚」では信濃川水系の鮭を通し、流域の自然や文化を見つめます。(9回続きの7)
「珍しき鮭の子御越し候(そうろう) 賞翫(しょうがん)いたし候」
関ケ原の戦いで西軍にくみし、紀伊・九度山(くどやま)に蟄居(ちっきょ)となった戦国武将の真田昌幸が、国元の信州・上田から届いた鮭の子の塩漬けをおいしく味わっている。国元にいる家臣に書状をしたため、鮭を贈ってくれた長男・信之の妻、小松姫に感謝を伝えるよう頼んだ。
長野県に入ると、信濃川の名は千曲川となる。新潟県と同じく、長野も古くから鮭との結びつきが深い。
JR上田駅(上田市)のそばにある上小(じょうしょう)漁業協同組合は、ある鮭のはく製を大切に保管する。河口の新潟市から250キロほど離れた所で、2010年秋に取れた体長約60センチのメスの鮭。この辺りでは、65年ぶりという遡上(そじょう)に地元は沸いた。
「明治中期生まれのおやじから、『昔、鮭は買うものではなかった』と聞いたが、川を上った鮭を見たことがなかった」。組合長の北條作美(さくみ)さん(76)は感慨深そうに話す。
長野県の記録によると、千曲川水系では昭和初期に年間6万〜7万キロの鮭が取れていた。それが昭和10年代に急減する。国策で昭和15(1940)年までに、発電用の「宮中ダム」(十日町市)や「西大滝ダム」(長野県飯山市、野沢温泉村)が建設され、「取水により下流に減水区間が生じるなど鮭の遡上環境が悪化」したことが大きな要因とされる。
鮭は昭和25(1950)年の26キロを最後に「長野県の漁獲統計上から姿を消した」と記されている。

信州の鮭文化は縄文時代にさかのぼり、...