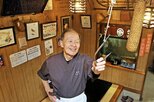北海道や太平洋側を含めて記録的な不漁といわれた2024年秋の鮭(シロザケ)。大型企画「碧(あお)のシグナル」の第2シリーズ「旅する魚」では信濃川水系の鮭を通し、流域の自然や文化を見つめます。(9回続きの2)
- <1>新潟のまちなか、続く鮭漁
「蔵王(ざおう)さま」と親しまれる金峯(きんぷ)神社(新潟県長岡市西蔵王)は1000年以上の歴史があるという秋の行事「王神祭(おうじんさい)」を受け継いできた。
2024年11月5日のお昼前、宮司の桃生(ももお)鎮雄さん(53)が神前に座り、包丁と鉄の菜ばしでまな板に載った鮭を手際よくさばいていた。こうした「包丁式」は平安時代に流行したといい、「全国にいまも行う神社はあるが、鮭を使うのは珍しいようです」と桃生さん。30分ほどで鮭を使った鳥居の形ができた。
この行事は農業、漁業、酒造の技を伝え、長岡の里を興した王神様に実りをささげる祭礼だ。「鮭を取らせてもらう感謝、そして畏怖の念を込めた所作で、一種の芸術活動です」
かつては神社に近い信濃川の鮭をささげていた。ただ鮭が取れなくなり、いまは「日本海側で取れた鮭」に。それでも祭礼後に、鮭が入った雑煮や大根おろしのなます、菊のお浸しをいただく伝統は変わらない。
桃生さんは「食べることは『命の更新』の意味合いも含んでいるんです」と説明する。今回も氏子や住民が集い、感謝の思いをかみしめた。

石のくぼみが二つの目と、そして口に見える。まるで鮭の頭のように。
魚沼市四日町の家々の間にたたずむ諏訪神社に、「鮭頭石(けいとういし)」がある。そのそばには「鮭魚(けいぎょ)明神」と書かれたほこらも立つ。金峯神社のように、中越地方ではいまも鮭信仰が残る。
信濃川を上った鮭は支流の魚野川でもよく取れていた。魚沼漁業協同組合で鮭漁に携わる、地元の目黒恒夫さん(72)は「子どもがまたぐと、ちょうどいい大きさ。でも、乗ると魚釣りがうまくならないって怒られた。とても大事にされていた」と振り返る。
いわれを...