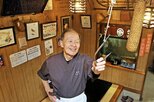北海道や太平洋側を含めて記録的な不漁といわれた2024年秋の鮭(シロザケ)。大型企画「碧(あお)のシグナル」の第2シリーズ「旅する魚」では信濃川水系の鮭を通し、流域の自然や文化を見つめます。(9回続きの3)
- <2>「鮭の神様」地域を見守る
新潟県長岡市の寺泊漁港に沿岸の小型定置網で取れた鮭を乗せて「招福丸」(9・9トン)が戻ってきた。2024年11月下旬の朝9時前、漁師たちがピチピチ跳ねる魚を1匹ずつ手際よく揚げる。
鮭は、寺泊漁業協同組合の漁師たちが狙う魚の一つ。海で定置網と刺し網を手がけるほか、大河津分水では鮭を捕まえ、ふ化放流に必要な卵を取っている。
2024年の定置網の鮭漁は10月前半から11月末まで。2万4千匹が取れた年もあったが、2024年は刺し網を合わせても580匹と桁が違う不振ぶりだった。漁師歴42年で、招福丸を率いる石井裕之さん(60)は「自然相手だから、どうしようもない。鮭漁の終わりの始まりですよ」とつぶやく。

鮭は「旅」をする回遊魚として知られる。新潟県の川で放された鮭の稚魚は、遠くオホーツク海やベーリング海を経て主に3〜5年で、元の川に戻ってくる。行程は数万キロにも上る。
その鮭が、新潟県を含め、全国で取れない。いろいろな説が上がる中、専門家に共通するのは、海に出た稚魚が十分育っていないとの見立てだ。
ふ化場で育った稚魚は、春までに県内各地の川で放され、海に下り、沿岸域で成長する。冷たい温度を好む鮭の稚魚にとって、適度な水温は5〜13度ほど。だが春に沿岸の水温が高いと、とどまる期間が短くなり、十分な大きさにならないまま、沖合に移動してしまう。
泳ぐ力が弱く、餌が十分取れず、他の生き物に食べられやすいといった影響が考えられる。長年、鮭の生態の研究に携わる北海道大名誉教授の帰山(かえりやま)雅秀さん(75)は海に出た時の水温が「後の生残率に大きく影響する」と語る。

ここで耐え残った鮭たちにも、次の関門が待ち受けているとみられる。
沖合に出た鮭は北上し、オホーツク海で最初の夏を過ごす。向かうルートは二つ。一つは日本海を北上して宗谷岬を経由するもの。もう一つが津軽海峡から太平洋に入り、北海道の東を通る経路だ。
「幼魚がオホーツク海にたどり着きにくくなっている」という仮説を唱えるのは、国の水産資源研究所さけます部門資源生態部長の佐藤俊平さん(49)。
道東の昆布森(こんぶもり)地区(釧路町)の沿岸を調査したところ、2015年以降、幼魚や稚魚が餌として好む高脂質で冷水性の大型動物プランクトンが減っていた。逆に小型で栄養価が低い暖水性のプランクトンが増える傾向がある。「幼魚がうまく成長できず、体のサイズが小さいため、捕食者や不適な環境から逃げにくくなっているのでは」という。
他に「オホーツク海も夏の水温上昇で生息域が狭まり、他のサケ類との競争にさらされる」「ベーリング海で、カラフトマスとの餌の取り合いに負けている」という帰山さんの見方、さらに鮭が帰る時期の沿岸水温が高く、鮭のルートや遡上(そじょう)のタイミングに響いているとみる研究者も。
人気の食べ物である鮭の不漁はよくニュースになる。盛岡市で12月中旬、「サケ学」の専門家約40人が参加した研究会でも話題になった。集まった研究者たちに取材してみると、「何が影響しているのか、はっきりしたメカニズムは正直にいって分からない」という声が一様に漏れた。
研究者も...