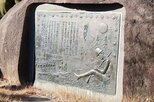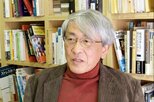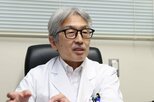不足すれば命にかかわる血液中の酸素濃度を、指先に軽く挟むだけで測れる医療機器がある。パルスオキシメーター。人体を傷つけることなくリアルタイムで状態を把握できることから、今や医療現場に欠かせなくなっており、新型コロナウイルス禍では呼吸不全の早期発見にも活躍した。その原理を見いだしたのは、新潟県長岡市出身で2020年4月に84歳で亡くなった青柳卓雄さんだ。医療機器メーカーの技術者として1974年に原理を発表してから、今春で50年となる。発明は海外でノーベル賞に推されるほどの功績だったが、評価されない時期も長かった。曲折に満ちた生涯を追った。
(東京支社・貝瀬拓弥)
ひらめきは心拍出量計の開発中…血中酸素濃度の測定に革命
「邪魔」な要素に着目、安定した測定を可能に
血液の赤色は酸素と結びつけば色合いが鮮やかに、そうでなければ暗くなる。パルスオキシメーターはこの性質を利用して、体の一部に光を当て、通り抜けた光の量によって血中酸素濃度を計測する。患者の呼吸がうまくいっているか、全身麻酔中に酸欠状態に陥っていないかなどを、継続的に調べることができる。
青柳卓雄さんが原理を着想したのは、新潟大工学部を卒業し、別の会社を経て1971年、日本光電(東京)に入社して間もなくのことだった。本人が学会誌に寄せた回顧録によると、上司から「何かユニークなものを開発せよ」との指示を受け、数人の部下と取り組んだという。

青柳さんは「医療の究極の姿は治療の自動制御」だと考えていた。まず人工呼吸器を自動制御できないかと模索し、その研究をしていた東大を訪ねた。
だが、東大の研究者からは「やめておきなさい」と言われる。人工呼吸器は患者の酸素状態に応じて動く必要があるが、当時は血中酸素濃度を連続して測れる実用的な装置がなかったからだ。血中酸素の計測は、青柳さんの研究テーマになった。
実際に開発に着手したのは、耳たぶに光を通して、心臓が送る血液量を測る心拍出量計だった。しかし、ここで壁に突き当たる。脈拍(パルス)によって血管が動く度に、測定値がぶれてしまうのだ。グラフの線が脈動のために細かなギザギザを描くのを見て悩むうちに、青柳さんは「待てよ」と思った。
「この脈波を分析すれば、酸素濃度を測れるのではないか」
体の一部に光を通して酸素濃度を測るアイデアは既に知られていた。ところが光は皮膚や脂肪など血液以外の組織も通るため、余計な影響を受けてしまい、...