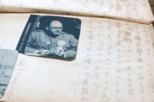戦後78回目の夏がやって来た。2023年も多くの新潟日報読者から、戦禍の記録や手記、遺品が寄せられた。その一つ一つが、戦時を生きた人々の証しだった。伝えたいと願う人がいる。受け継がなければと誓う人がいる。過去から託された思いを未来につなげ、平和を考える。
× ×
幼い日に空襲を生き延び、今年5月に91歳を迎えた長峰克英さん=新潟市北区=は思う。「戦争そのものの本体は、人間の心の中に潜んでいる」と。
その思いは、8月を重ねる度に色あせるどころか、焦燥感を伴い胸に迫ってくる。「戦争には新しいも、古いもない。違いは武器や戦術ぐらいだ。戦争をするのは、人間の意志によるものに変わりはない」
1932年生まれの長峰さんは東京都渋谷区で育った。6人兄妹の次男で、生家はJR恵比寿駅近く。今はおしゃれな店が並ぶ代官山付近にあった。心も体もぐんと育つ10歳前後の記憶が戦禍と重なる。
日本軍による米国ハワイの真珠湾攻撃から2年後の1943年4月、長岡市出身で連合艦隊司令長官の山本五十六がパプアニューギニア上空で散った。
既に戦況は悪化していた。6月、東京で営まれた山本の国葬に、海洋少年団だった長峰さんも参列した。静まり返った斎場、黒塗りの車、白いひつぎ、響き渡る弔砲…。どれも鮮明に覚えている。
「山本五十六は誰もが知っている大変立派な人。まさか死ぬなんて。これからどうなるんだろうと、何とも言えない不安を感じた」
■ ■
敗戦が忍び寄っていた1945年3月、下町の人口密集地を狙った「東京大空襲」があり、その後も都内は空襲に見舞われた。
5月。代官山付近に飛来した米軍のB29爆撃機から、焼夷(しょうい)弾が次々と降り注いだ。雨粒のように襲いかかる火の粉が瞬く間に火の海と化し、辺りをのみ込んだ。とにかく逃げた。中学1年生だった長峰さんは家族と手を取り合い、叫び、必死に坂を上った。
火と煙と怒声が渦巻いていた。あまりのすさまじさに「半分、夢を見ている感じだった」。家族全員、何とか逃げ延びた。
朝、自宅に戻ると見渡す限り焼け野原になっていた。くい一つ残っていなかった。兄の克昌さんと一緒に庭先に掘った防空壕(ごう)に隠しておいた布団も食べ物も、焼き尽くされた。それを見た瞬間、子どもながらに一気に疲れを感じ、動けなくなった。
つい昨日までそこにあった人の営みが、笑顔が、うそのようだった。あるのは鼻の奥まで粘り着くような異臭。人が殺される戦争の臭いだった。
「焦げた臭いではない。物が腐ったような、酸っぱいに近い、例えようのない臭い。ずっとまとわりつく、粘っこい臭いだった」
■ ■
7月、一家は長峰さんの父・喜一さんの実家がある現在の阿賀野市に疎開。8月15日の終戦を迎えた。
長峰さんは大学卒業後、公務員として働き、家族にも恵まれた。子どもらが戦争を体験していないことに幸せを感じる。しかし、同時に「戦争を知らないということは必ずしもいいとは思えない」とも考える。知らずにいると、気付かぬままに戦争にからめ取られかねないと恐れるからだ。
「だからこそ戦争について、人間について話し合いをしていくことが必要ではないか」。若い人たちが戦争を考えるきっかけになればと退職後に編んだ体験記は、今も手元にある。
(報道部・桑原健太郎)