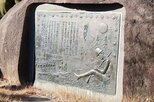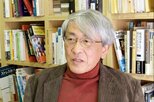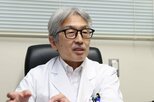新潟県の「佐渡島(さど)の金山」の世界遺産登録が大詰めを迎えた。江戸期以降、金銀産出や北前船の寄港で大いに隆盛した佐渡。港町としてにぎわった相川、小木、両津には時代は違えど花街があり、今もその面影を残す。「最後の小木芸妓(げいぎ)」と自認する伊藤和子さん(84)の話を聞き、両津では元妓楼(ぎろう)の建物で宿を営む「金沢屋旅館」を訪ねた。相川ではガイドと遊郭跡などを巡って往時をしのんだ。栄華の裏には悲話もあり、光がつくる影の奥深さがうかがえた。
(佐渡総局長・石塚恵子)
華やかな姿から一転、日中は…水上勉が感じた「ギャップ萌え」
「最後の小木芸妓」伊藤和子さん
半玉(見習い)時代から30年以上小木の花街に身を置いた佐渡市小木町の伊藤和子さん。「私は最後の小木芸妓。いわば生き証人」という。
生まれは小出町(現魚沼市)。佐渡からスカウトに来た料亭の女将(おかみ)の家に入る形で来島した。中学校に通いながら踊りなどお稽古ごとに通った。一元という置き屋に所属。20代半ばで独立し、45歳ごろまでお座敷に出た。源氏名はなく和子と呼ばれた。
小木には芸に厳しい伝統があり、稽古はつらかった。見習いとして一緒に入った2人はまもなく辞めたという。「全国からお客が来て、それぞれ故郷に民謡がある。リクエストされて、知らないというわけにはいかない」。一人前になってからも稽古は続いた。

昭和の小木は華やかだった。島中から声がかかり、迎えの車で出かけた。「小木芸妓は朗らかで、芸がいいから呼ばれた」と伊藤さん。一晩に3軒掛け持ちすることもあった。
小木芸妓といえば、明治の文豪尾崎紅葉とお糸の恋が有名だ。1899年、病気療養のため来島した尾崎は貸座敷「ごんざや」で出会ったお糸にほれ込んだ。毎晩のように一緒に過ごし、部屋を取った宿に泊まることはなかった。
伊藤さんも、戦後日本を代表する作家水上勉の旅行エッセーに登場する。ごんざやで出会った芸妓「A子さん」として書かれるのが伊藤さんだ。日中は家業の漁を手伝い、トビウオの水揚げをすると聞いた水上は関心を持ち、翌日会いに行く。
すると、伊藤さんはとっくりセーターに汚れたズボン姿で、包丁を片手にトビウオのはらわたを取っていた。前の晩、ほろ酔いだった芸妓が「座敷づとめの花やかさをケロリと消して、小木の漁師妻として」働く姿に、今で言う「ギャップ萌(も)え」したようだ。「尾崎紅葉が、この町に足をとどめ、二、三日では帰れない愛着を感じて、馴染んだお糸さんも、あるいは、このようなきびきびした働き妻だったか」と記している。

水上は物静かな人だったというのが伊藤さんの印象だ。「(家に)来たいと連絡があった。私は頭にこうして手ぬぐいをしてね」と遠い記憶を手繰った。
自宅には、水上が書いた色紙がある。「自分一人この道を歩く」。「これは私のこと。見ると思い出がよみがえる。楽しいこともあったけど、つらいことも多かった」としんみり思いにふけった。

◆相川、小木、両津…花街の歴史は三者三様
鉱山の創業期、相川地区の花街は佐渡金山に近い山先(やまさき)町にあった。始まりは不明だが、江戸初期の1613年には税を納めて公認で営業しており、江戸吉原の開設より早かった。古くは上相川茶屋坂周辺が歓楽街として栄えており、寛永(1624〜44年)のころ現相川会津町に移った。約280人ほどが働いていたとみられる。
奉行所に近いという理由で1717年、町北端の水金町に集団移転させられ、太平洋戦争後ごろまで続いた。移転時の廓(くるわ)は11軒。経営は変わったが、幕末、明治も11軒から増減はなかった。この町以外は遊郭を営むことが禁じられ、非公認の営業は摘発の対象となった。
相川地区と並んで古い歴史を持つのが小木地区。小木港は江戸期の元和(1615年ごろ)には越後への基地として栄えており、金銀の積み出し港、西回り航路、北前船の寄港地として繁栄。非公認の遊女が多くいた。「佐渡年代記」には1842年当時、74人を数えたとある。
三味線や舞踊などで客を楽しませる芸妓は明治期、小木に13人いたという記録がある。
両津地区には幕末から明治期にかけ、両津夷(えびす)に5軒、両津湊に2軒の妓楼があり、50〜60人の女性がいた。新潟-両津間の定期船運航など、両津夷が佐渡の表玄関になってから増加、1898年ごろには両津夷に20軒、両津湊に10軒が軒を連ねた。最盛期には、芸妓約20人を含め200人ほどが働いていたとされる。
唯一残る元妓楼、往時の絢爛さは今も…
両津地区の「金沢屋旅館」
「両津欄干橋 真ん中から折りょうと/舟で通うてもやめりゃせぬ」。遊郭に通う男の心情が両津甚句にうたわれる。橋で結ばれる両津夷、両津湊の住民は互いに対岸の廓(くるわ)に通っており、橋が折れても舟で...