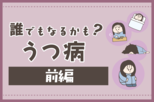2025年9月9日
PwC Japanグループ
PwC Japan、サステナビリティ経営を通じた企業価値向上へ、
3つの注力領域を策定し支援体制を拡充
―複雑化、高度化するサステナビリティ対応へ、
10月から順次新サービスを展開―
PwC Japanグループ(グループ代表:久保田 正崇、以下「PwC Japan」)は、サステナビリティ経営を通じた企業価値の向上を支援するため、新たに3つの注力領域を策定して体制を拡充します。企業のサステナビリティ経営が実行・成果創出を強く求められる段階に入ったことを踏まえ、経済合理性を考慮してより実効性の高い取り組みを支援するのが特徴です。企業単体の支援にとどまらず、産業の垣根を越えたエコシステムの構築や、業界団体や政府関係機関と連携する活動の推進に貢献することも目指します。3つの注力領域では10月以降、新たなサービスを順次、開発・提供していく予定です。
[画像1]https://digitalpr.jp/table_img/1803/117563/117563_web_1.png
3つの注力領域が必要となる背景
現在、気候変動、生物多様性、資源・廃棄物、人権といった単独では対応が難しい種々のサステナビリティ課題が表出し、悪化・変容し続けるなか、対応は待ったなしの状況となっています。企業はこうした多様な課題に全方位的に対応するのみならず、各種の規制・法令を遵守することが求められています。一方で、課題への取り組みが進展するにつれ、施策間で相互影響(トレードオフまたはシナジー)が生じたり(例えば再生可能エネルギーとネイチャーポジティブの関係など)、また、データを活用した取り組みの巧拙による企業負担の軽重などが認識され始めたりしています。さらに近年では、環境や人権問題のほか、紛争や経済安全保障などの地政学的要因による資源や素材の安定的な確保への影響も顕在化し、最悪の場合は製造活動の中断といったサプライチェーンリスクに直結することもあります。
このように企業はこれまでになく多くのテーマに同時に対応し、変容し続けるリスクに対処する必要に迫られています。その取り組みにおいては、経済合理性と実効性を備えたサステナビリティ施策と、将来に向けた機会の創出を検討し、市場の期待に応え、それを超え続けることが必要です。最近の動きとして、ネットゼロや資源循環といった大きなテーマに対しては、企業単体での取り組みを超え、大きなインパクトを求めて企業連合によるEnd to Endでの課題解決に向けた取り組みなども見られるようになっています。 PwCの調査(※1)においても、経済構造の急速な再構築が始まっており、今後10年の間に新たな社会のニーズに対応する重要性が示されています。
※1:https://www.pwc.com/jp/ja/press-room/2025/value-in-motion.html
こうした状況において、企業は事業活動を長期にわたって持続可能にするために、サステナビリティ課題に対処するだけではなく経済合理性を持った強靭なサプライチェーンを構築し、競争力を強化していくことが不可欠です。そのためには、バリューチェーン全体を包含した構造改革、ひいては産業全体のエコシステムの再定義が必要となります。また、制度面でもオペレーティングモデルの変革を求める規制やサステナビリティの開示基準が日本を含む世界各国において整備され、戦略から実行、開示に至るまで広範な対応が企業の競争力の源泉となる時代が到来しています。
3つの注力領域の概要
PwC Japanでは、このように企業を取り巻くサステナビリティ環境が大きく変化するなか、経済合理性を持ったサステナビリティ経営の支援、および持続可能な産業の発展、社会全体のサステナビリティを実現するために、特に重要と考えられる3つの分野を注力領域と定め、これらの実行に適した組織体制を整備し2025年7月より始動しました。新たな体制の下で下記の注力領域を定め、支援を提供してまいります。
① サステナビリティ戦略策定支援(ホリスティックアプローチ)
多様化する環境・社会課題と、経済合理性(財務的パフォーマンス)に対して、個別に検討し対応するのではなく、複数要素を総合的(ホリスティック)に捉え、全体最適化を図った戦略を提示します。その戦略に基づいて変革の道筋を示し、対外的な開示につなげる支援までを行います。これにより、企業は中長期的な施策ポートフォリオを組み直し、資源調達戦略、効率的な経営資源の配分を策定することが可能になります。
サービス例:課題間の相互影響評価に基づくサステナビリティ戦略策定支援、施策ポートフォリオ変革支援、ブランディング戦略策定支援など
② サステナビリティサプライチェーン変革支援(システミックアプローチ)
脱炭素や循環経済などの複雑な課題を解くサステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)の実現にあたっては、企業の一部門だけではなく全社、さらに複数企業横断でのエコシステム開発が必要になります。PwC Japanでは、システム思考に基づくエコシステム開発手法(システミックアプローチ)を活用し、ルール、ファイナンス、テクノロジー等の革新に焦点を当てたビジネスモデルの変革と、産業・企業の垣根をまたぐ事業構造改革やサプライチェーン変革などの検討、実装を支援します。
サービス例:サプライチェーン機能改革、サプライヤーエンゲージメント、サステナブルサプライチェーン構築(脱炭素、人権)、システミック投資など
③ 法定開示を起点としたサステナビリティ情報管理・統合思考経営支援
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)や企業サステナビリティ報告指令(CSRD)などのサステナビリティ開示基準への対応を起点に、企業の情報開示戦略から実行までの一連の取り組みを効率的・効果的に支援します。また、サステナビリティ情報の可視化を起点に、企業のサステナビリティ対応が、自社の顧客への価値を生み出す取り組みにつながるようにマテリアリティの適正化、戦略の高度化、価値創造ストーリーの構築などを提供します。統合思考に基づき、企業の戦略立案、変革、開示といったサステナビリティ経営全般にわたって、中長期的な企業価値向上を支援します。
サービス例:情報開示戦略立案、内部統制、保証対応、サステナビリティ情報管理プラットフォームなど
また、これらの注力領域のサービス提供の基盤として、デジタルトランスフォーメーション(DX)によるサステナビリティ業務の高度化・効率化支援、サステナビリティ専門知見の提供、業務管理のためのマネージドサービス支援なども強化してまいります。
[画像2]https://digitalpr.jp/simg/1803/117563/600_452_2025090814454668be6d8ad0235.png
PwC Japanではこれらの注力領域に係るサービス開発を加速し、産業や社会の構造変化を乗り越え、新しい価値を生み出す支援を推し進めてまいります。そのために、10月以降、以下のようなサービス開発やイベントを予定しております。
ホリスティックアプローチに基づく企業の意思決定を支援する新サービス
システミックアプローチに基づく業界横断エコシステム変革支援サービス
サステナビリティサプライチェーン構築に向けたリスクマネジメントの包括的サービス
サステナビリティ情報管理プラットフォームの構築支援および高度化
企業の最高サステナビリティ責任者等を対象とした企業価値向上を目指すコミュニティの形成
なお、3つの注力領域のコンセプトや、全体構造を示す書籍『サステナビリティ新時代 成果を生み出すホリスティック×システミックアプローチ』を7月に発行しています。
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/publication/new-sustainability.html
PwC Japanでは、この注力領域を支えるサステナビリティ課題の専門性および、戦略立案、変革・実装、情報開示といった経営課題に関わる専門性を、監査およびブローダーアシュアランスサービス、コンサルティングや、ディールアドバイザリー、税務、そして法務といったグループ全体にわたる幅広い分野で有機的に結合し、サービスを提供していきます。また、グローバルネットワークの各分野の専門家とも連携しながら最先端の知見蓄積を強化していきます。
PwC Japanのサステナビリティ経営支援サービスの詳細
https://www.pwc.com/jp/ja/services/sustainability-coe.html
以上
PwC Japanグループについて:https://www.pwc.com/jp
PwC Japanグループは、日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファームおよびそれらの関連会社の総称です。各法人は独立した別法人として事業を行っています。
複雑化・多様化する企業の経営課題に対し、PwC Japanグループでは、監査およびブローダーアシュアランスサービス、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、そして法務における卓越した専門性を結集し、それらを有機的に協働させる体制を整えています。また、公認会計士、税理士、弁護士、その他専門スタッフ約13,500人を擁するプロフェッショナル・サービス・ネットワークとして、クライアントニーズにより的確に対応したサービスの提供に努めています。
(c) 2025 PwC. All rights reserved.
PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. Each of such firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.