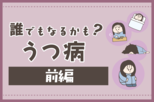京都産業大学(京都市北区/学長:在間敬子)は、和歌山県みなべ町と「包括的連携協力に関する協定」を締結しました。本協定を機に、世界農業遺産「※みなべ・田辺の梅システム」を中心に、地域資源の活用と次世代人材の育成を目的とし、教育・研究・産業振興など多面的な連携を推進していきます。
京都産業大学は、令和7年9月8日、和歌山県みなべ町役場にて、みなべ町と「包括的連携協力に関する協定」を締結しました。みなべ町は梅の生産を通じて自然環境と文化を守り続けてきましたが、今回の協定により、本学の先端科学技術研究所 生態系サービス研究センターを中心に、梅林に集まる生物調査やミツバチによる受粉促進の研究などを進め、地域振興、教育、研究、商品開発など幅広い分野での連携を強化します。
【主な連携内容(予定)】
•ミツバチによる梅受粉や保全に関する共同研究
•梅干し商品やスポーツ食品の共同開発
•学生による地域体験型ツアーの企画・実施
•生物多様性教育や世界農業遺産に関する教材開発
•地元高校生との共同研究・発表(FAO国際会議等)
•学生主体のPRイベント「五感で楽しむUME SYSTEM」の開催
先端科学技術研究所 生態系サービス研究センター 高橋純一センター長のコメント
「みなべ・田辺の梅システムは、地域の人々が守り育んできた大切な財産です。私たちは、この梅システムを理解し、生態系サービスの仕組みを明らかにするために、生物多様性の調査やミツバチの受粉研究を地域の皆さまと一緒に進めてきました。今回の協定を機に、さらに連携を深め、研究成果を農業や暮らしに活かすとともに、学生や地元の高校生が現場で学び、共に成長できる教育の場としても発展させていきたいと考えています。
大学と地域、そして次世代を担う若者たちが力を合わせることで、新しい発見や価値を未来へと受け継ぐことに貢献してまいります。」
※みなべ・田辺の梅システム
2015年12月、400年前から受け継がれてきた持続可能な梅を中心とする農業システムが世界農業遺産に認定されました。みなべ・田辺地域では、薪炭林を残しつつ、山の斜面に梅林を配置することで、水源涵養や崩落防止などの機能を持たせながら高品質な梅が生産されていること、梅の花の受粉におけるニホンミツバチの利用や里山・里地の自然環境の保全により、豊かな農業生物多様性を維持していることなどが、高く評価されました。
2025年 創立60周年 Be Innovative. 京都産業大学
【2026年4月、新しい学びが誕生します。】
■文化学部
文化構想学科・文化観光学科・京都文化学科へ再編
■アントレプレナーシップ学環 新設
<関連リンク>
・京都産業大学 先端科学技術研究所 生態系サービス研究センター
https://www.kyoto-su.ac.jp/wr-research/seitai/index.html
・世界農業遺産「みなべ・田辺の梅システム」紹介ページ
https://www.giahs-minabetanabe.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
京都産業大学 広報部
住所:〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
TEL:075-705-1411
FAX:075-705-1987
メール:kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/