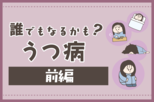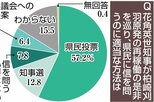「第30回釜山国際映画祭」で3人揃って最優秀俳優賞を受賞した北村匠海、林裕太、綾野剛が出演する映画『愚か者の身分』。劣悪な環境で育ち、気がつけば“闇バイト”に手を染めてしまった若者たちが、傷つきながらも必死に生きる姿を描く。3人はそれぞれどのようにこの作品に向き合い、“愚か者”というタイトルにどんな思いを抱いたのかを語った。
――本作の第一印象を教えてください。
【北村】脚本を読んだときにまず感じたのは、視力を失うという役柄をどう生き、何をなすのか――それを表現することにとても興味がわきました。そして、この作品に登場する剛さん演じる梶谷と、裕太演じるマモルという存在が、すでに僕の中で強く届いていました。世代や立場の違いがある中で、どう向き合っていくか。剛さん、僕、裕太――三世代ともいえる構成の中で、自分がどのように“つなぐ”存在になれるのかを考えました。それはまさに、僕ら20代後半から30代前半の世代が現実でも課せられているテーマのように思えて。だからこそ、この作品でその役割を担えることに大きな喜びを感じましたし、挑戦したいと思いました。
【林】物語の流れとして、とても面白いと思いました。緊迫感もありますし、「戸籍売買」という闇バイトを題材に、今の社会問題ともきちんと結びついているところにまずひかれました。ただ、最後まで読み終わったあとに一番心に残ったのは、そうした問題提起そのものよりも、人の“生き方”や、“人に何をしてあげられるか”“何を受け取って生きていくのか”というテーマでした。そこに描かれている人間の根源的な部分が深く胸に刺さって、「この作品はすごくいいな」と。そして、自分もぜひ“マモル”という役を通して、その世界の一端を演じてみたいと思いました。
【綾野】脚本を読んだときにまず芽生えたのは、闇ビジネスに飲み込まれた登場人物たちの痛みや孤独を、目を背けず見つめ、知る。そして受け止める映画でありたいという想いでした。
――「第30回釜山国際映画祭」で北村さん、林さん、綾野さんの3人がそろって最優秀俳優賞を受賞されましたが、実際は共演シーンがほとんどないそうですね?
【綾野】ワンシーンだけです。それも、同じ画面に3人が映っている程度で、撮影も1日だけでした。
【林】そうなんです。現場ではちゃんとお話しする時間があまりなくて、初めてお会いした本読みのときのほうが、いろいろ話せた印象があります。それでも、撮影現場でお会いするたびに温かく声をかけてくださって、本当にうれしかったです。今回の撮影では深く関われなかったですけど、取材や舞台あいさつでご一緒できるのがすごくうれしいです。
――北村さんは、前半は主に林さんと、後半は綾野さんと共演されていました。それぞれと演じるとき、緊張感や表現のトーンがまったく違ったのでは?そのあたりで意識されたことや、手応えを感じたことはありますか?
【北村】本作では“世代のバトン”のような関係性が物語の根底にあって、「生きる」を授けていくというテーマが、自分の中でもすごく一致していたんです。だから、裕太に対して“役者として何を残せるか”、剛さんから“何を受け取れるか”ということを、常に意識していました。
裕太といるときの自分と、剛さんといるときの自分――芝居の“質感”がまったく違う。意識的に変えていた部分もありますが、自然と変わっていたという感覚です。
剛さんとのシーンでは、僕はほとんど“目が見えない”状態で演じていました。だからこそ、剛さんの声の響きや息づかい、空間を流れる風の動き――そういった視覚以外のすべての感覚で芝居を受け止めていました。ある意味、すごく贅沢な時間でしたね。
声だけが頼りだからこそ、「今どんな表情をしているんだろう」と想像するしかない。目の前に“正解”がないからこそ、完全に委ねるしかない。その“もたれかかる”感覚を、剛さんなら必ず受け止めてくれるという信頼のもとで芝居ができました。
一方で、裕太との芝居はまったく逆。彼の持つピュアなエネルギーを目の前で受け取って、どう引き出すか、どう支えるか――とにかくその瞬間瞬間で、自分が何を与えられるかを意識していました。だから“任せる”というより、“共に成長していく”ような芝居。まるで作風の違う映画を2本撮っているような感覚でした。
裕太と過ごす時間は、まさに“青春”なんですよ。タクヤにとっても、マモルにとっても。それは若さだけじゃなく、誰かと真剣に向き合う時間という意味での青春。
剛さんとの時間は“逃走劇”であり、“暗闇のロードムービー”のようなものでしたので、それもまたある種の“青春”と呼べたのかもしれないですけど、タクヤにとっては失ったものが大きすぎて、どこに光があるのかも分からなくなる瞬間があった。
だから、撮影中は自分の中でも感情のバランスを取るのが難しかったです。それでも永田琴監督が常に包み込むように導いてくれたから、安心してその世界の中で生きることができたと思います。
――綾野さんは、北村さんとのシーンをどのように感じていましたか?
【綾野】この作品のラストをどう解釈するかは人それぞれだと思いますが、梶谷には、何かを失ったということよりも、救いを感じ希望を見出していた気がします。「ラストチャンスをもらった」という感覚でした。
――林さんは、北村さんから大きな刺激を受けていたように見えましたが…。
【林】マモルにとって、頼れるのはタクヤしかいなかったんですよね。もちろん現場ではいろんな方に支えてもらっていましたが、一番近くで、僕の声を一番よく聞いてくれていたのは匠海くんでした。だから、頼るというより“すがるような気持ち”もあって。匠海くんのお芝居をちゃんと受け止めて、それに込められた愛情をどう表現として返していくか――それを常に考えていました。それがすごく刺激的でもあり、幸せな時間でもありました。
――本作のタイトルにある“愚か者”には、どんな意味を感じましたか?そこから得たインスピレーションを教えてください。
【林】僕は“選択肢のなさ”だと思いました。そうすることでしか生きられなかった人にとっては、決して愚かなんかじゃない。でも、外から見たら「なんでそんなことを?」と愚かに見えるかもしれない。この作品の“愚か者”という言葉は、社会的に追い詰められた人の「選択肢のなさ」とつながっている気がします。そこにすごくリアルな痛みを感じました。
【北村】僕は“自己受容”という言葉が浮かびました。自分を受け入れることって、すごく怖いことなんですよ。現状や弱さ、ネガティブな感情から目を背けた方が楽な瞬間って、誰にでもある。でも、それこそが“愚か”なのかもしれない。この作品に出てくる彼らは、自分たちを「俺たちは愚か者だ」とどこかで認めているようにも見える。だからこそ走れるし、どんなに笑われても、肯定されなくても、笑いながら前に進める。自己受容って、弱さでもあるけど、同時に強さでもあると思うんです。自分を丸ごと受け入れられる人間こそ、本当の意味で強いのかもしれません。
【綾野】今の2人の話を聞いていて思うのは、“愚か者”という言葉の裏には、“人として生きること”への実感があるということです。誰にでも、迷ったり、弱さを見せたりする瞬間がありますが、そういう“人間らしさ”の中に、愚か者の姿があると思います。誰にでも少しずつ“愚かさ”がある。愚か者って、決して悪人のことではないですし、自分の心と正直に向き合う瞬間に現れるものだと思うんです。この映画に出てくる登場人物たちは、社会の最前線で傷つき、苦しみながらも、それでも生きようとしています。だからこそ、誰も彼らを軽々しく“愚か者”とは呼べない。むしろ、その言葉自体が、人間の尊さを映し出している。そう思うと、本作のタイトルはすごく美しいと思います。