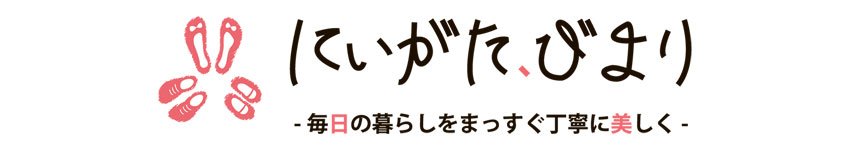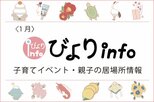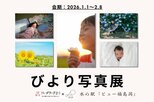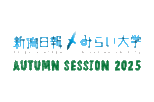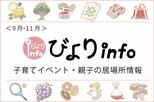弥彦山(634メートル)の麓に鎮座する弥彦神社(新潟県弥彦村)は、越後一宮として知られ、古くから人々の信仰を集めている。創建2400年ともいわれ、万葉集にもその名が登場し、鎌倉、江戸両幕府から寄進を受けてきた霊験あらたかな場所だ。近年はパワースポット人気の高まりを受け、若い参拝者も多い。新型コロナウイルス禍で落ち込んだ気分を晴らすため、村内のパワースポットを巡った。(三条総局・山崎琢郎)
弥彦神社の入り口は高さ約6メートルの一の鳥居だ。鳥居を別の柱で支える両部鳥居で、広島県の厳島神社などにも見られる。かつて参拝者が身を清めた御手洗(みたらし)川の上流には「玉の橋」がある。社殿が消失した明治末期の弥彦大火でも橋は無事だったという。

神様だけが渡れるという玉の橋。御手洗川が下を流れる
境内に入ると高い木々が立ち並び、神聖な空気に包まれる。神の使いとされる鹿がのんびりくつろぐ姿も癒やされる。参道の途中にある二つの石は「火の玉石」、別名「重軽(おもかる)の石」と呼ばれ、一度持ち上げて願いを念じ、もう一度持った時に重ければかなわない、軽ければ成就するという。観光客の人気スポットにもなっており、長岡市から訪れていた20代の女性2人は「すてきな人に出会えるか尋ねてみたら重かった。まだ望みは遠いみたい」と笑い合っていた。

願いがかなうかどうか占う「重軽の石」
「弥彦神社は女性神だから、カップルで参拝すると嫉妬されて別れる」という俗説がある。参拝者に聞いてみると、多くの人が信じていた。弥彦観光協会の三富克是事務局長(65)に真相を聞くと「弥彦神社が祭っているのは天香山命(あめのかごやまのみこと)(伊夜日子大神(いやひこおおかみ))という男性神。恋人同士で来ても大丈夫」と話す。ではなぜ迷信が広まったのか。三富さんによると、参拝に訪れる旦那衆が帰りに芸者遊びをしたいため「弥彦神社は女性神だから夫婦で行くと別れる」と、妻の同行を断ったことから始まったそうだ。
弥彦山を背後に建つ拝殿と併せて参拝したいのが、八つの摂社、末社だ。それぞれに御利益があり、特に「勝(すぐる)神社」は、その名前にあやかろうと弥彦競輪の観戦者がよく訪れるそうだ。
神社の神体山である弥彦山頂上にもパワースポットがある。四季の植物を楽しみながら徒歩や自動車、ロープウエーで上り、徒歩で10分ほど歩くと天香山命と妻の妻戸大神(つまどのおおかみ)(熟穂屋姫命(うましほやひめのみこと))が祭られる御神廟(ごしんびょう)に到着する。すぐそばの札所にはお守りやおみくじと並び、大きく「縁」と書かれた絵馬がある。良縁を願って「2礼4拍手1礼」で手を合わせた。山を挟んで越後平野と遠く佐渡島が見える。神社を巡り、汗をかいたらすがすがしい気分になった。これもパワースポットの効果かもしれない。

弥彦山の山頂にある御神廟
味覚でも開運を楽しみたい。弥彦村の9軒の宿や飲食店では「開運だしカレー」を味わえる。神社や神棚に供える「神饌(しんせん)」のかつお節や昆布のだしと、スパイスが効いた少し大人向けのカレーで、見附市出身のスパイス料理研究家一条もんこさんがプロデュースした。古くから魔よけにも用いられた「クローブ」、恋愛のお守りだった「クミン」など4種のスパイスを煮込んでいる。

村内9店で提供する「開運だしカレー」。店舗によって盛り付けや提供時間が変わる
開運パワーを持ち帰りたい人には、弥彦おかみ会が考案したパワーグッズがお薦めだ。鳥居や弥彦名物をあしらった手拭いやポーチのほか、幸せを掃き集める願いを込めた「開運ミニほうき」も販売している。おかみ会の白崎陽子代表世話人(47)は「弥彦だけのパワーグッズを手にしてもらいたい。今後、新しい商品も考えている」と話す。土産物として開運のお裾分けにも重宝しそうだ。

弥彦おかみ会が考案したパワーグッズ
■関連サイト「越後一宮 彌彦神社」(外部サイトに移動します)