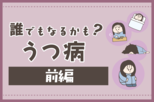東日本大震災で被災し、保存か解体かで議論になった岩手県大槌町の旧役場庁舎=2011年4月
2011年の東日本大震災で被災し、津波の痕跡を伝えた各地の「震災遺構」について、岩手大准教授の坂口奈央さん(50)が、住民の目線で論じた著書「生き続ける震災遺構」を出した。
これまで外部の研究者やメディアは主に建物などを遺構として扱ってきた。著書では、被災しながらも回復した島や樹木といった自然を、住民が「おらほ(私たち)の遺構」と呼ぶようになった経緯を紹介。日常を取り戻す道しるべや、復興のシンボルとしての価値が生まれたと指摘した。
大災害のたびに、そのインパクトを象徴する遺構を保存するか解体するかで論争になるが、直後は外部の人たちの主張が目立つことが多い。東日本大震災でも、津波の教訓を継承し...
残り779文字(全文:1079文字)